Information > コラム
2025.5.9
スタートアップオーナー・シリアルアントレプレナーの離婚 ~後編:株価評価の難しさと実務上の留意点~
離婚にともなう財産分与の場面において、スタートアップ(ベンチャー)創業者やシリアルアントレプレナー(連続起業家)特有の問題・リスクとして、以下の点が挙げられます。
▼スタートアップ創業者特有の問題・リスク
①額面上の財産規模が大きかったとしても、財産のほとんどは自社株でありキャッシュがほとんど無い。
②財産分与として自社株を相手方に渡すことができない(資本政策に支障が生じるほか、株主間契約等で譲渡が制限されているケースが多いため。)。
③ある時点で自社株に財産的価値があったとしても、その後どうなるか分からない(財産的価値が大きく下落する可能性がある)。
今回は、このような問題・リスクについて検討・対処するうえでかかせない、スタートアップの株式の評価方法について取り上げます。
スタートアップを巡る離婚問題について、以下の点についてはこちらのコラムで解説していますのでご参照ください。
1.離婚がスタートアップの事業存続やエグジットに与える影響について
2.別居後の価値上昇と財産分与について
3.他の株主との関係と、株主間契約等について
広く会社経営者に関係する離婚問題については以下のコラムも参照ください。
・特有財産の立証 ー財産分与を回避する方法ー
・ストックオプション・RS(株式報酬)の財産分与
・会社・子ども名義の資産は財産分与でどう扱われるか〜第三者名義の財産の取扱い〜
※資産承継対策の一環として、IPO(上場)前に資産管理会社つくり、そこに自社株を移した上で、当該資産管理会社の株式を子どもに持たせた場合、子ども名義で保有する資産管理会社の株式は財産分与の対象になるか論点になることがあります。第三者名義の財産を巡る離婚問題です。
・財産分与の割合は”常に50%”ではない 2分の1ルールが修正されるケースとは(5%、30%、40%とした裁判実例付)
※スタートアップならではの急成長の要素や努力の成果が考慮される可能性があります。例えば別居後の著しい価値上昇があった時、そうして上昇した価値をも財産分与に取り込まれると判断されるとき、それを50%にて分け合うのは不公平であるとして傾斜をつける、という考え方です。
・スタートアップ専用 婚前契約(夫婦財産契約)雛形

岩崎総合法律事務所はスタートアップとそこに関わる皆様を応援しています。
目次
- はじめに
- 会社の消滅・後退リスク
- VCからの資金調達と影響
- 評価の時間軸と将来価値の評価
- 優先株と普通株の評価
- 希釈化ベースでの株式評価
- 株式の評価における鑑定の有用性
- 税制適格ストック・オプションの評価に関する問題
1.はじめに
スタートアップなど非公開会社の株式は、上場企業と異なり市場価格が存在しないため、その評価を巡って争いが生じることが少なくありません。
特にスタートアップの場合、成長段階に応じて株価が大きく変動します。別居時、現在、将来の時間軸において果たしてどの時点を捉えて評価するべきか、財産分与時における公正な評価方法を見出すことが課題となります。
株式評価には複数の方法がありますが、どの方法を採用するか、またその際の前提条件や算定基準によって評価額に大きな幅が生じることは避けられません。
財産分与の本質は公平性の確保にあります。理論上の評価額も重要な考慮要素となりますが、最終的に資産の実質的な価値を適切に検討することが重要です。
以下では、特にスタートアップ特有の株式評価に関する論点を取り上げて説明します。
2.会社の消滅・後退リスク
スタートアップ企業は、他の中小企業と比べて事業リスクが高いとされています。
中小企業庁2023年版「中小企業白書」によれば、日本の企業の5年生存率は80.7%とされています(Ⅱ−198頁参照)。
一方、スタートアップの5年生存率はこれを大きく下回り、15%ともいわれています。
こうしたデータからもわかるように、スタートアップは短期間で急成長を遂げることが期待される一方、その期待に応えられなかった場合には倒産や解散のリスクが高まります。
実際、帝国データバンクの統計によれば、業歴10年未満の『新興企業』の倒産件数は2024年中で3080件にのぼり、倒産件数全体に占める割合は31.1%となります(帝国データバンク「全国企業倒産統計2024年12月版」(2025年)8頁)。
あらゆる会社にも言える潜在的なリスクですが、スタートアップの場合には統計的にもその懸念が他の会社よりも大きいということです。
とはいえ一定のまとまった資金調達を経て、サービスも展開しているような場合にまで倒産の可能性が高いと言えるようなものではないでしょう。
結局はスタートアップだからという一般論ではなく、「そうなる可能性」の具体性次第であり個別事情によって判断されます。
したがって、離婚時にスタートアップの株式を評価する際には、個別事情も踏まえてこうしたリスクを適切に織り込むことが求められます。
単に過去の資金調達時のバリュエーションを基準にするのではなく、会社の現在の状況、見込まれる将来の状況や経営リスクを勘案した合理的な評価が必要です。
3.VCからの資金調達と評価
VC(ベンチャーキャピタル)から出資を受けているスタートアップでは、資金調達時に行われるバリュエーション(企業価値評価)が、離婚における株式評価に影響を与えることがあります。
VCが出資する際にこの過程を経て算出された出資価額をもとに、配偶者側から「この評価額こそが正当な株価である」と主張されるケースがあります。VCは、事業の将来性や収益予測に基づき、専門的なデューデリジェンス(DD)を実施して株価を算定しているという主張です。
しかし、VC出資時のバリュエーションは、必ずしも企業の客観的な現時点の価値を反映しているわけではなく、むしろ将来の成長を期待した結果のものです。
スタートアップでは資金調達後に「ダウンラウンド」(企業価値の引き下げを伴う追加資金調達)が行われることもあり、最初のバリュエーションがその後の実態にそぐわなくなることも珍しくありません。ダウンラウンドの発生比率について1割前後とする統計もあります(株式会社産業革新投資機構(官民ファンド)『スタートアップ・ファイナンス市場レビュー(2024H1)』(2024年)12頁)。
このような事情から、離婚時の株式評価にVCからの資金調達額をそのまま適用することには慎重な検討が必要です。
(補足:取引事例法について)
なお、株式評価方法の一つとして「取引事例法」というものがあります。
この方法は、過去に実際に行われた取引の価格をもとに株価を算出する手法です。
一見、公平で合理的な評価方法に思えますが、株式評価の実務で取引評価法がベースになることはあまりありません。
その理由として、過去の取引価格の合理性の有無を判断することが難しいことや、資金調達やセカンダリー取引における一株あたりの金額の決定は個別の取引事情によって影響を受けるものであり、取引に類似性がないことが挙げられます。

4.評価の時間軸と将来価値の評価
スタートアップの事業価値は、事業の成長段階や市場環境によって大きく変動します。
このため、離婚のタイミングは財産分与における評価額に大きな影響を与えます。
特に、資金調達直後やIPO直前といった局面では、外部の投資家によって高額なバリュエーションが付けられ、事業価値が急上昇するケースが少なくありません。
このような局面で離婚を迎えた場合、配偶者からその高額なバリュエーションをもとにした財産分与の主張を受けるリスクがあります。
また一方で、離婚時点では赤字であっても、将来の成長が見込まれるスタートアップは、その潜在的な利益をどのように評価に反映させるかが重要な争点となります。
しかし、その将来価値を正確に評価することは難しく、過大評価も過小評価も公平性を損なう原因となり得ます。この点が、離婚におけるスタートアップ株式の評価を一層複雑にする要因です。
たとえば、現時点では収益が出ていない企業でも、将来のIPOやM&Aによって大きなリターンを得る可能性がある一方、事業の失敗により価値が大幅に下落するリスクもあります。そのため、評価時点での単純な数字だけではなく、将来の不確実性も考慮に入れた評価が求められます。
将来価値を巡る争点を解消するために、柔軟な解決策を双方が検討できることが望ましいです。例えば、事業の成長や利益の発生に応じて、配偶者への支払いを段階的に行う合意などが考えられます。このような取り決めにより、事業価値の変動を前提とした合理的な財産分与が可能となります。
具体的には、将来のキャッシュフローや利益の一定割合を配偶者に支払う方法、事業が一定の成果を上げた場合にのみ追加支払いを行う方法などが考えられます。
5.優先株と普通株の評価
ファイナンスラウンドの進んだスタートアップにおける株式は、通常、普通株式と優先株式に区分されます。
優先株式は、VCなどの投資家に対して発行される株式であり、M&A時の優先的な分配権といった特権が付与されていることが特徴です。一方、創業者や経営陣が保有する株式は普通株式であり、優先株主との関係では劣後する立場にあります。
例えば、現状の日本のスタートアップファイナンス実務では、会社が清算される場合やM&Aで譲渡される場合、優先株主はまず投資額を回収した上でその残りについて更に株式比率に応じた分配を得られる設計になっていることが多いです。そのため、同じ1株であっても、優先株式と普通株式では評価額が異なってきます。
スタートアップの普通株式は、企業の成長段階によって評価額が大きく変動します。
特に、赤字が続く創業初期や、エグジットの見込みが立っていない段階では、優先株式に比べて評価額が低くなるのが一般的です。1円といった評価しかつかないケースも珍しくありません。
優先株と普通株の評価の違いを財産分与実務でどのように取り上げるかについては、会社がIPOする見込みとM&Aする見込み如何が重要な要素となってきます。IPOならそのタイミングで優先株は普通株に切り替わるため、こうした優先劣後の影響は考慮されないからです。
なお、M&AとIPOの割合はこれまで6:4~7:3程度で推移してきましたが、M&Aの割合は増加傾向にあります(フォースタートアップス株式会社「【2024年 年間】国内スタートアップ投資動向レポート」(2025年))。
6.希釈化ベースでの株式評価
スタートアップでは、役職員向けインセンティブプランのストック・オプションや資金調達の手法として用いられるJ -KISS(日本版 Keep It Simple Security)、SAFE(Simple Agreement for Future Equity)などのいわゆるコンバーティブルエクイティが活用されていることが多くあります。これらはいわゆる潜在株式です。
潜在株式とは、現時点では発行されていないものの、将来的に株式に転換される可能性のある権利のことを指します。
株式評価において、こうした潜在株式を考慮した「完全希釈化ベース」で評価を行うか否かは重要な論点となります。基準となる株式数が多ければ、その分だけ一株あたりの株価は下がる(希釈化される)からです。
完全希釈化ベースとは、評価時点における全ての潜在株式(発行会社が保有するものを除く)が普通株式に転換されたものと仮定して、株式数を基準に評価を行う手法です。
ファイナンス実務では通常、完全希釈化ベースでの評価が採用されますが、離婚財産分与実務も同様でしょうか。
この点、特に、潜在株式の行使見込みが低い場合や、権利実現に厳しい条件が付されている場合には、完全希釈化ベースによる評価は不適切とされる可能性があります。
権利実現の見込みがないことを立証できるような状況であればファイナンス実務においてもその分の潜在株式は基準株式数には算入されないと思われ、その点では同様です。
但し、特に財産分与実務においては、潜在株式を含む評価を行うか否かについて、実際の権利行使の可能性や事業計画をより個別事情に踏み込んで確認されるように思います。
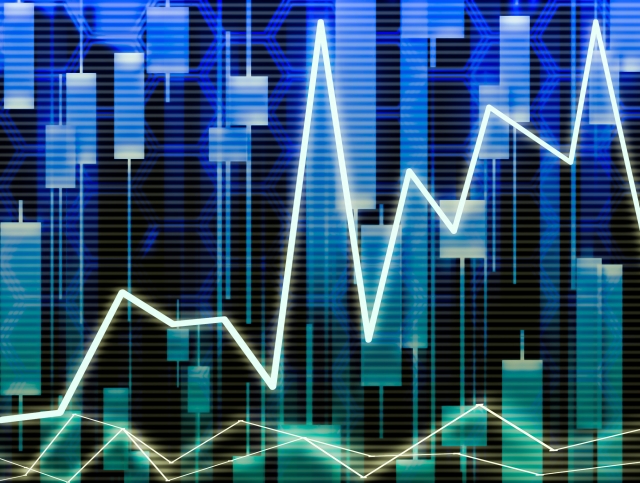
7.株式の評価における鑑定の有用性
スタートアップ企業の株式を巡る離婚時の財産分与では、事業価値を正確に評価することが重要な課題となります。そのため、場合によっては専門的な知見を有する第三者による鑑定が必要になることがあります。
理論上は、裁判手続きにおいて株式の鑑定を依頼することが可能です。しかし、実務において実際に鑑定が実施されるケースは非常に限られています。その理由は主に以下の二つです。
① 鑑定費用の問題
株式の評価鑑定には高額な費用がかかります。
1件あたり100万円単位の費用が発生するため、当事者双方にとって負担が大きいことが理由の一つです。財産分与における鑑定の必要性は認識されつつも、費用対効果の観点から見送られることが多いのが現状です。
② 裁判所の対応方針の問題
もう一つの理由は、裁判所の対応や経験の蓄積不足です。
家庭裁判所での実務では費用の問題に関わらず手続きの進行に消極的な対応をされることが多くあります。
鑑定を検討する際には、その費用負担や裁判手続きの進行への影響を十分考慮する必要があります。費用負担が重いにもかかわらず、鑑定結果が最終的な判断に必ず反映されるとは限らない点を踏まえ、裁判所や相手方と協議した上で慎重に対応することが重要です。
8.税制適格ストック・オプションの評価に関する問題
(1)前提(権利行使価額の設定方法について)
2023年、国税庁は通達を改正し、税制適格ストック・オプション(以下「税制適格SO」といいます。)の権利行使価額の設定方法を明確化しました。
税制適格SOとして扱われるためには、その権利行使価額を発行時点の時価以上にしないといけないのですが、明確な基準が示されていなかったため、必要以上に権利行使価額を高めに設定するケースが多かったのです。
しかし、この通達改正によって基準が示され、そのような対応が不要となりました。
具体的には、取引相場のない株式(上場株式と気配相場等のある株式以外の株式)については、一定の条件のもと、「財産評価基本通達」に従って権利行使価額を設定することにより、税制適格要件を満たすものとされました。
その結果、中小企業においては純資産価額方式を用いて権利行使価額を設定することが可能になり、純資産がマイナス(債務超過)の場合には備忘価格として1円と設定することも可能になりました。
また、種類株式を発行している場合は、その内容を勘案して個別に普通株式の価額を算定することになるため、その分評価額が下がる場合もあります。
(2)財産評価基本通達による評価を巡る主張
通達改正を受けて、「財産評価基本通達に基づいて評価した場合、税制適格SOは無価値である。」と主張される場合があります。
ただし、このような主張が採用される可能性は低いように思われます。
その理由は、財産評価基本通達が適用される範囲や趣旨が限られているためです。
(3)財産評価基本通達が採用されにくい理由
財産評価基本通達の適用は、本来、相続税や贈与税などの課税の場面に限定されるものであり、財産分与における株式評価にそのまま拡張・類推適用することは想定されていません。
この通達の趣旨は、税務上の公平性を確保するために統一的な評価基準を設けることにあります。一方、財産分与における株式評価は、実質的な資産価値をもとに離婚当事者間の公平性を図るものであり、単純に税務上の評価方法をそのまま適用することは適切ではありません。
また、スタートアップ企業の場合、現時点での純資産額が低くても、将来の事業成長によって大きな価値を持つ可能性があります。そのため、純資産価格方式に基づく評価額だけでは、スタートアップの本質的な価値を正確に反映できないことがあります。

以上、スタートアップ(ベンチャー)創業者や、シリアルアントレプレナー(連続起業家)世帯の離婚における財産分与で問題となる、スタートアップの株式の評価方法について解説してきました。
スタートアップ(ベンチャー)創業者やシリアルアントレプレナー(連続起業家)の方をはじめ、その配偶者の方、さらには投資先に経営者の離婚リスクが考えられる投資元(ベンチャーキャピタル)の皆様は、初回のご相談は30分間無料※ですのでお早めに当事務所までご相談ください。
※ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。
