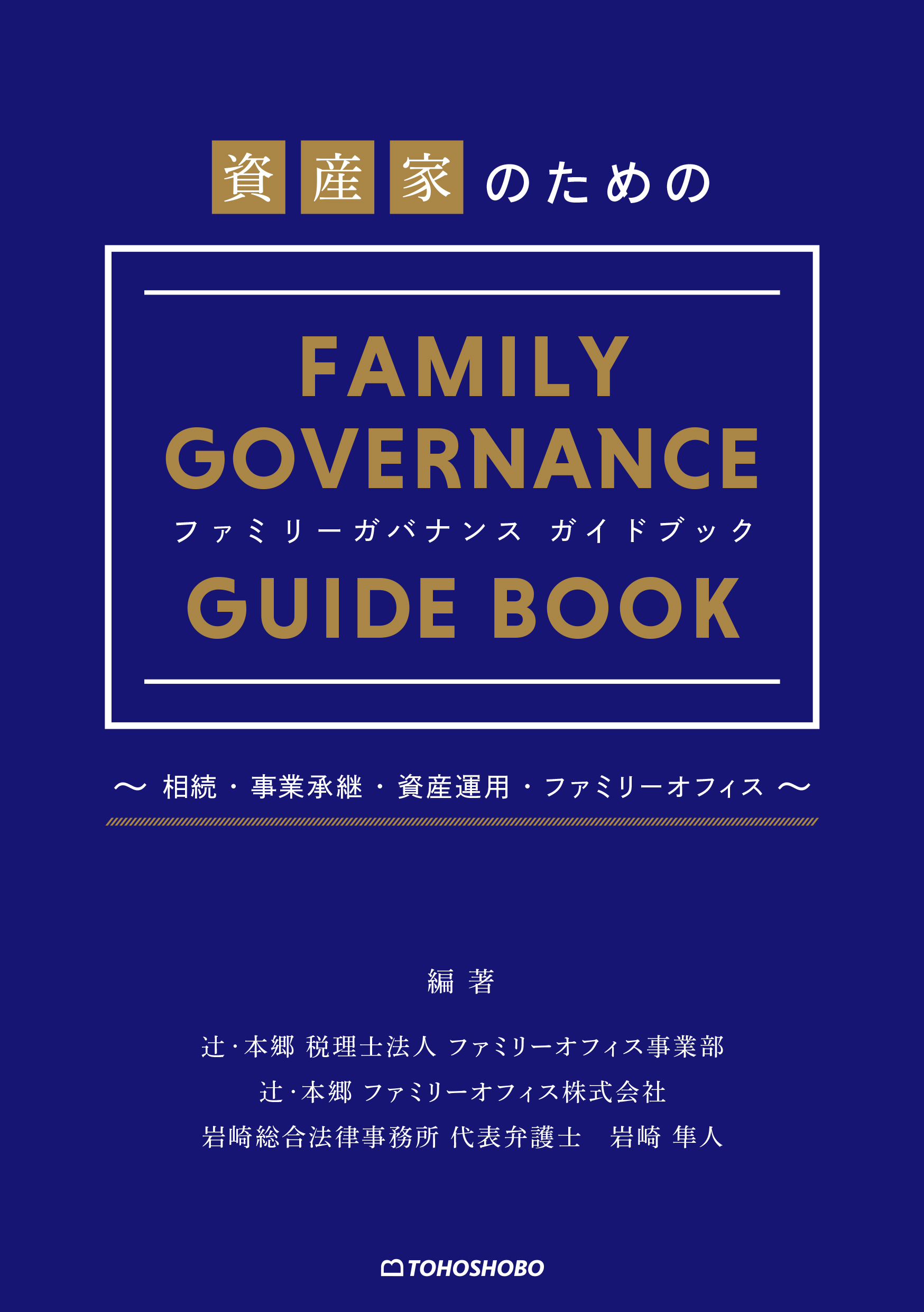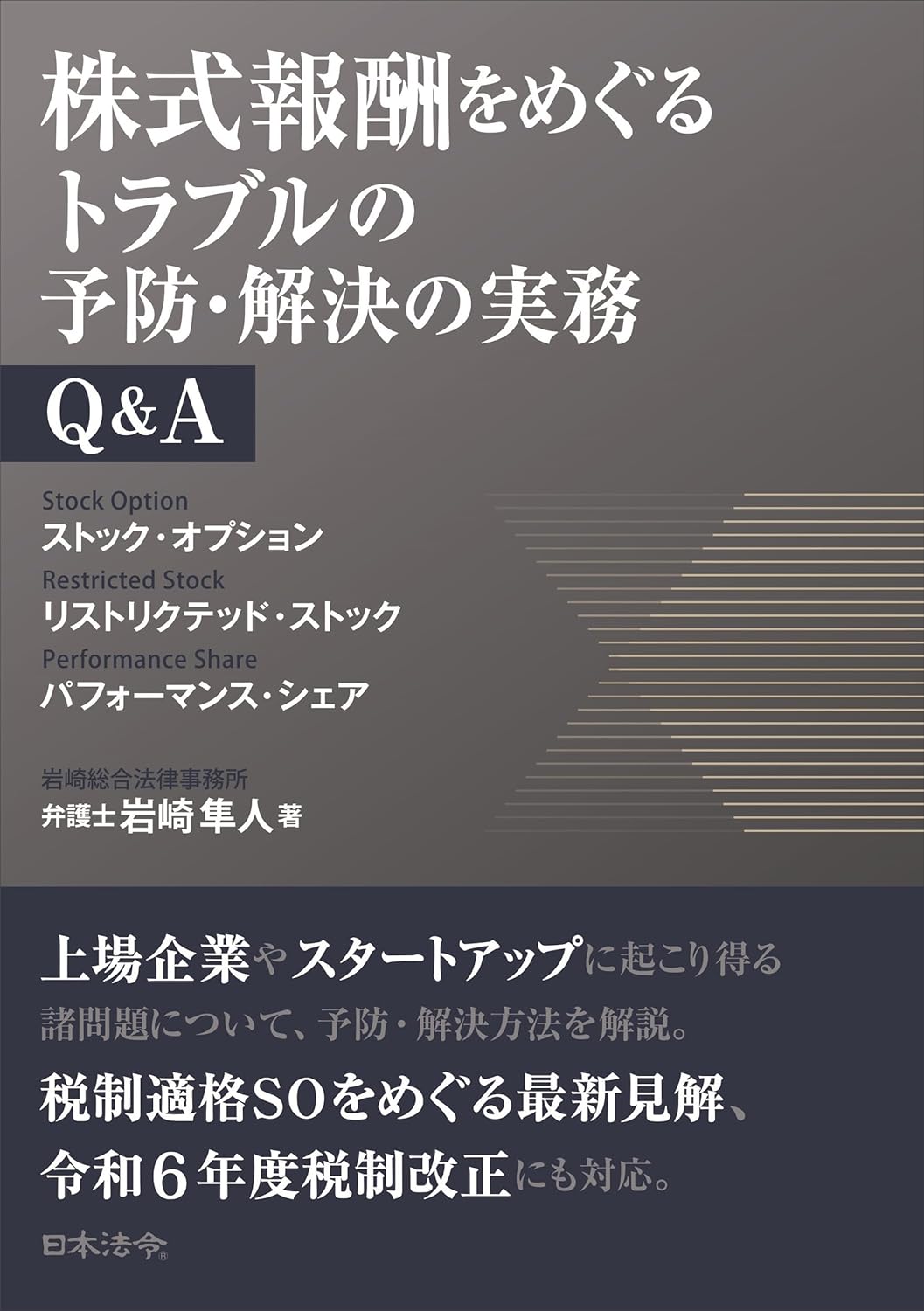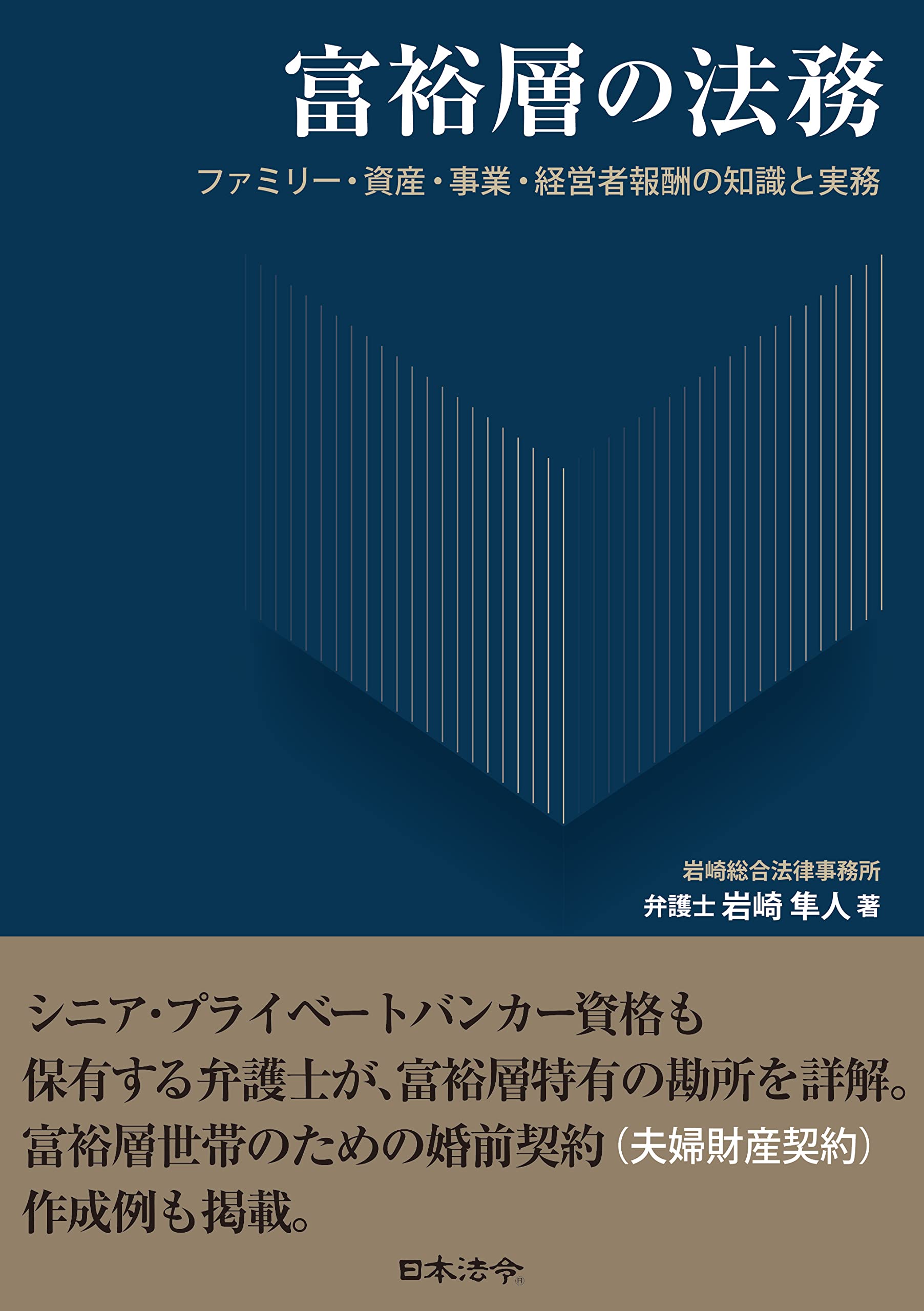Information > コラム
2024.7.17
外資系企業に勤務する世帯の離婚問題 ー8つの特徴とその影響ー
あなたやあなたの配偶者が、外資系企業(欧米の金融機関、コンサルティング会社、GAFAMをはじめとするクロスボーダーIT企業など)の役員や従業員の場合、離婚にあたっては通常の家庭とは異なる問題が起こるかもしれません。
それは主には以下の8つの理由からです。
① 国内企業に勤めている方よりも収入が多い場合がある
② 転職を繰り返す場合がある。転職の際にはサイニングボーナスを得ている場合がある
③ 収入には株式報酬(主にはRS(リストリクテッド・ストック)やRSU(リストリクテッド・ストック・ユニット))が含まれる場合がある
④ グローバル人材に育てるため、留学やボーディングスクールに通わせるなど教育費には高額な支出をしている場合がある
⑤ 外国からの収入や国外資産があるときには租税効果の計算が複雑な場合がある
⑥ 国外資産が日本には存在しない性質のものである場合がある
⑦ 為替の影響を受ける場合がある
⑧ 外国籍を保有している場合がある、二重国籍である場合がある
このコラムでは、そうした外資系企業に勤務する世帯の離婚トラブルに共通する問題点をいくつかご紹介します。

目次
- 1 勤め先が外資系企業であることの「財産分与」の特徴
- Q1 国外資産や外国通貨がある場合はどのような点に注意するべきでしょうか。
- Q2.会社から株式報酬(RS等)をもらっているようです。株式報酬とはなんですか。どういったことに注意すれば良いですか。
- Q3.非上場の外資系企業のエクイティの取り扱いはどうなりますか。
- Q4.その他の財産分与の特徴はありますか。
- Q5.財産分与の割合・方法はどうなるでしょうか。
【実例とコメント】実際の運用と乖離していることも
【実例とコメント】アメリカの他人の裁判記録が役に立つことも
- 2 勤め先が外資系企業であることの「婚姻費用」の特徴
- 3 外資系企業に関連するその他の離婚問題
1 勤め先が外資系企業であることの「財産分与」の特徴
Q1 国外資産や外国通貨がある場合はどのような点に注意するべきでしょうか。

外資系企業にお勤めの世帯は、国内のみならず国外にも不動産、預貯金、株式等の有価証券をお持ちの場合があります。
これらには、アメリカ特有の制度であるジョイント口座(joint account)やジョイントテナンシー(joint tenancy)といったように、名義そのものが夫婦共有の扱いとなっている財産や、夫婦以外の親族と共有となっている財産が含まれます。このことから、財産分与の対象性に問題が生じる場合もあります。
また、外国通貨をお持ちの場合や、国外資産を現地通貨により評価する場合に問題となるのが為替相場です。
財産分与の対象財産の基準時は原則として別居時ですが、評価時は離婚時(現実的には離婚時に直近の双方が合意した時点)とされています。
近時の急速な円安に見られるような為替相場の変動が発生すると、実際の分与額に大きな影響を及ぼすことがあります。
Q2 会社から株式報酬(RS等)をもらっているようです。株式報酬とはなんですか。どういったことに注意すれば良いですか。
外資系企業勤めの従業員・役員に対しては、現金で支払われる給与のほか、株式報酬が支払われるケースも多くあります。
特に欧州や米国企業ではよく見られます。
株式報酬とは、役員や従業員のインセンティブ報酬の一種として株式等を活用するものです。
新株予約権として付与するものをはじめ、一定の譲渡制限を付した株式や、その株式に変わる単位(ユニットやポイント)を付与するものとが含まれます。
ストック・オプション(SO)、事前交付型リストリクテッド・ストック(RS)、事後交付型リストリクテッド・ストック(RSU)、中長期の業績連動型のパフォーマンス・シェア(PS)などと呼ばれるものがその代表例です。
株式報酬は米国発の制度とされ、その後、欧州や日本も含め世界各地に広がりました。
欧米等の外資系企業では、役員のみならず広く従業員まで株式報酬付与の対象とされることがあります。
この場合、婚姻費用算定の際の収入額としてどのような金額を計上すべきか、財産分与の対象となるか、対象となるとしてどのような方法での分与となるか、財産分与に伴い発生する税金の取り扱い等については事例に応じて様々です。
株式報酬の金額は大きくなることが多く、離婚問題を解決するにあたっては重大論点となります。
当事務所は、様々な株式報酬の設計・課題解決を手掛けてまいりました。これらの知見は、夫婦間の財産の清算の場面である財産分与手続においても効果を発揮しています。株式報酬の財産分与について詳しくは、こちらのコラムをご確認ください。
コラム:ストックオプション・株式報酬の財産分与
弊事務所では、富裕層法務サービス Legal Prime® を通じ、資産家、投資家、会社経営者などの資産・収入の多いお客様に対し多様なサポートを提供してまいりました。
これにより得られた知見の一部を書籍化し発売中です。ご興味をお持ちいただけましたら、書影をクリックして詳細をご確認ください。
Q3 勤め先は非上場会社です。エクイティ報酬をもらっていますが、どのように取り扱われますか。非上場の外資系企業のエクイティの取り扱いはどうなりますか。
前記のとおり、外資系企業では、RSUやSOといった伝統的なエクイティ報酬が支給されることが多々あります。
これらは本社が所在する国の上場企業を発行会社として実施されることが多く、そのため最終的に得られる株式には流動性があるのが一般的です。
一方で、外資系企業には非上場の会社も存在します。
非上場の外資系企業でも、優秀な人材の採用やリテンション(引き留め)のためにエクイティ報酬を導入するケースがあります。
中には「コーオウンド」と呼ばれる経営形態を採用している企業もあります。コーオウンドとは、役職員が会社の株式の多くを所有し合うタイプの会社を指します。
しかし、非上場であるがゆえに株式の流動性が低いものです。ただ付与するだけでは採用にもリテンションにも活用できません。
そこで、非上場の外資系企業がエクイティ報酬を活用する時には、その経済的価値・保有していることのメリットを生み出すために様々な仕組みが設計されています。
こうした仕組みは、財産分与などの離婚事件において問題となることも少なくありません。
例えば、非上場企業のエクイティ報酬には以下のような特徴が見られます。
1.特殊な配当設計
積極的な配当の仕組みが導入されており、会社にもよりますが相当にまとまった金額となる場合もあります。
2.処分制限
株式を売却・処分する際、会社や同僚への売却条件が厳しく設計されている場合があります。
社内規程には、処分には原則として会社の承諾が必要と記されていることが多いです。
仮に承諾なしで処分可能な場合が定められているとしても、その場合の買い取り価格は通常のバリュエーション(評価額)よりも低く設定されます。
これらは非公開企業としての秩序を保つための措置です。
こうした状況を把握するには、関連資料を精査する必要がありますが、非公開企業のため詳細な情報が得られない場合もあります。
その際には、裁判例の調査や発行会社への照会などを通じて事実確認を行うことが求められます。
さらに、株式の売買が会社での昇進や評価に影響を及ぼす可能性が否定できない点も問題です。
こうした背景を踏まえると、売買の実行を前提に財産分与を進めるべきか否かは、慎重に検討する必要があります。
実例とコメント:実際の運用と乖離していることも
社内規程に記載された内容や付与時の契約の内容が実際の運用と一致しないことも珍しくありません。
例えば、原則的に会社の承諾が必要とされていても、実務では会社が承諾を行う運用がなされることがあります。
また、計算式も控えめな内容ではなく、通常のバリュエーションに基づく価格が事実上採用される場合もあります。
Q4 その他の財産分与の特徴はありますか。
外資系企業にお勤めの役職員の方々には、現金の保有を必要最低限にとどめ、余剰資金を積極的に投資に回している方が多い印象があります。
これらの投資先は、有価証券だけでなく、不動産も含まれます。また、国内外を問わず幅広く選定される傾向が見られます。
具体的には、有価証券については国外のものが多く、口座も海外の金融機関を利用しているケースが目立ちます。
不動産に関しては、国内の場合、主に都心一等地の高級不動産への投資が多く、一棟ビルの購入に積極的な方は少ない印象があります。一方、国外不動産に対しても抵抗が少なく、条件が良ければ積極的に投資する方が多い印象があります。
また、こうした方々は、単に資産を運用するだけでなく、ストレスを感じることなく効率的に運用を行っているケースが多く見られます。そのため、投資において高いスキルを持つ方が多いという印象を受けます。
財産分与においては、これらの多様な資産を適切に評価し、公平に分配することが求められます。
特に海外資産の場合、その所在や価値の確認が重要であり、慎重な検討が必要です。
Q5 財産分与の割合・方法はどうなるでしょうか。

世帯の資産が多い場合、夫婦で財産を半々に分け合う「2分の1ルール」も、単純に適用されることはありません。資産の範囲、評価の方法、分与の方法等に複雑な論点が存在します。
外資系企業勤めの世帯においては一定の金額の蓄財があるケースが多いです。
その資産の内訳としても、前記の株式報酬や、外国通貨、暗号資産、デリバティブ、国内外の不動産など、多数の種類に及ぶことがあります。
▼財産分与の割合に関する問題については、こちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。
「財産分与の割合は”常に50%”ではない 2分の1ルールが修正されるケースとは(5%、30%、40%とした裁判実例付)」
実例とコメント:アメリカの他人の裁判記録が役に立つことも
アメリカでは判決文や訴訟記録がオンラインデータベースで閲覧可能です。
離婚のようなプライバシー性の高い案件には制限が設けられることが一般的ですが、それ以外の多くの記録は誰でも参照できます。
この仕組みは、日本で離婚を検討している方にも影響を与える可能性があります。
特に外資系企業に勤務する方にとって、株式報酬や海外資産、多国籍にまたがる問題など、複雑な要素を含むケースでは、重要な参考資料となり得ます。
たとえば、株式報酬の評価や企業の財務情報は、離婚訴訟でしばしば争点となります。
しかし、特に発行会社が非公開企業の場合、そうした情報を入手することは困難です。
この点で、同じ企業を巡るアメリカの裁判記録において株式評価が取り上げられていれば、それを参考に自分のケースに適した戦略を検討することが可能です。
2 勤め先が外資系企業であることの「婚姻費用」の特徴
Q6 多くのボーナスはどのように扱われますか
通常、婚姻費用や養育費の算定にあたって収入額を認定する際には、源泉徴収票を用います。
そこに記載される収入額に賞与の額が含まれていますので、通常、賞与の額は、婚姻費用・養育費の算定の基礎となる収入額に反映されています。
ところが、外資系企業の場合、業績に連動するインセンティブ・ボーナス(incentive bonus)や、入社時に支払われる一時金としてのサイニング・ボーナス(signing bonus)、サインオン・ボーナス(sign-on bonus)などの名目で、定期的に支払われる給与とは別途のボーナスが支払われることがあります。
原則としては、このようなボーナスも婚姻費用や養育費算定の基礎となる収入に全額算入されるべきでしょう。
しかし、ボーナスの支払額が定期的に支払われる給与に比べて著しく大きく、また恒常的には支払われておらずごく一時期にのみ支払われたものであるなどといった特段の事情がある場合には、(全額ではなく)過去数年分の平均額を取るなどしてこれを修正することが妥当な事案もあるものと考えられます。
Q7 RSU、SOその他のエクイティ報酬は婚姻費用でどのように考慮されますか。
RSUやSO、その他のエクイティ報酬に共通する特徴として、額面上の所得が高くても、それが必ずしも実際のキャッシュフロー(現金収入)を反映していない場合がある点が挙げられます。これは、それぞれのエクイティ報酬の設計内容に大きく依存します。
例えば、無償ストック・オプションの場合、権利が実現する前、つまり金銭化が可能になる以前の段階で所得として認識されることがあります。
また、役職員に対して金銭債権を付与し、それをもとに時価で株式等のエクイティを取得させる仕組みもあります(この場合、付与された金銭債権はエクイティ取得のためだけに存在し、他の用途には使えないものです)。
これらは、実質的にはキャッシュフローを伴わない報酬です。
そしてこうした仕組みは特定の年度に限らず、毎年繰り返し行われるケースもあります。
婚姻費用の算定は、生活費のために計算されるものです。
そのため、額面上の所得ではなく、実際のキャッシュフローに着目する必要があります。
この観点から、エクイティ報酬がもたらす額面上の「所得」と実際の現金収入の乖離の有無や程度は重要な論点となります。
もちろん、富裕層世帯などの高額所得者世帯においては、標準的な算定方式が当てはまることはほとんどありません。
このため、所得がそのまま計算式に代入されて婚姻費用額が導かれることはありません。
とはいえ、実際の負担額としてあるべき金額を導く際には、自由に使えるお金が毎年どの程度発生するかは重要な要素となります。
このため、富裕層世帯のような高額所得者世帯においてもこの論点はやはり重要なのです。
Q8 所得の変動が激しいですが、これはどのように考慮されますか。
年々所得は上昇していく傾向があります。
これは金銭による報酬だけでなく、エクイティ報酬の付与なども含まれます。
しかし、上位の役職者ほど業績連動型の報酬体系の影響を受けるため、市場環境や会社の業績が悪化した際には、大幅に所得が下がることも珍しくありません。
また、雇用保護が厚い日本の労働文化とは異なり、米国企業では突然解雇されることがある点も特徴的です。
母体が米国企業でも、勤務先が日本国内であれば労働基準法により強力な雇用保護がなされるのですが、実際には退職勧奨や事実上の解雇が比較的自由に行われている印象を受けます。
これは、言い渡された従業員が会社に居続けることが難しいカルチャーや、退職・解雇に応じるよう設計されたインセンティブの存在によるものと考えられます。
このような背景から、突然解雇され、それまでの所得が維持できなくなるケースも少なくありません。
一方で、キャリアアップを目的とした自発的な転職が行われることも一般的です。その場合、通常はより好条件を提示されることが多いと考えられます。
さらに、退職時にはインセンティブとしてまとまった手当てが支給される場合があります。
しかし、その一方で、保有しているエクイティは消滅することもあります。
このように、特に外資系企業にお勤めの方にとっては、所得が大きく変動する状況は珍しくありません。
婚姻費用や財産分与を考慮する際には、こうした所得の変動を適切に評価することが重要です。
短期的な所得変動ではなく、総合的な視点で安定的な評価を行う必要があります。
Q9 教育費・留学費用が超高額なのですが、この負担はどうなるのでしょうか。

国際的に活躍される外資系企業勤めの世帯の方は、お子さんに国際的な素養を身につけてもらうため、海外留学や、ボーディングスクール(寄宿舎学校)、インターナショナルスクールなどの国際的な教育機関に通わせるケースも相当数あるものと承知しています。
また、そうでないとしても、受験準備のための塾や予備校、お子さんの心身の健康と素養を高め将来の可能性を広げるための各種習い事に通わせる家庭も多くあるようです。
こうした広い意味での教育費は、通常、標準算定方式に基づき算定される婚姻費用・養育費の金額中に既に包含されています。
しかし、留学費用(渡航費用や現地での生活費)、塾代、習い事代などは、標準算定方式により勘案された公立学校における教育費の金額を遥かに超えることから、一定の場合、特別費用として、婚姻費用・養育費とは別途の支払いを要すると考えられています。
具体的には、父母双方の同意により実施された教育である場合や、明確な同意に欠ける場合でも黙示的に同意している場合に、特別費用として認められるものとされています。さらにそのような同意が認められないケースにおいても、世帯収入・資産の額や父母の最終学歴、職業等の社会的地位等の事情を鑑みてそれに相応しい教育であれば認められるべきであるといった議論もあります。
▼超高額な教育費・留学費の問題については、こちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。
コラム:ボーディングスクールなど高額な養育費(教育費)の取り決め【合意書雛形あり】
Q10 高額所得者の婚姻費用・養育費はどのように算定されますか
夫婦が別居後は、配偶者や子どもの生活維持のための婚姻費用分担義務を負います。また、離婚後は、一方の親(非監護親)は、他方の子どもを養育している親(監護親)に対して、養育費の支払義務を負います。
一般の家庭では、裁判所が公開している標準算定方式に基づく算定表に当てはめることで簡易迅速に算定可能です。
しかし、算定表で計算できるのは年間の給与年収で2000万円までの世帯です。外資系企業勤務の世帯の場合、この上限を上回ることも多く、こうした高収入の世帯にそのまま使用することはできません。
裁判例や学説上、高額所得者の場合の婚姻費用の算定方法として、大きく分けて、次の3通りの方法が提唱されています。
これら3つの方法のうちいずれが採用されるかは、双方の公的書類上の収入額をはじめ、保有資産の状況、これまでの生活状況等、さまざまな事情を総合考慮して決定されます。
(1) 算定表の上限額とみなす方法
算定表の上限額をもって婚姻費用の額とする方法です。
この方法は極めてシンプルかつ明快です。例えば、夫が外資系企業勤めの高額所得者、妻が専業主婦で別居して幼い子1名を養育、という案件であれば、その婚姻費用は、算定表の上限額に従い常に月額40万円です。
この方法は、婚姻費用の算定方法としては、収入額が算定表の上限額(上述のとおり給与収入であれば2000万円)をわずかに上回るような事案であれば妥当性を有するものの、これを大きく上回る収入の場合には妥当性に欠けると考えられています。その反面、養育費の算定にあたっては、収入額が上限額を大きく上回っていても、実務上は原則的にこの方法が妥当すると考えられています。
(2) 標準算定方式を応用する方法
総収入のうち公租公課、職業費及び特別経費を除く割合であるところの基礎収入割合が一般に所得が増えるほど低下していく関係にあることに着目して、標準算定方式を修正・応用する方法です。
算定表上限の収入額からの乖離に応じ、標準算定方式における「基礎収入割合」を低下させる方法や、基礎収入から控除する公租公課、職業費及び特別経費の額や割合を修正したり貯蓄率を控除したりする方法などが唱えられています。
標準算定方式を応用する方法なので、比較的簡易迅速に計算可能な点にメリットがあります。反面、控除すべき実額の主張立証に困難があるほか、算定表の上限額を遥かに超える収入(目安として1億円)がある世帯への適用は難しいと言われています。
(3) 標準算定方式から離れて裁量的に算定する方法
同居中の家計の状況、別居後の現在の生活費支出状況から、必要分を加え、浪費部分を除くなどして、裁判所が裁量的に相当な婚姻費用を算定する方法です。
収入額が1億円を超えていたり、通常の家庭と異なる態様で生活費分担が行われてきた高所得世帯など、標準算定方式の応用が難しい案件に採用されます。
▼その他婚姻費用に関する問題については、こちらでも詳しく解説していますので、ご参照ください。
「高額所得者と婚姻費用」
3 外資系企業に関連するその他の離婚問題
Q11 国籍が外国籍なのですが、日本のことだけを考えておけばいいでしょうか。
夫婦あるいは配偶者が外国籍や二重国籍である方の場合、別途の問題が生じます。
一つは、日本の法律で処理されるか(これを準拠法の問題と言います)。
もう一つは、日本の裁判所で判断されるか(これを国際裁判管轄の問題と言います)。
夫婦間の権利関係はその国や地域の文化・価値観を反映しており、
どこの国の準拠法、裁判所で扱われるかは極めて大きな差異を生じさせる場合があります。
例えば、
・ 有責配偶者であっても離婚請求できる
・ 離婚後であっても配偶者の生活を保障しなければならない
といったルールを米国のカリフォルニア州などは定めています。
特に後者の離婚後の生活保障は、アリモニー(Alimony)あるいは配偶者扶養と呼ばれるものですが、
支払い総額は莫大なものとなる可能性があります。
このように外国籍・二重国籍の方の場合には、準拠法や国際裁判管轄の違いをよく考えて行動しなければいけません。
Q12 色々な税金が生じていますが、離婚ではどのように扱われますか。
外資系企業勤めの世帯を含む高所得世帯においては、所得税をはじめとする重い税金の負担があります。
婚姻費用・養育費との関係では、通常、標準算定方式に基づき算定される婚姻費用・養育費の金額中に既に包含されています。しかし、上述した高額所得者の算定方法においては、公租公課の実額が検討対象ですので、高額所得を得ている配偶者にいかなる税金がいくらかかっているかは重要な問題となり得ます。
財産分与との関係では、財産分与の基準時(多くは別居時)に負担し未払いである公租公課については適切に控除しなければ、公平を欠く場合があると考えられます。
また、不動産や有価証券(上述した株式報酬をはじめ、それ以外の株式、投資信託を含みます。)などについては、これらを売却して財産分与する場合はもちろん、これらを現物で分与する場合であっても、財産分与時点までに値上がりした利鞘が譲渡益として認識され、譲渡所得税の支払い義務が発生することにも注意が必要です。
▼参考
国税庁ホームページ「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」
▼離婚と税務の問題については、こちらでも詳しく解説していますので、ご参照ください。
「離婚と税金~離婚給付(財産分与、養育費、慰謝料)に関して思わぬ課税が生じないように~」
岩崎総合法律事務所が提供しているLegal Prime®では、外資系企業の役員、お勤めの方の離婚についてサポートを行なっておりますので、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
また、特設サイト「富裕層世帯の離婚」もございますので、ぜひご覧ください。