株式報酬・報酬事故・トラブル対応

上場企業・スタートアップのお客様に、ストック・オプション(SO)、リストリクテッド・ストック(RS)、パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)など、株式報酬制度の設計・発行に係るサポートをします。
特に改正が段階的に行われている税制適格ストック・オプションについては、現在の内容を踏まえて正しく設計するとともに、近い将来に予定されている改正を踏まえた提案・助言を行います。発行済の内容修正手続きも実施しています。
発行や運用に係る法務だけでなく、報酬委員や外部アドバイザーとしてサポートすることも可能です。
サポート実績
・ 株式会社ユーグレナ 【証券コード:2931】
・ AI CROSS株式会社 【証券コード:4476】
・ 株式会社市進ホールディングス 【証券コード:4645】
・ 株式会社No.1 【証券コード:3562】
・ 株式会社インティメート・マージャー 【証券コード:7072】
・ 株式会社メディネット 【証券コード:2370】
・ 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 【証券コード:7361】
・ 投資事業 / 金融事業会社 【上場企業】
・ 人材情報提供サービス会社 【上場企業】
・ 精神的健康課題解決サービス会社 【上場企業】
・ 医療機器開発会社【未上場企業】
・ 清掃警備会社【未上場企業】
ほか多数
※ 順不同。社名を個別標記しているものは予めご承諾をいただいております。
書籍紹介
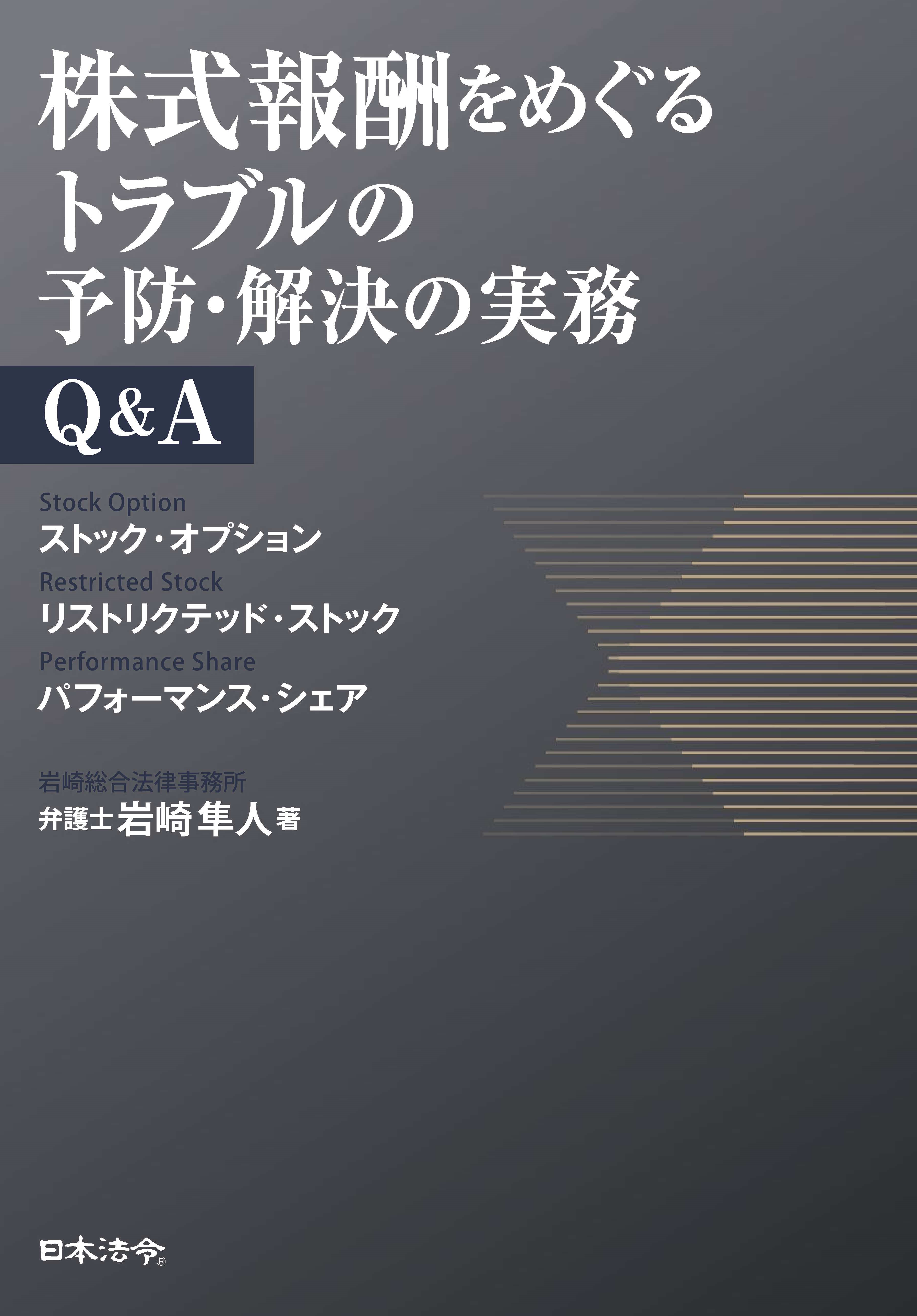
『株式報酬をめぐるトラブルの予防・解決の実務Q&A ――ストック・オプション リストリクテッド・ストック パフォーマンス・シェア』
著者 岩崎 隼人
出版社 日本法令
定価 3,520円(税込)
発行日 2024年5月19日
発行形態 単行本・256ページ
ISBN 9784539730133
Amazonほか各オンラインストア、出版社直販サイト、全国の書店にて
関連記事
・上場企業向けの新たな株式報酬制度「SSP」の法律監修を実施:株式会社ユーグレナで導入されました
・ストックオプションを割当先から没収するためには
・狙い撃ち的なストックオプション没収の問題
・「取締役会が適当と認めた場合」を取得事由とすることの実効性
・逆インセンティブの問題
・べスティング条項の注意点
・株式報酬とインサイダーの問題
・受給者の納税資金の問題
・報酬戦略における開示戦略
・報酬類型選択の視点
「任意の報酬委員」や、「報酬アドバイザー」活用のススメ
02. 報酬制度の設計・運用のための報酬アドバイザー
01. 任意の報酬委員会の有用性
Q: コーポレートガバナンス・コード等の要請を踏まえ、当社の報酬制度設計や運用について任意の報酬委員会を設けたいと思います。改めて任意の報酬委員会の意義とはどのようなものでしょうか。
A: 報酬制度設計や運用の透明性を高めることで、投資家からの評価が向上します。役員に対する適切なインセンティブ付けをとおして企業価値の向上に貢献します。こうした報酬ガバナンスの構築に重要な役割を担うものが任意の報酬委員会です。
任意の報酬委員会とは
「任意の報酬委員会」とは、法定機関ではないものの、取締役や経営陣に関する報酬制度の設計・運用に第三者の意見を取り入れることで、報酬制度に透明性・客観性を持たせ、投資家からの評価向上や役員に適切なインセンティブを与えることを目的とする委員会です。
任意の報酬委員会を設けることのメリット
1. 報酬設計の重要性
役員の報酬は、会社の経営において重要な役割を担います。
意思決定等会社において重要な役割を担う役員が、どのようにリスクテイクし、どのように積極的に活動するかについて、報酬の設計や内容が重大な影響を与えるからです。
そしてこうした重要な報酬の設計・運用に関する諮問委員会である任意の報酬委員会には、その設置と活用をとおして企業価値を向上させ、投資家との関係を良好なものとすることが期待できます。
2. 投資家との関係
投資家の投資指針において重視されるコーポレートガバナンス・コード等では、経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきであるとされ、そのために、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきとされます。
そして、こうした体制を設けるために、一定の場合には任意の報酬委員会を設け、委員会の適切な関与・助言を得ることが求められています。
このように、任意の報酬委員会の設置、活用は、対投資家との関係において重要なことであり、投資家との関係性を良好なものとすることが期待できます。
コーポレートガバナンス・コード 原則4-2(取締役会の役割・責務(2))
経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである。コーポレートガバナンス・コード 補充原則4-2①
取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきである。その際、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。コーポレートガバナンス・コード 原則4-10(任意の仕組みの活用)
上場会社は、会社法が定める会社の機関設計のうち会社の特性に応じて最も適切な形態を採用するに当たり、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統治機能の更なる充実を図るべきである。コーポレートガバナンス・コード 補充原則4-10①
上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきである。 特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべきである。対話ガイドライン 3-5(経営陣の報酬決定)
経営陣の報酬制度を、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう設計し、適切に具体的な報酬額を決定するための客観性・透明性ある手続が確立されているか。こうした手続を実効的なものとするために、独立した報酬委員会が必要な権限を備え、活用されているか。また、報酬制度や具体的な報酬額の適切性が、分かりやすく説明されているか。東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)」
金融庁「投資家と企業の対話ガイドライン(改訂版)」
3. 企業価値向上
報酬制度が会社の経営戦略の点から、役員に適切なインセンティブとなるように設計されている場合には報酬制度の仕組みをとおして企業価値向上に貢献します。こうしたインセンティブ付けとして適切な内容を検討するために、代表取締役のみで検討するよりも、社外取締役等の意見も取り入れて検討する方が客観的な意見を取り入れることができる点で有益です。
4. リテンションに貢献
代表取締役の一存で個々の役員の報酬を決めると、状況によっては役員同士の関係性が悪化する場合もあり、リテンションの観点から望ましくない場合があります。こうした場合にも、任意の報酬委員会の意見を踏まえて個々の役員の報酬を検討することは有益です。
5. 支給後の事後調整を行いやすくする
新型コロナウイルスの蔓延、戦争、インフレの進行、異常な物価高や為替変動など激変する環境下において、株価や業績がこうした外部環境に連動して影響を受けることがあります。このようにして株価や業績に悪影響が生じ、役員が業績連動報酬を受給できない(行使できない)事態になることがあります。投資家の視点を尊重すればその結論で良いということになりますが、一方で役員が十分な努力を積み重ねていた場合には、役員の視点からすると必ずしも適切な結論とはならない場合もあります。
このように、インセンティブとしての機能をもたせるために、経営努力との関連性が希薄な外部環境の悪影響の要素を取り除いて業績評価を行うなどして、事後的に給付内容を調整するべき場合があります。そのとき恣意性を排除するため、報酬委員会が客観的・独立的に審議することで、投資家への説明責任に耐えるとともに、インセンティブ制度を健全なものとして機能させる役割を報酬委員会に期待することもできます。
6. 業績連動報酬の損金算入の要件を支える
役員に対する業績連動報酬を損金算入するための要件として、所定の日までに報酬委員会(その委員の過半数が当該法人の独立社外取締役であるものに限り、当該法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と特殊の関係のある者が委員となっているものを除きます。)の決定(当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成しているものに限ります。)その他適正な手続を経ていることが求められます。
任意の報酬委員会の構成メンバー
報酬委員会委員に必要な能力は、報酬に関する法務・会計・税務の知見など技術的な能力に加えて、外部・内部のビジネス環境を踏まえて最適な報酬構成を検討する能力です。典型的には弁護士や会計士などです。
現状の任意の報酬委員会の構成メンバーについて、役員以外の者をメンバーに加えている会社はわずか数パーセント程度であり、ほとんどが社外役員を含む役員で構成されています。社外取締役の在り方に関する実務指針の心得1でも、社外取締役の最も重要な役割は、経営の監督であり、その中核は、経営を担う経営陣(特に社長・CEO)に対する評価と、それに基づく指名・再任や報酬の決定を行うことであるとされています。このため現状は社外役員の中から報酬委員会のメンバーとなるに相応しい者を選抜する(あるいは報酬委員会のメンバーとなるに相応しい者を社外役員として登用する)ことを検討します。
アドバイザーの活用
役員陣のみでの対応が難しい場合には、任意の報酬委員会のアドバイザリーとして上記の能力を保有する専門家の助言、サポートを得ることも重要です。
02. 報酬制度の設計・運用のための報酬アドバイザー
Q: 当社は任意の報酬委員会を設けています。このたび報酬制度の見直しをしているのですが、どのような内容、水準の報酬としたらよいか、報酬構成をどのようにしたらよいかなど報酬委員会のメンバーでは必ずしも見当がつきません。このようなとき、外部のアドバイザーに頼ることはできるのでしょうか。
A: 外部のアドバイザーの助力を得ることは可能であり、そうするべきです。外部のアドバイザーは、報酬に関する法務・会計・税務の知見など技術的な能力を持ち、外部・内部のビジネス環境を踏まえて最適な報酬構成を検討できる能力を持つ者であることが望ましいです。
報酬設計の重要性
役員の報酬は、会社の経営において重要な役割を担っています。
意思決定等会社において重要な役割を担う役員が、どのようにリスクテイクし、どのように積極的に活動するかについて、報酬の設計や内容が重大な影響を与えるからです。
報酬設計の多様化
役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されることが通常ですが、このうち株式報酬は約50%超の上場企業で導入されています。導入されているスキームは1種類だけにとどまっているケースが大半ですが、昨今では多様な報酬制度設計を導入している会社も現れてきています。これは、自社の報酬戦略を遂行するための適切なインセンティブ制度を設計するためには、複数のスキームを用いるべき場合があるからです。
アドバイザーの有用性
こうした多様な報酬制度の設計のためには、法務・会計・税務等の技術的な能力が広く求められます。この点で、任意の報酬委員会メンバーなど役員陣のみで検討することが難しい場合もあります。
このような事情を踏まえて、最適な報酬制度構築のために必要となる能力(報酬に関する法務・会計・税務の知見など技術的な能力や、外部・内部のビジネス環境を踏まえて最適な報酬構成を検討する能力など)を有する者(典型的には弁護士、会計士や専門のコンサルなど)を報酬委員会のアドバイザーとして登用することは、米国の大手上場企業では当然のことになっており、国内でも増加傾向にあります。
アドバイザーのサポートによって、報酬委員会の議論・決定がより客観的で深くなり、報酬委員会の決定内容の質が向上し、これによって自社の状況や経営戦略に照らした最適なインセンティブ制度の設計・運用を実現することが期待されます。
特に現行の報酬制度を見直すときや、報酬類型を新たに設けるときなど、報酬委員会のメンバーのみで対応することに不安のある場合にはアドバイザーの登用を検討することが有益といえます。
お問い合わせ
麹町駅徒歩1分と交通至便の場所に位置する当事務所では、初回30分の無料相談を実施中。
受任後も365日いつでも気軽に相談でき、迅速に対応できる体制を用意しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。







