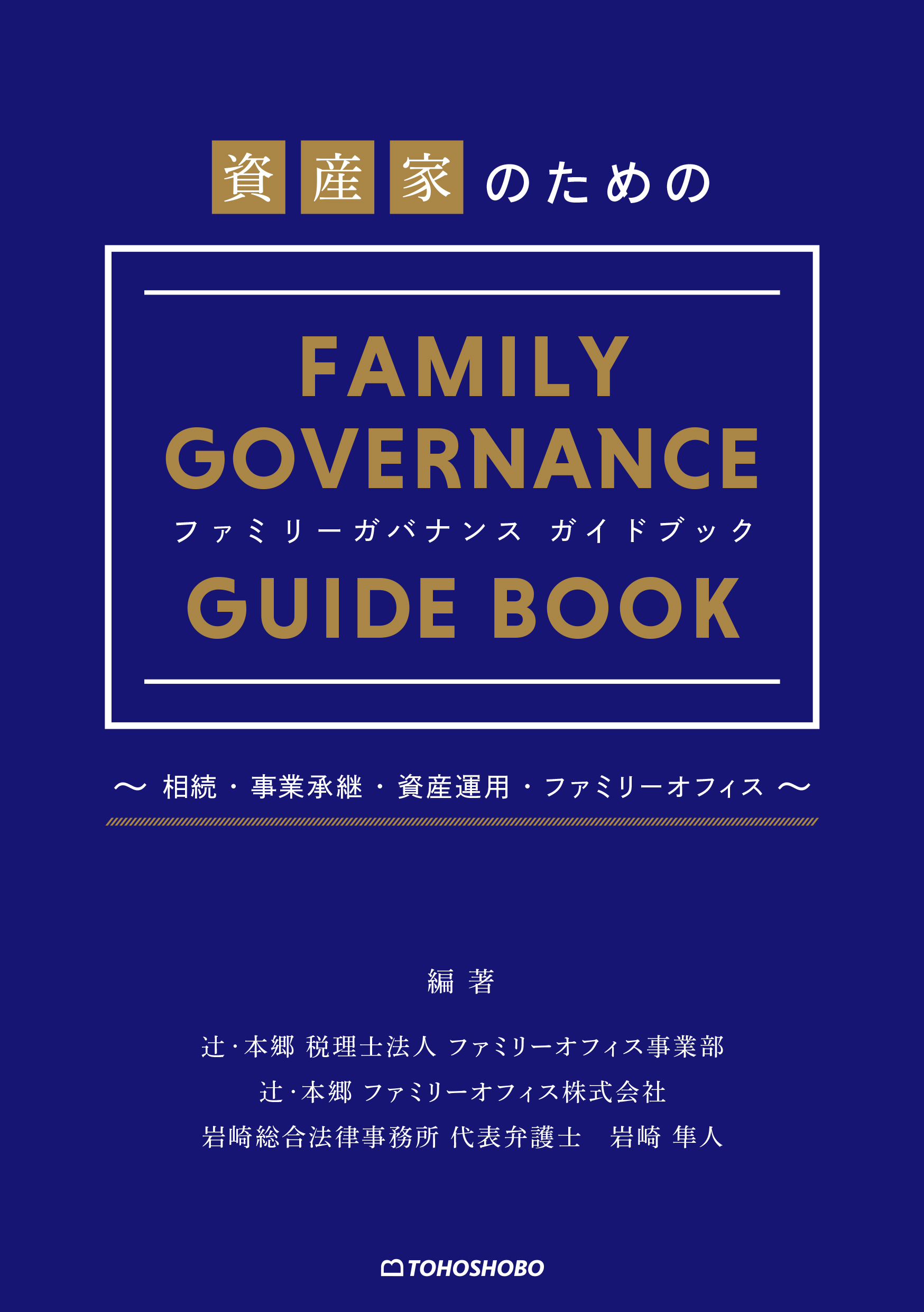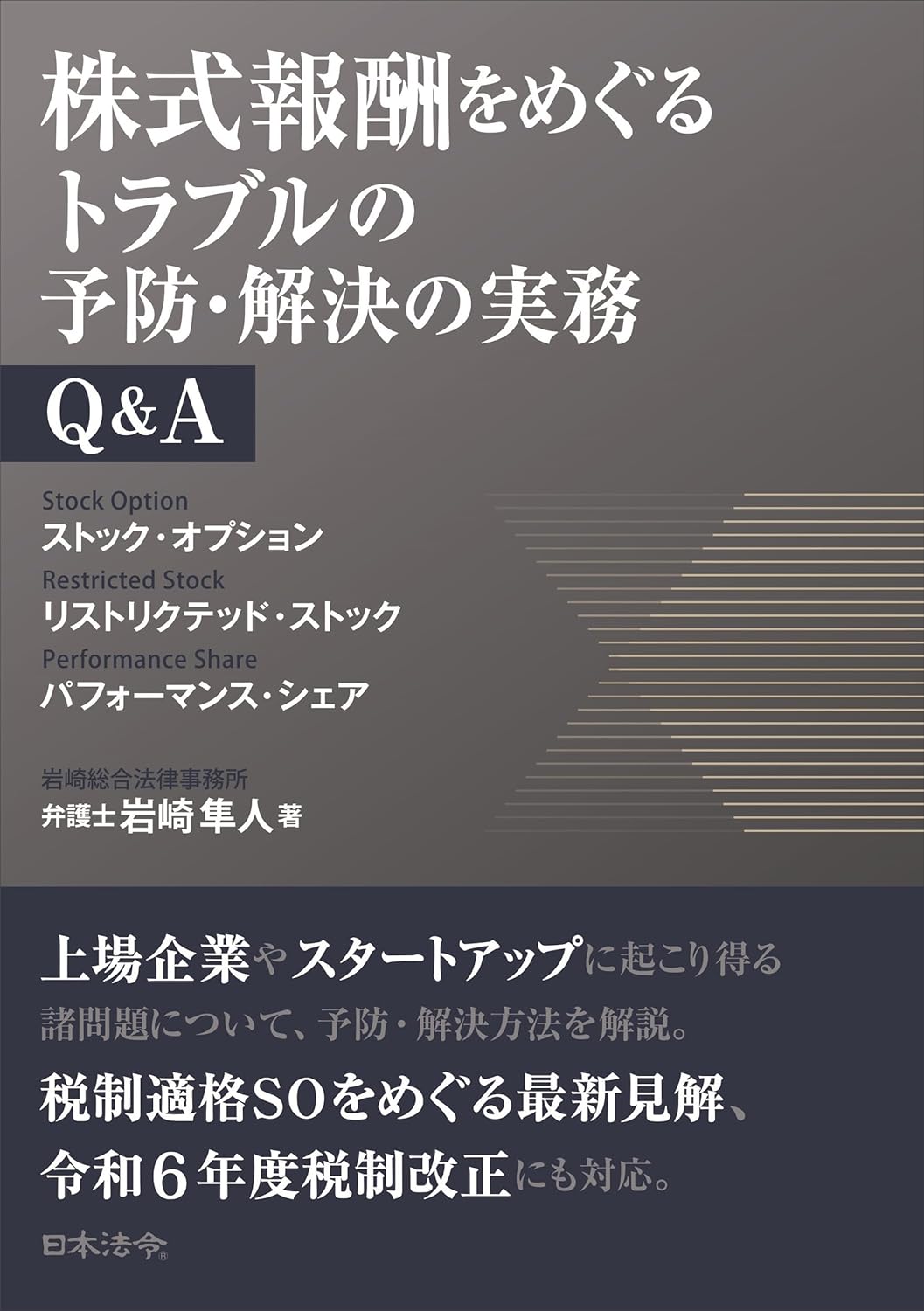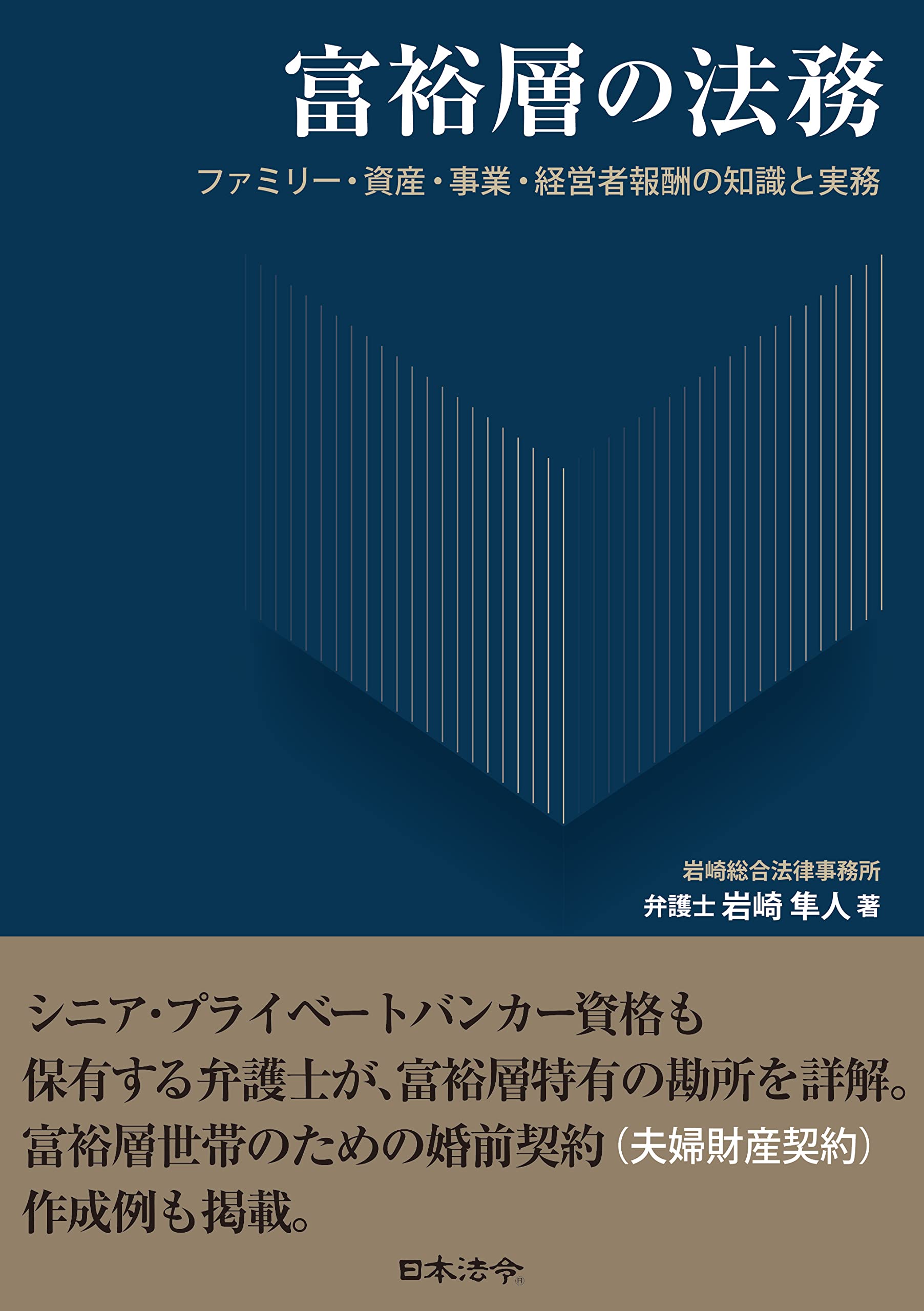Information > コラム
2025.3.28
ファンドオーナー・ファンド運営者(GP)の離婚
ファンドオーナーやファンド運営者(General Partner、GP)が離婚する場合、一般の財産分与とは異なり、ファンド持分や報酬の取り扱い、キャッシュフローの評価など、極めて複雑な問題が生じます。
特に、ファンド持分の譲渡制限や成功報酬、キャリードインタレスト等の報酬の扱いは争点になりやすく、慎重な対応が求められます。
そこで今回のコラムでは、ファンド関連の離婚問題について、財産分与の観点から詳しく解説します。
岩崎総合法律事務所では、資産家、経営者、投資家、高額所得者などの「富裕層」と呼ばれるお客様に対する法務サービス Legal Prime®を提供する中で、財産分与案件のノウハウ、経験が蓄積されてまいりました。
ファンドオーナー・ファンド運営者世帯の離婚についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
弊事務所では、富裕層法務サービス Legal Prime® を通じ、資産家、投資家、会社経営者などの資産・収入の多いお客様に対し多様なサポートを提供してまいりました。
これにより得られた知見の一部を書籍化し発売中です。ご興味をお持ちいただけましたら、書影をクリックして詳細をご確認ください。
目次
- ファンドの組成から清算までの一般的な流れを教えてください。
- ファンド投資家が離婚する場合、どのような点が問題となるのでしょうか。
- ファンド持分の処分は禁止されており、財産分与時点ではまだ存続期間が経過していません。払い戻しもできない状況ですが、この場合にもファンド持分は財産分与の対象となるのでしょうか。一定期間処分できないという制約を受けていますが、財産の評価にあたってこの事情は考慮されるのでしょうか。
- 別居開始後、ファンドに新規加入者が現れたことにより手数料収入がありました。この手数料収入は財産分与の対象になるのでしょうか。
- 分配金を受領し、別居を開始した後に分配金の返還(LPクローバック )が生じた場合、これらの返還分は財産分与の対象になるのでしょうか。
- ファンドの存続期間との関係で、最終的な利益は5年以上先まで確定しません。この場合どのように財産分与を行うのでしょうか。
- ファンド運営者が離婚する場合、どのような点が問題となるのでしょうか。
- 管理報酬を先払いで受領した関係で、別居開始後に報酬の精算(クーローバック)が発生しました。この場合、精算分は財産分与の対象になるのでしょうか。
- 成功報酬の対象となる期間の途中で別居が開始した場合、この成功報酬の一部が財産分与の対象となるのでしょうか。
- LPS契約に基づく報酬とは別に、投資先から報酬を受領しました。その結果、管理報酬が減額されることになりましたが、管理報酬の受領は別居前で、減額分の調整は別居後に行われました。この場合、減額分は財産分与にあたり考慮されるのでしょうか。
- LPS契約書をみると、「成功報酬」という規定がありません。この場合、管理報酬だけが支払われているということでしょうか。
- 離婚に備えてできる準備にはどのようなものがありますか?
- ファンド関係の契約書が手元にあるが、分量が多く、また見慣れない単語・表現が多く理解できません。離婚に向けてどのように準備を進めるべきでしょうか。
【ファンド投資家について】
【ファンド運営者について】
【ファンド投資家・ファンド運営者共通】

Q1 ファンドの組成から清算までの一般的な流れを教えてください。
一般的に以下の流れで組成・運営されます。
組成
ファンドの法的構造としては、LPS(投資事業有限責任組合)、LLP(有限責任事業組合)、民法上の組合など、投資目的に応じた形態が採用されます。
LPSは、GP(無限責任組合員)が主導し、投資家であるLP(有限責任組合員)からの出資を募ることで設立されます。
この段階では、ファンド契約の内容が詳細に決められ、投資方針や報酬の条件、持分の譲渡制限などが規定されます。
ファンドに対する出資の方式としては、一括で出資する方式、ファンド運営者から要請を受けた際に出資するキャピタル・コール方式があります。
投資期間
ファンドの投資期間中、ファンド運営者は投資戦略に基づき、複数の投資対象を選定して資金を投入します。
通常、投資先企業のバリュエーションやエグジット戦略を慎重に計画し、リターンの最大化を図ります。
運営・管理・分配
追加投資やエグジット(M&A・IPO)に向けた戦略を立てます。
ファンド運営者は管理報酬や成功報酬、キャリードインタレスト等の報酬を受領します。
ファンドオーナーには投資有価証券の売却状況等に応じてファンド財産が分配されます。
ファンド運営者の報酬等(管理報酬、成功報酬、キャリードインタレストなど)についてはQ7をご覧ください。
清算・分配
ファンドの存続期間が終了すると、投資有価証券等について売却・上場を通じて得た利益がLPへ分配されます。
一般的に、ファンド運営者も成功報酬やキャリードインタレストとして利益の一部を取得することになります。
【実例・コメント】
ファンドオーナー、ファンド運営者、いずれも様々な名目で報酬や分配金等を受領することになります。これらの支払いが一つの口座でまとめて管理されている場合もありますが、例えばファンド運営者として受領する管理報酬はA口座で管理し、成功報酬その他の支払いはB口座で管理するといったケースがあります。この場合、財産分与を求める側としては、把握している口座ですべてか(漏れがないか)留意する必要があります。一方、財産分与する側(ファンド運営者側)としては、これらの口座の中で特有財産(財産分与の対象とならない財産)と混在していないか(徹底した分離管理ができているか)よく確認する必要があります。
【ファンド投資家について】
Q2 ファンド投資家が離婚する場合、どのような点が問題となるのでしょうか。
財産分与の観点からおさえておくべきポイントは以下のとおりです。
・持分の評価と換価性
ファンドオーナーの持分は流動性が低く、また、譲渡制限が付けられている場合が多いため、評価方法が問題となります。
・分配金請求権の扱い
過去の分配金だけでなく、確定しているものの支配時期が到来していない分配金や将来の分配金が財産分与の対象となるかが争点になります。
特に、財産分与の基準時点(別居時点・離婚時点)が分配金の発生時期とどのように関係するかを検討する必要があります。
・新規投資家が参入した際に生じる手数料収入の扱い
ファンドに後から参加する投資家がいる場合、既存の投資家に対して手数料を支払うことがあります。
別居後に新規投資家がファンドに加入し、手数料収入が発生した場合には、財産分与の対象となる可能性があります。
手数料の詳細については、Q4をご覧ください。
Q3 ファンド持分の処分は禁止されており、財産分与時点ではまだ存続期間が経過していません。払い戻しもできない状況ですが、この場合にもファンド持分は財産分与の対象となるのでしょうか。一定期間処分できないという制約を受けていますが、財産の評価にあたってこの事情は考慮されるのでしょうか。
ファンドには「投資期間」と「存続期間」という言葉があります。
「投資期間」は、新規に投資を行う期間で、「出資拘束期間」ともいわれます。
「存続期間」は、まさにファンドが存続する期間であり、期間満了をもって清算されることになります。
ファンド持分や投資家としての地位については、以下のように基本的に譲渡できないように定められています 。
【条項例】
「組合員は、組合財産に対する持分を、裁判上及び裁判外の事由の如何を問わず、譲渡、質入れ、
担保権設定その他一切の処分をすることができない。」
「有限責任組合員は、無限責任組合員の書面による承諾がある場合を除き、その組合員たる地位に
ついて、裁判上及び裁判外の事由の如何を問わず、譲渡、質入れ、担保権設定その他一切処分をす
ることができない。」
そのため、存続期間中に財産分与として持分や地位を処分することはできません。
もっとも、存続期間中の譲渡が禁止されているからといって、直ちに財産分与の対象から除外される訳ではありません。
婚姻後の出資である場合には、持分や地位も財産分与の対象に含まれるのが原則となります。
ただし、評価にあたっては、存続期間の長さや清算時に見込まれる利益などが考慮されると考えられます。
Q4 別居開始後、ファンドに新規加入者が現れたことにより手数料収入がありました。この手数料収入は財産分与の対象になるのでしょうか。
後から参加する投資家は、いわば既存の投資家が負ったリスクの上に後追いで投資することになります。
そのため、後から参加する投資家について、以下のように一定の手数料を支払うよう定めておくことがあります。
【条項例】
「追加で出資を行う組合員は、それぞれ組合員が書面により指定する日(以下「追加クロージング
日」という。)までに、①各追加出資組合員の出資約束金額に追加クロージング日時点におけ
る既存出資比率を乗じて算出した額の出資金に、②当該追加クロージング日までに行われた各払込につき、当該払込時点の既存出資比率を当該追加出資を行う組合員の出資約束金額に乗じて算出した額に関し、当該払込のなされるべきであった日の翌日から追加クロージング日までの期間について年利○%(年365 日の日割り計算とする。)でそれぞれ算出された利息金の合計額を加算した合計額を、別途指定する口座に振り込みの方法により支払うものとする。」
この手数料は、ファンドやファンド運営者ではなく、ファンド投資家に支払われることが一般的です。
手数料の発生時期が別居前であった場合には、持分や分配金請求権とは別に財産分与の対象に含まれる可能性があります。
Q5 分配金を受領し、別居を開始した後に分配金の返還(LPクローバック )が生じた場合、これらの返還分は財産分与の対象になるのでしょうか。
以下のような場合に分配金を返還しなければならないと定められていることが一般的です。
ただし、返還については請求期限や金額に制限が設けられていることが多いです。
・表明保証違反などの義務違反により、ファンドから買主に対して損害賠償を行う場合
・価格調整条項に基づき、ファンドから買主に対して売買代金の一部を返還する場合
【LPクローバックに関する条項例】
「〇条に基づく支払債務について、組合財産をもって弁済することができないときは、無限責任組合員は組合員に対し、本組合から支払い済み分配金の一部について返還するよう求めることができる。ただし、当該返還請求は、分配金の支払いから〇年以内に限り行うことができ、かつ、各組合員に対する請求額は、支払い済みの分配金の累計額に○%を乗じた額を上限とする。」
通常は返還された金額を考慮、すなわち共有財産から控除した上で財産分与を行うことになると考えられます。
Q6 ファンドの存続期間との関係で、最終的な利益は5年以上先まで確定しません。この場合どのように財産分与を行うのでしょうか。
分配金は以下3つの場合に発生します。
①:投資証券等について売却などの処分が行われ、その対価として金銭を受領した場合
②:投資証券等に関して配当、利息などを受領した場合
③:①②以外の理由で組合財産に関して収益が発生しこれを受領した場合
分配金の支払い時期については、金額の大きなものについては都度払いとしたり、一定の期間(半期ごとや1年度ごと)で支払うよう定めるケースが多いです。以下条項例となります。
【条項例】
「無限責任組合員(※ファンド運営者)は、○条に定める範囲にて、以下の各号のとおり組合員(無限責任組合員と有限責任組合員(※ファンドオーナー)の総称)に対して分配金を支払うものとする。
⑴投資証券等について処分収益を受領した場合(※上記①の理由で収益が生じた場合)
無限責任組合員は、投資証券等について処分を行いその結果収益を受領したときは、当該処分収益を受領した後○ヶ月以内に、処分等に要した一切の費用を控除した上で、○条の定めに従い分配する。
⑵投資証券等に関して配当、利息などを受領した場合(※上記②の理由で収益が生じた場合)
無限責任組合員は、投資証券等に関して配当、利息等を受領したときは、当該配当・利息等を受領した後○ヶ月以内に、処分等に要した一切の費用を控除した上で、○条の定めに従い分配する
⑶前各号以外の理由で組合財産に関して収益が発生しこれを受領した場合(※上記③の理由で収益が生じた場合)
無限責任組合員は、前各号以外の理由で収益を受領したときは、当該収益を受領した後○ヶ月以内に、処分等に要した一切の費用を控除した上で、○条の定めに従い分配する。ただし、当該収益の額が○円以下の場合は、無限責任組合員が裁量により指定した日において当該収益を分配する。」
一方、ファンド契約においては、通常以下の定めがあり、契約に定めがある場合を除いて、組合財産について分配を求めることはできません。
【条項例】
「組合員及び脱退組合員は、本契約に特別定めがある場合を除いて、事由の如何を問わず、本組合が解散する前に組合財産について分配を請求することはできない。」
ファンドに関して、ファンドオーナーの最終的な利益が確定するのは、ファンドの存続期間が満了し、最終的な分配が行われて以降になります。
そのため、存続期間が満了する前に財産分与の問題が生じた場合には、財産分与の対象となる範囲や評価の問題が発生します。
この場合の対応として、ファンド清算前の時点で一定額の支払いをもって合意する方法や、一定額を財産分与として支払った上でファンドの存続期間の満了を待ち、最終分配が確定した段階で分与額を再度計算して過不足を清算する方式などが考えられます。

【ファンド運営者について】
Q7 ファンド運営者が離婚する場合、どのような点が問題となるのでしょうか。
財産分与の観点からおさえておくべきポイントは以下のとおりです。
・ファンド持分の制約
ファンド運営者の持分は、ファンドの運営責任と密接に結びついているため、以下のように譲渡制限や処分禁止が定められていることが通常です。そのため、財産分与の際には持分の評価だけでなく、持分をどのように処理するかも問題となります。
【条項例】
「組合員は、組合財産に対する持分について、裁判上及び裁判外の事由の如何を問わず、譲渡、質入れ、担保権設定その他一切の処分をすることができない。」
・報酬等の種類と評価
ファンド運営者が受け取る報酬、利益には主に以下の4つがあります。条項例と併せてご紹介します。
①管理報酬
ファンド運営に関する日常業務の対価として支払われるものです。
一定額で支給したり、出資約束金額(組合員が出資することを約した金額)や投資総額(ある時点において、組合が取得した投資証券等の取得価額の合計額)などに対する一定割合をもって支払われることが一般的です。
【条項例】
「無限責任組合員は、管理報酬として、以下の各号に定める額を、当該事業年度の期初から〇日以内に、毎年前払いで現金にて受領するものとする。
⑴最初の事業年度
総組合員の出資約束金額の合計額の〇%相当額
⑵第2事業年度以降、出資約束期間の満了する事業年度まで
各事業年度について、総組合員の出資約束金額の合計額の〇%相当額
⑶出資約束期間が満了する事業年度の翌事業年度以降
各事業年度について、当該事業年度の直前事業年度の末日における投資総額の〇%相当額」
②成功報酬
ファンドに収益が生じた場合の対価として支払われるものです。
収益に対する一定割合をもって支払われることが一般的です。
【条項例】
「無限責任組合員は、成功報酬として、第〇条に従い計算される金額(※例:収益の一定割合)を受領するものとする。」
③キャリードインタレスト(Carried Interest)
成功報酬の支払いに代えて、ファンドオーナーに対する報酬としてではなく、ファンドオーナーが保有するファンド持分の権利の実現として、ファンドの収益に対して一定割合が支払われることがあります。
【条項例】
「第〇条に定める処分収益の分配は、以下に定める順位及び方法に従い行うものとする。
⑴全ての組合員等に対して行われた組合財産の分配額の累計額及び当該分配において前〇項に基づき全ての組合員等に対し行う分配額(以下「分配可能額」という。)の合計額が、全ての組合員等の出資約束金額の合計額に達するまで、組合員等に分配可能額の100%を分配する。
⑵無限責任組合員に分配可能額から全ての組合員等の出資約束金額の合計額を控除した額の〇%を分配する。
⑶組合員等に分配可能額から全ての組合員等の出資約束金額の合計額を控除した額の〇%を分配する。」
※上記条項例は、無限責任組合員と有限責任組合員との間で、組合持分に基づく分配を行うものとして規定しています。
④投資先等から受領する報酬、手数料
無限責任組合員が投資先等から直接報酬を受け取る場合もあります。
報酬の名目については、投資先の役員に就任した場合の役員報酬のほか、アドバイザーとして関与した場合の報酬など多岐にわたります。
これらの報酬は、ファンドに関与した結果もたらされるものです。そのため、当該報酬の支払いがあった場合には、当該相当額についてファンドから支払う管理報酬を減額したり、そもそもそのような報酬を受け取ることが禁止される場合もあります。
【条項例】
「無限責任組合員は、投資先から手数料又は報酬その他の対価を受領することができる。当該対価を受領した場合、各組合員は、無限責任組合員が投資先から受領した報酬相当額について、管理報酬の支払いを免れるものとする。」
管理報酬は比較的明確に評価できますが、その他の報酬についてはファンドのパフォーマンス等によって影響を受けるため、また、対象となる期間が長期にわたるケースも多いため、基準時や評価方法等が問題となりやすいです。
・報酬等の発生時期と評価
別居後に確定した報酬が、どの程度財産分与の対象になるかが争点となります。
例えば、成功報酬が別居前の投資活動の成果であるのか、それとも別居後の成果であるのかなど、双方の主張が対立する場合があります。
Q8 管理報酬を先払いで受領した関係で、別居開始後に報酬の精算(クーローバック)が発生しました。この場合、精算分は財産分与の対象になるのでしょうか。
ファンド投資家と同様、ファンド運営者についても以下のような場合に分配金を返還しなければならないと定められていることが一般的です。「GPクローバック」といわれます。
・成功報酬やキャリードインタレストが先払いで支払われた場合において、当初の見込みが外れて投資実績が悪化し、成功報酬等が過払いの状態になった場合
・適正な成功報酬額を超えて支払いを行ったことが判明した場合
【GPクローバックに関する条項例】
「本組合の清算手続における分配を行う日の時点において、無限責任組合員が第○条に定める成功報酬を受領している場合で、かつ~(略)の場合は、~(略)のいずれか小さい金額に相当する額を、本組合に速やかに返還するものとする。かかる返還金(以下「クローバック金額」という。)は、本組合への支払いをもって、各組合員等へその持分金額に応じ按分の上帰属する。」
クローバックは、支払い済みの報酬等について後から清算するものです。
そのため、原則として、クローバック分を考慮、つまり共有財産から控除した上で財産分与を行うことになります。
ただし、クローバックが発動した原因がファンド運営者である配偶者自身の故意・過失などによって生じたものである場合(例:財産分与を逃れるために意図的にクローバックを生じたさせた場合など)には、返還が生じた理由に応じてクローバック分を考慮せずに財産分与が行われる可能性があると考えます。
Q9 成功報酬の対象となる期間の途中で別居が開始した場合、この成功報酬の一部が財産分与の対象となるのでしょうか。
成功報酬はファンドに収益が生じた場合の対価として支払われるものであり、収益に対する一定割合をもって支払われることが一般的です。
そのため、成功報酬の対象となる期間の途中で別居が開始した場合には、成功報酬の一部が財産分与の対象に含まれると考えられます。
ただし、管理報酬は一定の期間(半期、一年など)ごとに支払われるのに対して、成功報酬は収益が出た場合やファンド解散時に支払われることが多く、対象となる期間が長期になるケースが多いです。
そのため、例えば10年経過して成功報酬が発生した場合に、最初の1年目の段階で別居が開始したケースと、9年目の段階で別居が開始したケースとで、成功報酬に対して同程度に夫婦の協力関係があったとはいえません。
この場合は、期間按分、つまり同居期間と別居期間を按分して評価する方法などが検討されることになります。
一方、成功報酬が期間ではなくある特定の事象を理由として生じるものである場合、その発生原因となる事情が別居前に発生している場合には、支払時期が別居後であったとしても、それは単に支払時期に関して猶予されているものに過ぎないとして、成功報酬の全てが財産分与の対象になる可能性もあります。
したがって、成功報酬の発生条件や支払条件を精査して主張を組み立てる必要があります。
Q10 LPS契約に基づく報酬とは別に、投資先から報酬を受領しました。その結果、管理報酬が減額されることになりましたが、管理報酬の受領は別居前で、減額分の調整は別居後に行われました。この場合、減額分は財産分与にあたり考慮されるのでしょうか。
Q7でご紹介のとおり、ファンド運営者は投資先から報酬を得る場合があります。
投資先から報酬を受領してもその分だけ管理報酬が減額される(つまり、トータルの報酬額は同じ)よう定められている場合は、管理報酬の減額に関して落ち度がある訳ではありません。
そのためこの場合は、減額分を考慮して、つまり減額された分を共有財産から除外して財産分与を行うことになると考えられます。
Q11 LPS契約書をみると、「成功報酬」という規定がありません。この場合、管理報酬だけが支払われているということでしょうか。
Q7でご紹介したとおり、ファンド運営者が得る報酬等にはいくつか種類があり、「報酬」という表現が用いられていない場合もあります(キャリードインタレスト、投資先から受領する手数料など)。
そのため、LPS契約書を確認する際には、「報酬」という表現に限らず、ファンド運営者に対して報酬等の利益が発生していないかよく確認する必要があります。

【ファンド投資家・ファンド運営者共通】
Q12 離婚に備えてできる準備にはどのようなものがありますか?
財産分与においては、どれだけ事前に資料を収集できるかが重要です。離婚に向けて別居を検討している場合には、別居前の同居期間中に配偶者の財産資料の収集を行うことが必要になります(別居後に相手方宅で収集することには問題が生じやすいです)。
離婚のプロセスと準備については以下のコラムをご参考ください。
・離婚問題の決着に向けて 〜離婚のプロセスと準備〜
・財産分与と財産調査 〜「いつ」「なにを」「どのように」調べるか〜
Q13 ファンド関係の契約書が手元にあるが、分量が多く、また見慣れない単語・表現が多く理解できません。離婚に向けてどのように準備を進めるべきでしょうか。
Q12のとおり、事前準備として資料収集が重要となります。
一方、どのような資料を収集すればよいのか、また、収集した資料をどのように分析すれば良いのか、特に配偶者にとってはご自身で判断できないこともあるでしょう。
ファンド契約においては、LLP(有限責任事業組合)、LPS(投資事業有限責任組合)、LP(有限責任組合員)、GP(無限責任組合員)など、特有の言葉が多用されています。
自身がファンドに関与していない立場である場合、契約書の内容を一見して理解することは極めて困難です。
また、持分や報酬債権の種類や性質、ファンドの構成、分配金や報酬などの支払時期、金額・方法などを契約書をみてご自身で正確に判断することも難しいでしょう。
ファンドに関して財産分与が問題となる場合は、ご自身がファンドに関与している立場であるか、配偶者がその立場にあるかに関わらず、離婚によるインパクトを把握することは重要です。
離婚が懸念される場合には、なるべく早期に弁護士に相談することをおすすめします。
【実例・コメント】
当事務所が取り扱ってきた事案の中で、配偶者(ファンド運営者)から提示された財産分与額がファンドからの収益を適切に反映したものか疑わしいとして争点化したケースがあります。
調査の結果、成功報酬の一部について、支払時期が離婚後であったことを理由に財産分与の対象から除外して計算されていることが明らかとなりました。
ファンドオーナー、ファンド運営者、いずれも収益構造(分配に関する定めや報酬体系)が複雑で、一見して理解できないケースが多いです。そのため、ご自身での対応ではこれらの事実を正しく理解することが難しい場合もあります。
実例の詳細については当事務所までお尋ねください。

以上、ファンドオーナー・ファンド運営者世帯の離婚で頻発する財産分与問題について解説してきました。
このほか、財産分与については以下のコラムも是非ご覧ください。
・資産の多い夫婦が離婚する場合の財産分与
・特有財産の立証 ー財産分与を回避する方法ー
・財産分与と財産調査 〜「いつ」「なにを」「どのように」調べるか〜
請求する側、支払う側、いずれにとっても財産分与対策はなるべく早期に実施することが重要です。
現時点で離婚が懸念されない場合であったとしても、現在のリスク状況を確認しておくことは非常に有益といえます。
離婚問題でお悩みの方は、初回のご相談は30分間無料※ですのでお早めに当事務所までご相談ください。
※ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。