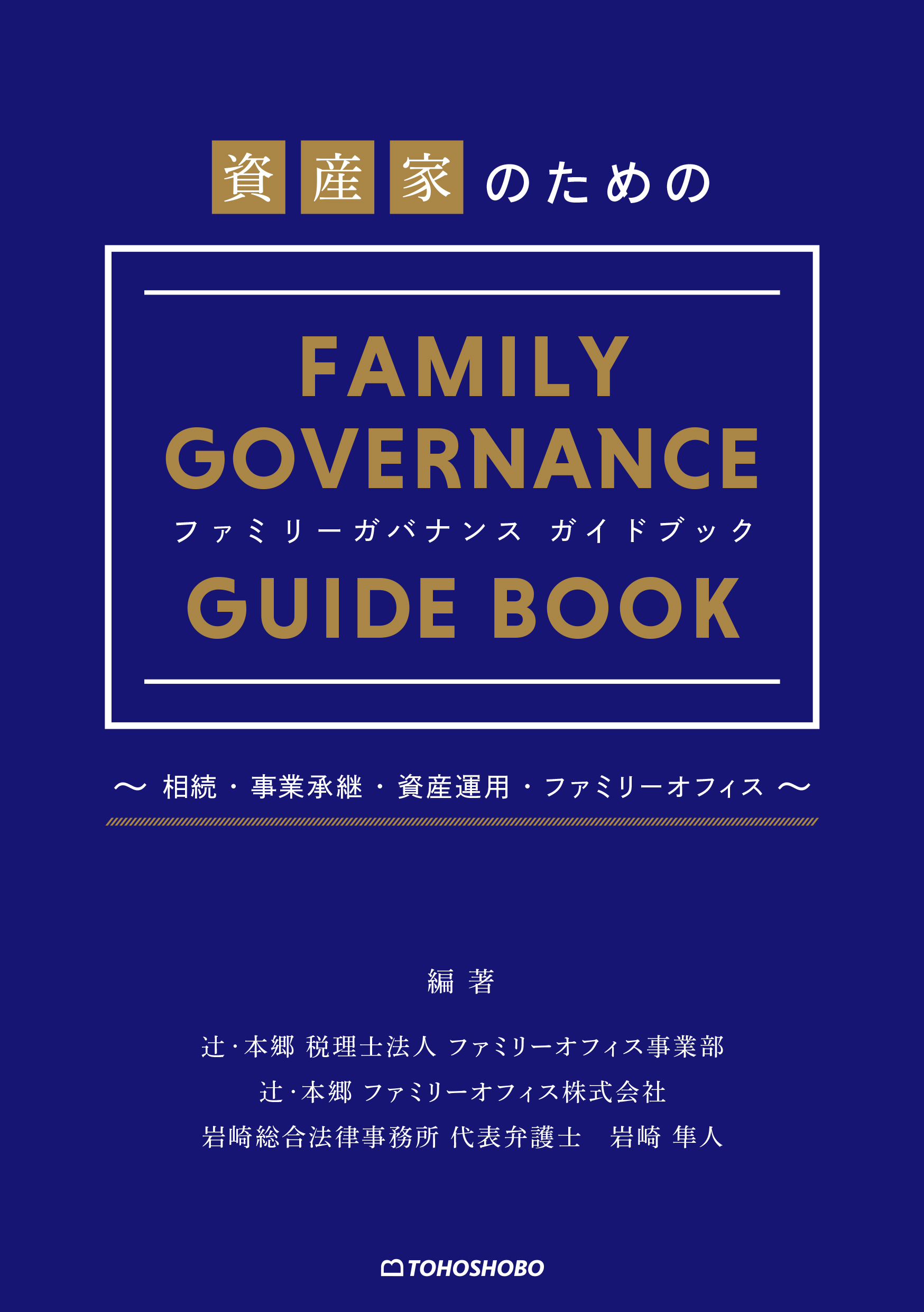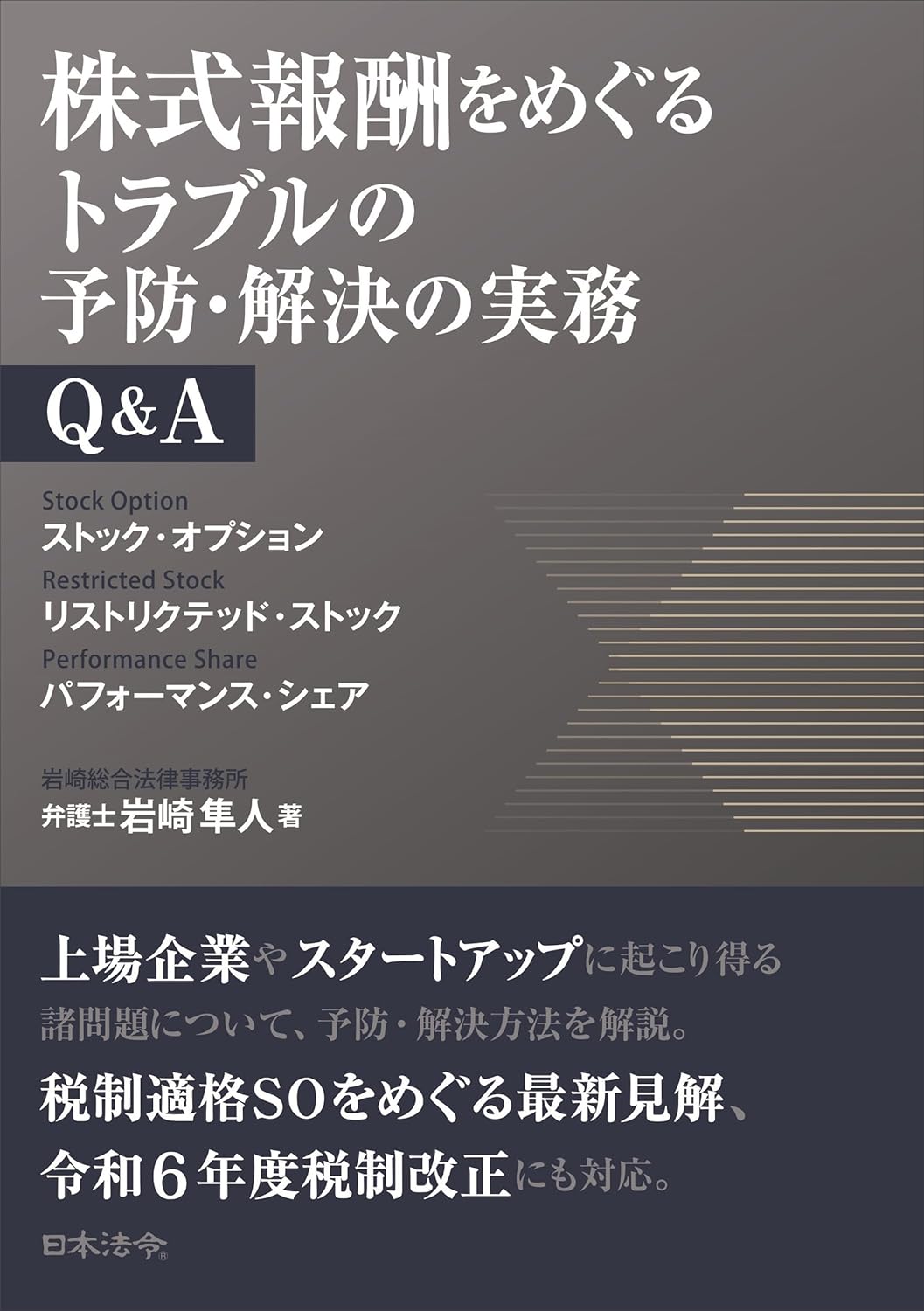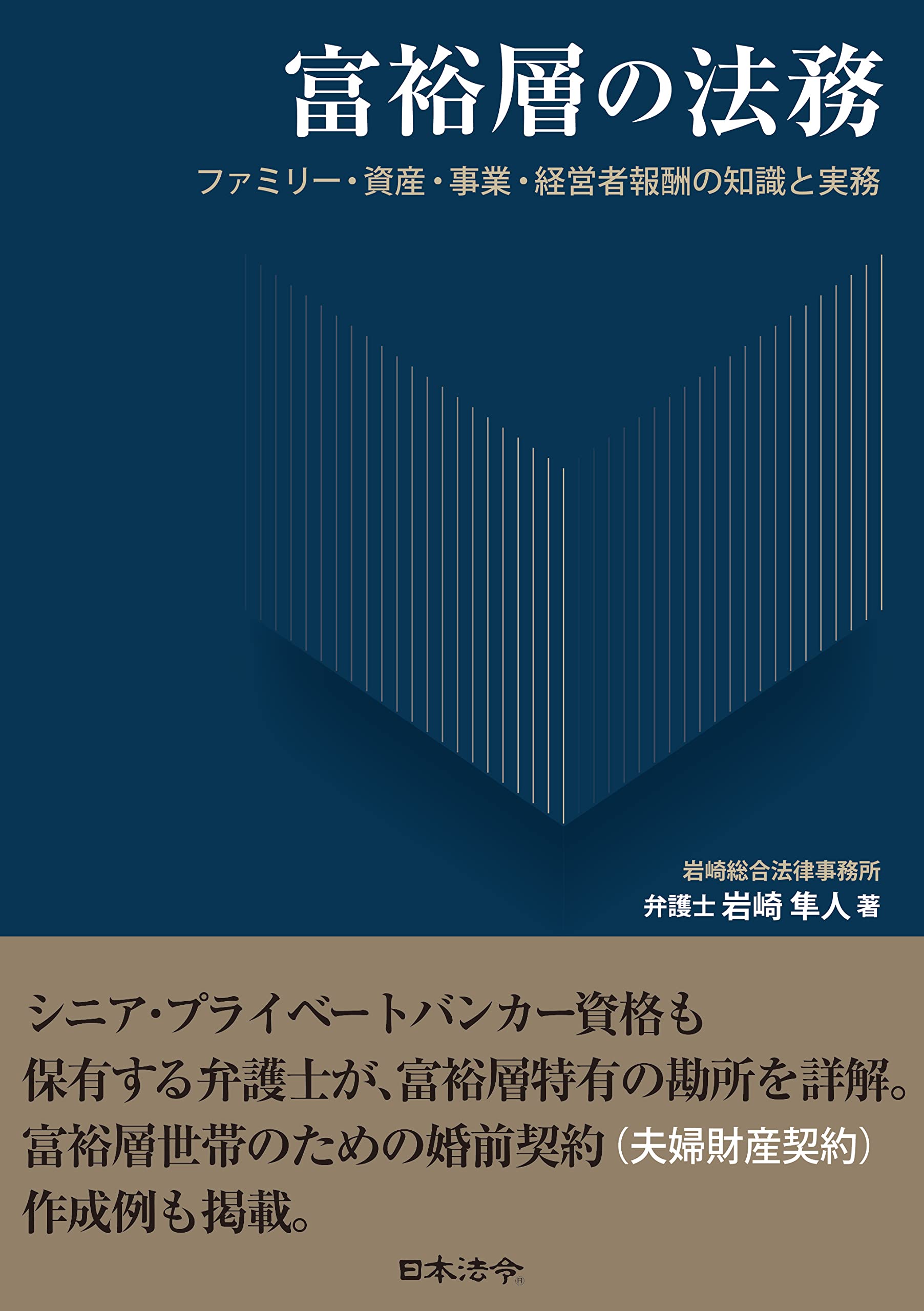2023年3月21日(火曜日)
生前の遺留分対策と遺留分侵害額請求紛争
経営者世帯の相続においては、「遺留分」を巡る問題が高確率で発生します。
資産の規模や種類の多様さ、変動の複雑さから相続財産の範囲、相続財産たる自社株式や不動産の評価、特別受益等を巡って争いとなるためです。
以下では、被相続人によって生前に行われた遺留分対策を巡る争いについて、特に経営者の相続に特有のポイントを、Q&A形式で解説いたします。
岩崎総合法律事務所では、経営者、高額所得者などのお客様に対する法務サービス Legal Prime® を通して、相続紛争案件のノウハウや経験を蓄積してまいりました。経営者の相続紛争の問題について、お客様にとって最善の解決となるようにサポートしています。
当事務所では、生前に資産承継計画を検討される際の助言や設計もサポートしています。遺留分対策を含む生前の資産承継計画についてご関心をお持ちの方も是非ご相談ください。
弊事務所では、富裕層法務サービス Legal Prime® を通じ、資産家、投資家、会社経営者などの資産・収入の多いお客様に対し多様なサポートを提供してまいりました。
これにより得られた知見の一部を書籍化し発売中です。ご興味をお持ちいただけましたら、書影をクリックして詳細をご確認ください。
目次
- Q1 被相続人が遺留分問題に対して生前に対策していたようです。一見、自分の遺留分に侵害はないようにも見えますが、承服できません。生前に行われた遺留分対策について、何も言うことはできないのでしょうか
- Q2 既にしてしまった「遺留分の放棄」をなかったことにできますか
- Q3 既にしてしまった「除外合意」・「固定合意」をなかったことにできますか
- Q4 生前の「財産流出」を取り戻せますか
- Q5 会社の資産・事業を分割して相続人たちで承継しました。それぞれの承継資産の「評価」について注意すべきことはありますか
- Q6 遺言書に遺留分侵害額「請求先の指定」があります。従わなければいけませんか
- Q7 遺留分対策として「養子縁組」が行われているようです。こうした養子縁組は無効にできるのでしょうか
- Q8 生前贈与された一棟ビルがあります。これまでの賃料収入累積は相当高額です。これは遺留分の基礎に入らないのでしょうか
- Q9 ある相続人の「資産管理会社」に生前贈与が行われました。相続人個人への生前贈与ではないのですが、遺留分で考慮されるのでしょうか
Q1 被相続人が遺留分問題に対して生前に対策していたようです。一見、自分の遺留分に侵害はないようにも見えますが、承服できません。生前に行われた遺留分対策について、何も言うことはできないのでしょうか。
特に事業を営む方の相続において親族内事業承継を行うときには遺留分の問題は避けては通れません。
経営者が事業承継計画を立てるとき遺留分の問題は必ず検討する論点ですが、遺留分は法律が定める制度ですから、事前の対策といってもどうしても限界があります。
しかし、自身の死後、会社が引き続き反映していくことを願って、少しでも遺留分問題が顕在化しないよう、生前に対策するのです。
この対策は、正しく行われるものであれば法的に問題はなく、また被相続人の遺志として尊重されるべきではあります。
しかし一方で、間違った対策が行われている場合や、後継者が自身の利益のために事実関係や評価を歪曲し、不当な遺産分配を行おうとする場合もあります。
こうしたとき、生前に行われた遺留分問題対策の意義、その有効性などが争われ、遺留分侵害額請求事件に発展することがあります。
ここでは、生前に行われた遺留分問題対策にかかる論点のうち、よく争点になるケースをいくつか取り上げて説明していきます。
Q2 既にしてしまった「遺留分の放棄」をなかったことにできますか

被相続人から、生前に遺留分放棄を迫られて家庭裁判所に申立して、遺留分を放棄する場合があります(民法1049条1項)。
遺留分を放棄してしまえば、その後は遺留分侵害額請求権を行使することはできなくなります。
しかし、被相続人の死後になって遺留分放棄の前提となっていた事実が異なっていたことが発覚する場合もあります。
また、遺留分放棄から相続開始までに相当の時間が経過していたような場合には、自身の状況、他の相続人との関係、遺産の状況が大きく変動していたりと、「遺留分を放棄するべきではなかった」と考える場合もあります。
このとき、遺留分の放棄については、申立の前提となった事情が変わり、遺留分を放棄することが不当となった場合には、放棄許可の審判が取り消しとなる可能性があります。
Q3 既にしてしまった「除外合意」・「固定合意」をなかったことにできますか
特定の者に事業を承継させようと考える場合、遺留分対策のために経営承継円滑化法に基づいて、除外合意ないし固定合意あるいはその両方をもちかけ、すべての相続人の間でこうした合意を結んでいる場合があります。
除外合意をすれば、当該株式が遺留分侵害額請求の対象とならなくなります。
固定同意をすれば、遺留分侵害額請求との関係で、当該株式の評価額が合意時に固定され、その後の上昇分は考慮されなくなります。
しかし、その除外合意ないし固定合意の前提に争いがあった場合や、錯誤が生じていたような場合には、この無効・取消を巡って紛争となります。
また、除外合意、固定合意を結ぶ際に、付随合意を利用する場合があります。
付随合意として、例えば後継者が経営権を承継し、非後継者はこれを争わず遺留分の計算対象に加算しないものとする代わりに、後継者が非後継者に毎年一定の金銭の支払いを約束するといった取り決めがされる場合があります。
こうした付随合意に反した場合には、債務不履行が問題となります。
もっとも、かかる債務不履行をもって除外合意、固定合意の解除事由とまでなるかについては確定見解がないところではあります。
一方損害が生じていればかかる損害の賠償義務は生じるものと思われます。
Q4 生前の「財産流出」を取り戻せますか
遺留分の侵害の認定には、そもそも遺産の範囲(相続開始時の積極財産や加算される生前贈与の財産)がどのようなものかが問題となります。
この点、遺産の範囲を縮小するために生前贈与を用いていると思われる場合があります。
特に、贈与の「履行時点」は相続開始時から比較的遠くない時期であるにもかかわらず、贈与契約書上の「締結日付時点」は相当過去になっている場合です。
どういうことかというと、遺産に組み込まれる生前贈与かどうかは、その生前贈与が相続発生時から遡っていつのことだったかが論点になります。そして、その相続開始から遡る時点というのは、贈与契約の「締結日付時点」であって、「履行時点」ではないのです。
例えば相続開始の半年前に相続人に対して贈与の履行があったとしても、この贈与契約の締結日が相続開始日から10年より前だと、その贈与額は遺留分では原則として考慮されません。
この点を意識してか上記のようなケースがあり、こうした場合には贈与契約書の日付がバックデートであるなどの疑いがある場合が生じますから、大きな論点となります。
また、生命保険や死亡退職金などが遺留分対策として用いられている場合もあります。
Q5 会社の資産・事業を分割して相続人たちで承継しました。それぞれの承継資産の「評価」について注意すべきことはありますか

事業承継を円滑に進めるため、遺留分問題を検討するとき、その会社の資産・事業を分割する場合があります。
すなわち、会社にはその収益のコアとなる事業とそうでないものがある場合があり、そうした場合に、コアビジネスに直接関連しない金融資産や不動産などを、金融資産運用業や不動産業として切り出して(別法人などを設立し)、これを後継者でない者に承継させるのです。
これによって、後継者に承継させる株式の価格を低くすることができ、加えて非後継者にも承継させる相続財産を増やすことができるので、遺留分問題に一定の効果があります。
もっとも、こうした切り分けですべての遺留分問題が解消されているかはケースバイケースであり、後継者に承継されるコアビジネスの株式の評価と、非後継者に承継されるノンコアの(株式の)評価もその評価方法や前提とする事実・資料によって相当に幅が出てしまうため注意が必要です。
Q6 遺言書に遺留分侵害額「請求先の指定」があります。従わなければいけませんか

生前の遺留分問題対策として遺留分侵害額請求先を指定している場合があります。
遺留分侵害額請求については、その請求権の行使にあたって所定の順序があるのですが、これを指定されるということです。
まず、遺留分侵害額請求の対象に贈与によるものと遺贈によるものがある場合には、遺贈を受けた者が先に対象になります(民法1047条1項1号。この順序は遺言によって変更することはできません)。
遺贈による受遺者が複数ある場合で、遺言者が遺言で順序を定めている場合には、その定めに従います(なお、この指定がない場合には、全ての遺贈について目的物の価額の割合に応じて計算されます)。
生前贈与が複数ある場合、その生前贈与が同時に行われたものであれば、遺言者が遺言で順序を定めている場合には、その定めに従います(民法1047条1項2号ただし書き。この指定がない場合には、全ての生前贈与について遺贈と同様、目的物の価額の割合に応じて計算されます(同号本文))。
同時に行われた生前贈与でない場合には、新しい贈与から順次前の贈与に対して受贈者が遺留分侵害額請求の対象となります(民法1047条1項3号)。同時になされたものではない生前贈与については、遺贈と異なり遺留分侵害額請求の対象とする順序を指定することはできず、単純に時間的先後関係に従って順序が決まります
このように遺留分侵害額請求は、以下の順番になされていき、それぞれの受遺者、受贈者が対象となって、遺留分侵害状態を解消していくことになります。
優先順位の遺贈
⇒劣後順位の遺贈
⇒(同時実施の場合の)優先順位の生前贈与
⇒(同時実施の場合の)劣後順位の生前贈与
⇒新しい生前贈与
⇒古い生前贈与
なお、受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰するものとされています(民法1047条4項)。
これは、本来なら請求を受けるはずのない者が、先順位者の資力状況という偶然の事実によって損害を被ることは不公平であるとされるためです。
こうした仕組みを踏まえ、被相続人である富裕層が生前の遺留分問題対策として、遺留分侵害額請求の影響を押さえ込むべき資産として重要なものから順に生前贈与していき、遺贈によるとしてもそれには先に侵害額請求の対象にするものと、それに続くものを遺言書にて指定しておくことを実施している場合があります。
こうした指定がある場合には、原則としてかかる指定の有効性を確認後、これに基づいて遺留分侵害額請求権を順位づけて行使していくこととなります。
Q7 遺留分対策として「養子縁組」が行われているようです。こうした養子縁組は無効にできるのでしょうか
相続税対策としてはよくあるものの遺留分問題対策として実施されている例はあまりないように思いますが、
法定相続人である子の人数を養子縁組で増やし、それぞれの相続人の遺留分を減少させるという方法もありえます。
こうした養子縁組が実施されていたとしても、養親と養子との間に真正な縁組の意思がないと養子縁組は無効となり、養子縁組無効を確認するための裁判手続や、それを経ずとも遺留分の裁判手続の中で養子縁組の無効性が考慮されることはありえます。
裁判実務の傾向では、養親子関係を創設する目的が併存してさえいれば養子縁組を無効としないものが多いです。
しかし、遺留分対策以外の目的が考えられないなど特異状況の場合には、そもそも養親の意思能力に問題があったなど個別具体的事情の下では養子縁組を無効とするケースもあります。
Q8 生前贈与された一棟ビルがあります。これまでの賃料収入累積は相当高額です。これは遺留分の基礎に入らないのでしょうか
配当・賃料等果実を生じさせる資産を早期に譲渡し、少なくともその果実自体は相続財産でも特別受益でもないとして遺留分を減少させるような方法がとられている場合もあります。
こうした果実は遺留分侵害額請求権の計算の基礎には通常入ってきません。
改正前の民法1036条は、減殺の請求があった日以後に限ってのものではありましたが、受遺者は、その返還すべき財産の外、果実を返還しなければならないものとされていました。
しかしながら、遺留分侵害の請求が2019年7月1日施行の相続法改正によって金銭請求化されたことに伴い、旧民法1036条も削除されています。
そのため、今後は、果実についてかかっていくことはできず、一般の金銭請求権同様に、法定利率(民法404条)による遅延損害金のみ発生するように整理されたものと考えられます。
Q9 ある相続人の「資産管理会社」に生前贈与が行われました。相続人個人への生前贈与ではないのですが、遺留分で考慮されるのでしょうか
後継者が支配株主である資産管理会社へ生前に財産を移している場合もあります。
形式上は当該資産管理会社は後継者とは人格が異なり、相続人ではありません。
このため、相続開始時から1年より前に資産管理会社に贈与が行われているような場合、遺留分算定の基礎財産に組み入れられないということが形式的な結論です。
しかし、実体としては後継者と資産管理会社が一体のものとして扱われるべき場合もあり、そうした実質面を考慮するときには、相続人への特別受益の期間と同様10年間は持戻しされるという結論が支持されるべき場合もありえます。

以上、の論点について正当な結果を求めるためには、事実関係及び法律関係を整理して、適切な分析に基づいた方針のもと、正確に主張立証していくことが重要です。
もし、相続問題、遺留分の問題を巡ってお悩みの方は、初回のご相談は30分間無料※ですので、少しでもお困りの際にはお気軽にご相談ください。
※ ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。