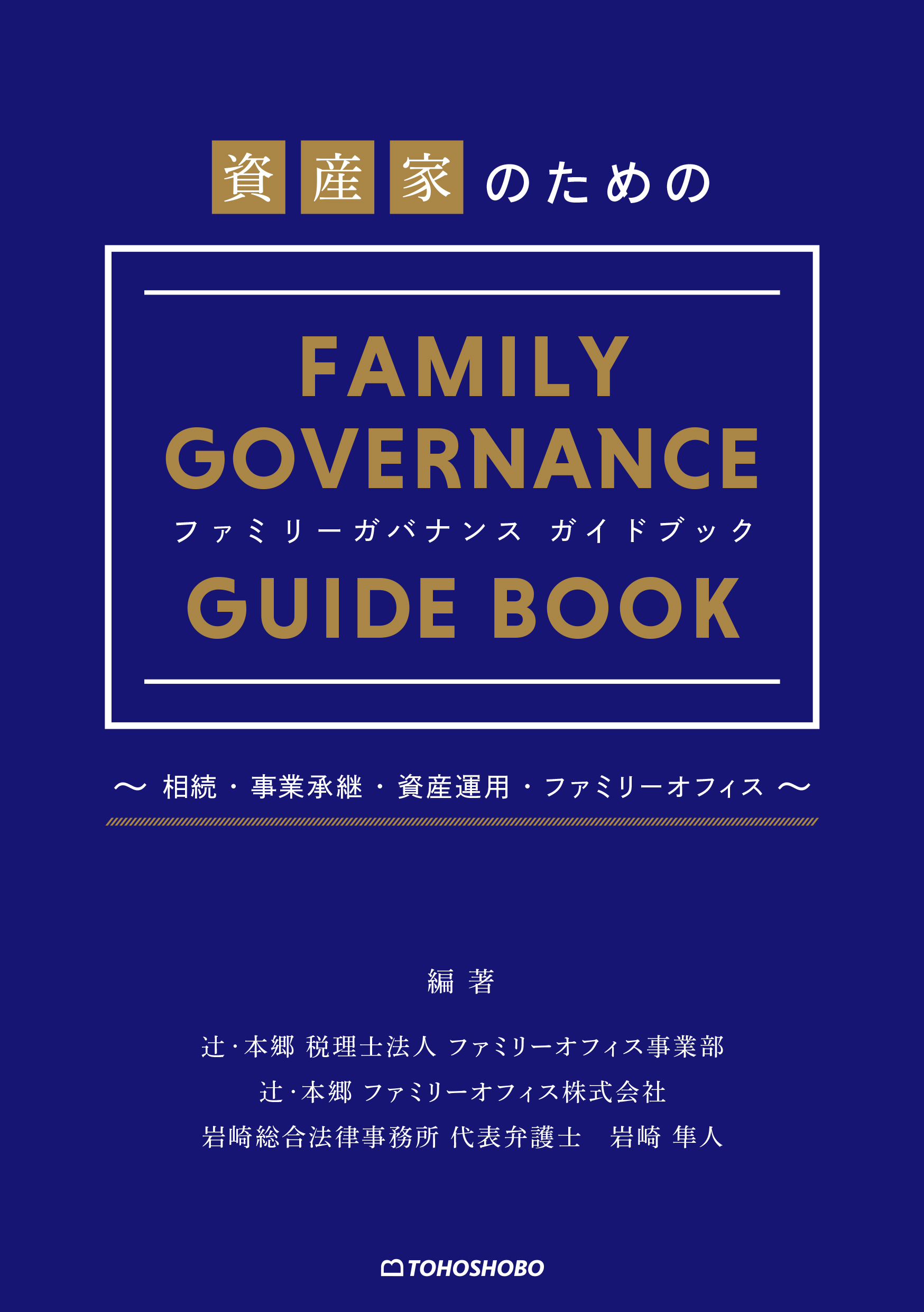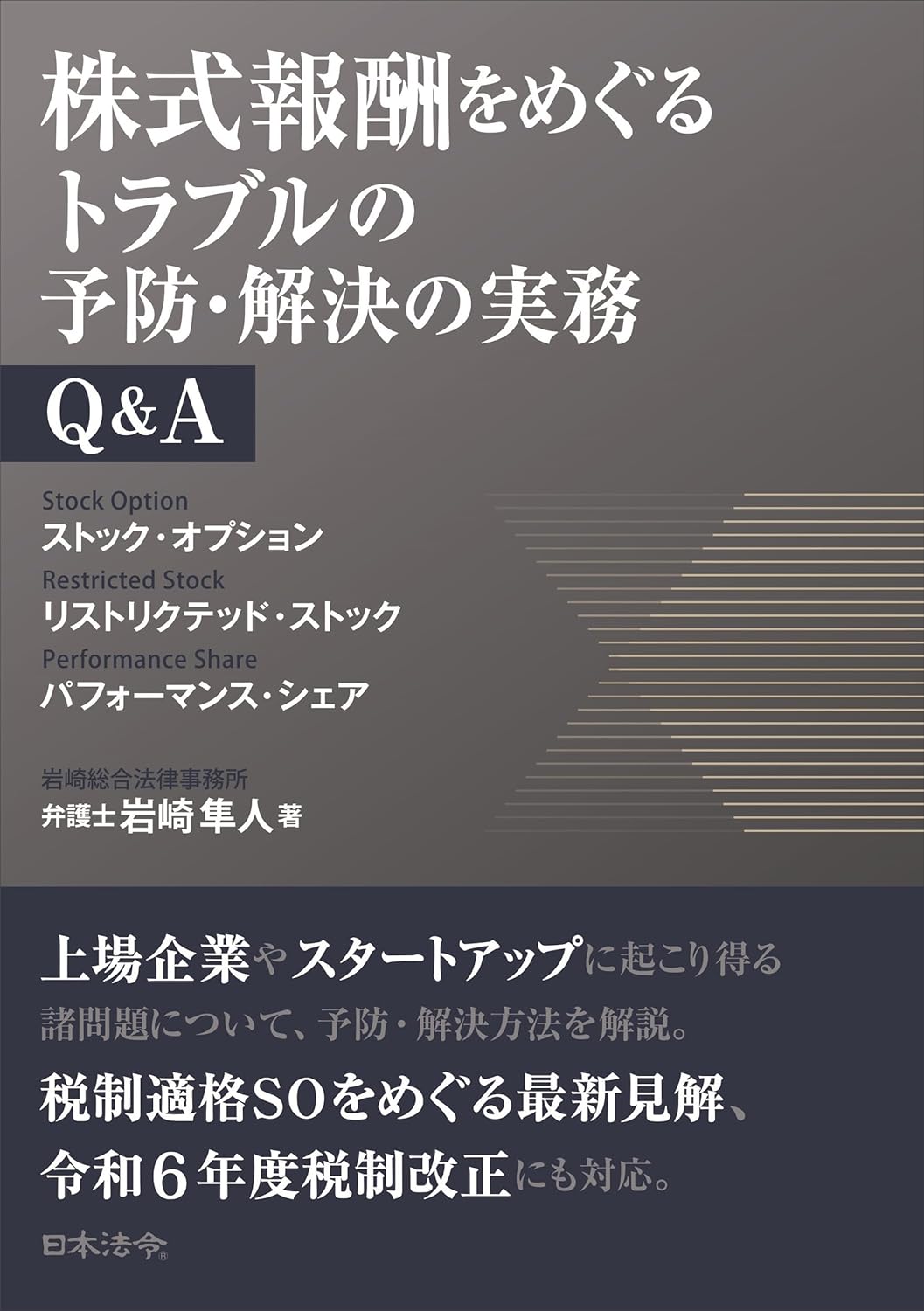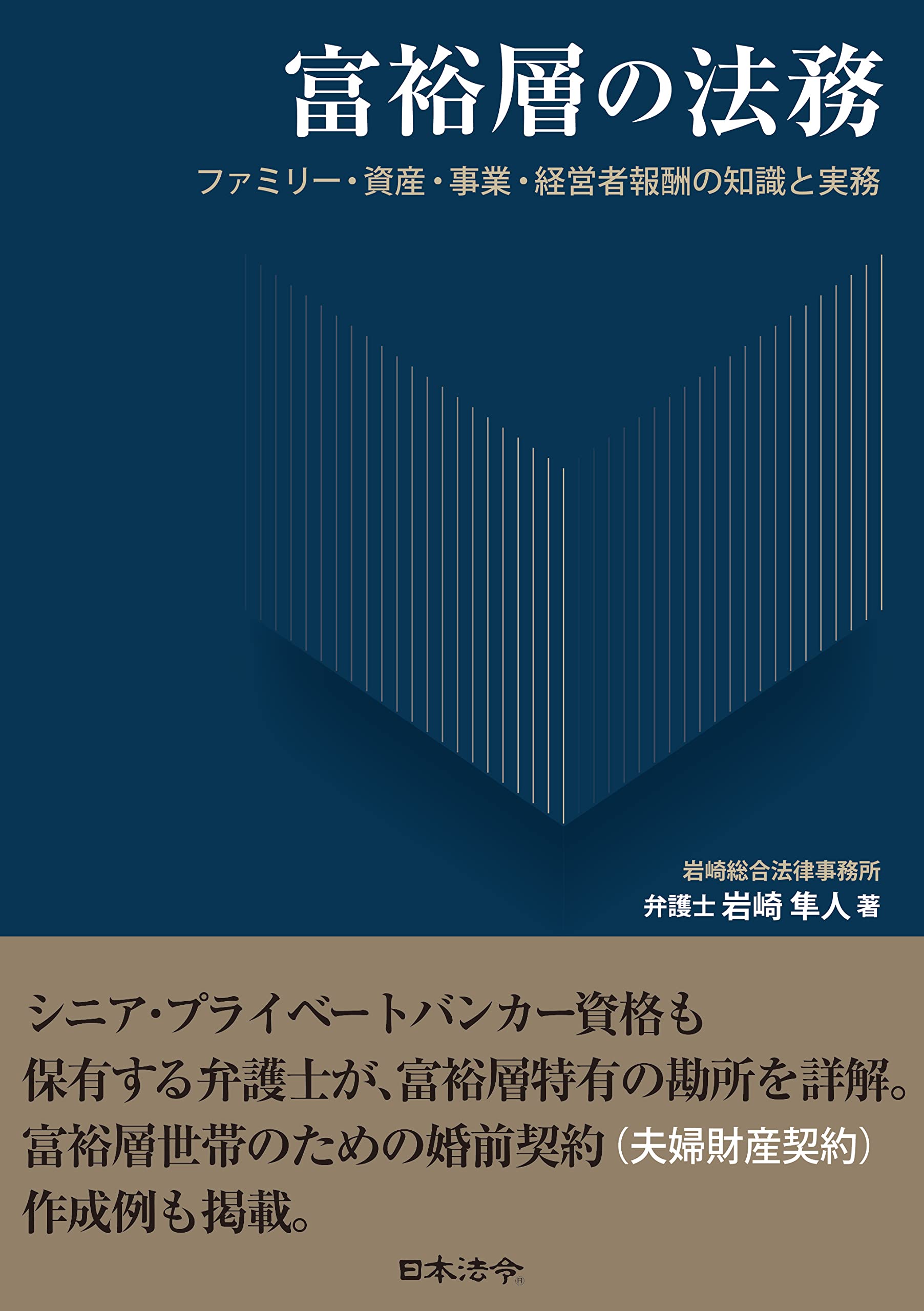2025年1月16日(木曜日)
不動産オーナーの財産分与〜特有の課題と解決策〜
本コラムでは、多くの不動産を保有し不動産賃貸業を営む不動産オーナーの財産分与で問題となる論点と、それらにどのように対処していけばよいかについて解説します。
不動産オーナーの財産分与にあたっては、多くの不動産を保有することに起因する特有の論点が存在します。
また、税務の観点から法人を設立している場合も多く、このような税金対策等が不動産オーナーの財産分与を複雑にします。
岩崎総合法律事務所では、資産家、高額所得者などの「富裕層」と呼ばれるお客様に対する法務サービスLegal Prime®を提供してきました。
これにより培われた不動産オーナーへのサポートの知見やノウハウを生かし、お客様のトラブルが正しく解決されるようサポートさせていただきます。
お悩みの方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
弊事務所では、富裕層法務サービス Legal Prime® を通じ、資産家、投資家、会社経営者などの資産・収入の多いお客様に対し多様なサポートを提供してまいりました。
これにより得られた知見の一部を書籍化し発売中です。ご興味をお持ちいただけましたら、書影をクリックして詳細をご確認ください。
目次
- 結婚期間中に、父が所有していた不動産を相続しました。この不動産は財産分与の対象となりますか。
- 相続財産がどうして対象になることがあるのでしょうか。
- 婚前からの不動産の賃料収入等も財産分与の対象となるのでしょうか。
- 融資の関係から会社名義で多くの不動産を所有しています。財産分与の対象は不動産ですか、株式でしょうか。
- 株式か会社の財産そのものが財産分与の対象になるかで、どういったことが変わってきますか。
- 相続対策で、子どもの法人を用意して不動産を所有させています。この不動産や子どもの法人も財産分与にあたって考慮されますか。
- 財産分与にあたって、不動産はいくらと評価されることとなりますか。
- 不動産を保有している法人はどのように評価されることとなりますか。株式はいくらになるのでしょうか。
- 不動産を処分しなければ財産分与の資金を捻出できません。不動産を売却するにあたって発生する仲介手数料や税金等はどのように取り扱われますか。
- 子ども名義となっている不動産などは子どもの将来のために贈与したものです。配偶者は浪費癖があるので、離婚後に親権者となる配偶者が管理するのは避けたいです。対策はあるでしょうか。
Q1 結婚期間中に、父が所有していた不動産を相続しました。この不動産は財産分与の対象となりますか。
まず、相続財産や結婚前から保有している財産などは、原則として財産分与の対象になりません(このような財産を「特有財産」といいます。詳しくはこちらのコラムをご参照ください)。
ご相談のケースでは、お父様から相続した不動産とのことですので、この不動産は原則として財産分与の対象にならないものと思われます。
もっとも、それは特有財産であることを立証できた場合に限ります。
財産分与にあたっては、所有している財産が特有財産であることを認めてほしい側から、特有財産であることを立証する必要があります。
この点、例えば、相続したその不動産について、相続の際に相続税の支払いが特有財産から支払われたことを立証できない場合には(夫婦の財産から支出した場合など)、財産分与の対象となるリスクがあります。
また、賃料収入や不動産価格の値上がり分といった果実的なものが財産分与の対象になる可能性もあります。
Q2 相続財産がどうして対象になることがあるのでしょうか。
財産分与は、夫婦が築き上げた財産を清算することを主な目的とするものです。
このため、相続で得たものであったとしても、その維持や価値向上に夫婦の貢献がある場合など「夫婦が築き上げた」と言いうる部分がある場合には財産分与の対象になるということです。
そしてその夫婦の貢献は、夫婦それぞれが実際に手足を動かす必要はなく、例えば婚姻後の給与収入等といった夫婦共有財産をその相続財産のために用いた場合にも観念される可能性があります。
Q3婚前からの不動産の賃料収入等も財産分与の対象となるのでしょうか。
相続財産と同様、婚前の財産であったとしてもその維持や価値向上に夫婦の貢献がある場合など「夫婦が築き上げた」と言いうる部分がある場合には財産分与の対象になる場合があります。
不動産の運用によって得た賃料収入等も同様で、夫婦の協力がある場合には、共有財産として財産分与の対象になる場合があります。自分たちや経営する資産管理会社でその不動産を管理するような場合です。
不動産の運用を第三者(管理会社)に委託している場合はどうか
夫婦それぞれが手足を動かしているわけではないので、そういった貢献は観念しにくいところです。
もっとも、その管理会社に管理手数料(報酬)を支払っている場合には、その支払いの出所が問題になります。
その不動産の賃料収入から支払っている場合であれば夫婦の貢献は観念しにくいですが、給与収入など夫婦共有財産から支払っている場合であれば夫婦の貢献があるものと評価されることがありうるように思います。
【実例・コメント】自分たちで管理している場合には注意
大きな事業規模になっている不動産オーナーや、収入源の多くを不動産収益が担っている場合、一族の代表的なファミリー資産という位置付けの不動産を保有している場合には、ファミリー(自分たち)で管理していることもよくあると思います。
このとき、配偶者の協力を得ていることも見られますが、その際報酬を支払っていなかったり、あるいは不適切な金額である場合には、たとえ相続財産であったとしても財産分与の対象になる可能性があります。

Q4 融資の関係から会社名義で多くの不動産を所有しています。財産分与の対象は不動産ですか、株式でしょうか。
まず、その会社の株式は財産分与の対象となりえます。
財産分与の際に、会社の株式を評価するにあたっては、会社の不動産等の資産の保有状況等も考慮されることとなります。
この点では、会社で保有している不動産等の価値も財産分与の際に考慮されるものといえます。
他方で、会社名義の財産そのものは、会社という第三者名義の財産であるため、財産分与の対象とならないのが原則です。
例えば、この会社が保有している不動産や、これらの不動産を運用することによって得た賃料収入の集積である会社名義の預金口座残高といったようなものそのものは、財産分与の対象にはならないのが原則なのです。
財産分与は、夫婦で築き上げた財産を清算するものであり、第三者の財産に及ぶべきものではないからです。
しかし、例外的に、会社名義の不動産や預金口座残高であっても、それらの財産が直接財産分与の対象となることがあります。
例えば、実質的に夫婦の財産と会社の財産とが一体と見られるようなケースの場合です。
資産管理会社のようなケースが典型的ですが、事業を営んでいる法人であっても小規模経営、個人事業主相当といった評価をされて直接財産分与の対象となった事例があります。
Q5 株式か会社の財産そのものが財産分与の対象になるかで、どういったことが変わってきますか。
会社の財産を相談者個人の財産とみなして直接財産分与の対象とする場合と会社の株式を財産分与の対象とする場合の違いについては、前者の方が、後者よりも、配偶者に分与する額が高くなる可能性があります。
すなわち、会社の株式の価値を評価するにあたっては、会社が抱えている債務といった消極財産も考慮して株式の評価額が決定されることとなります。
他方で、会社の財産を直接財産分与の対象とする場合、財産分与にあたっては、原則として債務は財産分与の対象とならないことから、場合によっては会社の債務といった消極財産が財産分与の際に計上されないことがあります。
この場合には、会社の保有する不動産等といった積極財産のみが財産分与の対象となります。
要するに、会社の負の財産である借金等の債務が考慮されるか否かといったことが大きな違いになる可能性があります。
Q6 相続対策で、子どもの法人を用意して不動産を所有させています。この不動産や子どもの法人も財産分与にあたって考慮されますか。
第三者名義の財産の論点となります。
子の財産については、その財産が形成された経緯を踏まえて、財産分与の対象になるか否か判断されることになります。
相続で馴染みのある「名義預金」(実際のお金の所有者と名義が異なる預金のこと)同様、実質的には親の財産であると評価される場合には財産分与の対象になる場合があります。
例えば、取得原資を誰が支出したか、夫婦の一方が支出したものであるとして、それが贈与の趣旨で行われたものなのか、その後の株式の管理や会社経営は誰がどのように行なっているか、子供の年齢や判断能力等が考慮されます。
そして、その子どもの財産が対象になるとして、それが株式なのか、法人名義のその財産そのものかは前述の論点と同様です。
子どもの財産が対象になるような場合には、法人名義のその財産そのものが財産分与の対象になることも相当にあると思います。

Q7 財産分与にあたって、不動産はいくらと評価されることとなりますか。
不動産がいくらと評価されるかは財産分与の結果を大きく左右する極めて重要な問題です。
もっとも、不動産は株価のような時価がなく評価が困難です。このため、裁判において頻繁に争点化します。
不動産の評価方法については、①実勢価格(取引価額・時価)を算定することを主眼とするものと、②課税評価額を算定することを主眼とするものがあります(不動産の評価方法に関する詳細はこちらのコラムもご参照ください)。
この点、課税評価額を算定する方法としては、Ⅰ 公示価格による方法、Ⅱ 固定資産税評価額による方法、Ⅲ 路線価による方法があります。しかし、いずれもあくまで課税評価額を算出する方法ですので、客観的な交換価値と必ずしも一致しません。
このため、これを考慮するときには内容を慎重に検討し、各地域の特殊性、当該土地の個別的要因、時期的な変動等を加味して適正な補正ないし調整を行わなければいけません。
鑑定書・査定書
評価額の算定にあたっては、不動産鑑定を活用して鑑定書を作成し、これを不動産評価のための資料として提出することもあるほか、不動産仲介業者に査定書を作成してもらい、これを活用することもあります。
査定書は、実務家によって多くの取引事例との比較データを積み上げて査定されるものであるという点で説得力のある資料であり、裁判手続でも不動産の評価資料としてよく利用されます。取得にコストがかからない点も利点です。
他方で、意図的に評価を操作して査定書を作成する事例も珍しくない点には注意が必要です。
【実例・コメント】足して2で割るという判断がよくみられる。ただし、収益物件の場合には注意
裁判実務上は、不動産会社の査定書を基準にしたり、上記の公示価格・固定資産税評価額・路線価による評価方法を参照しながら問題となっている不動産の価格について合意を形成するということもよくあります。
双方が提出する不動産会社の査定書の金額を足して2で割るという単純簡易な方法で判決を示す裁判官も相当多くいる印象です。
ただし、収益物件の場合には注意が必要です。
収益物件の場合には、時価を算定するにあたって、どの程度の収益を得られるかに着目して、その収益を期待利回りで除して資本還元することにより価格を算定する方法が活用されます。
特に一棟ビル、一棟アパートのような不動産や、ホテルや旅館といったオペレーションアセットの収益については、予測を立てることが難しい場合も多く、その評価は通常の不動産よりも困難です。
このため、当事者間でその評価額を巡って激しく対立することもよくあります。
Q8 不動産を保有している法人はどのように評価されることとなりますか。株式はいくらになるのでしょうか。
非上場の会社の場合には時価がなく、その評価が問題となります。
会社を運営していない側からすると、会社内部の状況は通常不明です。収支も複雑であり、不動産よりも評価が困難です。
適切に評価するにあたっては、総勘定元帳など会社の内部の状況をよく示す資料をもとに分析する必要があります。
対外的に示している事業計画書も、その信憑性の問題はあるものの、裁判実務上は重視される傾向にあります。
離婚を検討する際にはこうした資料の扱いには注意を払うべきでしょう。
評価方法
非上場の株式の客観的価値を評価する方法はいくつかあります(詳細な株式の評価方法についてはこちらのコラムをご参照ください)。
それぞれの評価アプローチには一長一短があり、必ず正しい唯一の評価方法が存在するものではありません。
実務上は、ネットアセット・アプローチ(貸借対照表上の純資産から価値を評価する方法)のうち純資産価額に基づいて評価する方式や税務上の評価に用いられる評価方式等を参考にしながら、価格そのものについて合意をするということもよくあります。
あるいは、会社の決算書を参考にして価格を合意することもあります。
また、税務上の評価に用いられる評価方式等で良いと当事者が合意した場合には当該評価方式で評価する場合もあります。
これら合意が何ら調わない時には、裁判手続の中で鑑定をし、公平な評価額を裁判所が定めます。
Q9 不動産を処分しなければ財産分与の資金を捻出できません。不動産を売却するにあたって発生する仲介手数料や税金等はどのように取り扱われますか。
不動産を売却するにあたって発生する仲介手数料や税金等の諸費用は、これを控除した上で、配偶者に分与すべき財産分与額に充当していくこととなります。
Q10 子ども名義となっている不動産などは子どもの将来のために贈与したものです。配偶者は浪費癖があるので、離婚後に親権者となる配偶者が管理するのは避けたいです。対策はあるでしょうか。
信託を活用することが考えられます。
例えば、子ども名義となっている不動産を信託財産として、受託者を自分とするというものです。
受託者は当該不動産を管理処分する権限を有します。このため、離婚となった後でも、その不動産を管理することが可能になります。
子どもが有する株式については、種類株を活用し、無議決権株式としておくことが考えられます。
また、これから子どもに対して贈与を行おうと考えている場合には、贈与を行う際に一工夫することも重要です。
すなわち、贈与契約上で、財産管理者を指定するのです。
具体的には、配偶者に贈与予定の財産を管理させない意思表示を行うとともに、当該財産の管理者を相談者または配偶者以外の第三者に指定しておきます。
財産の浪費を防ぐためには、家庭ごとの個別の事情を踏まえて、契約により手当することが重要です。
以上、財産分与における不動産オーナーの財産分与について解説してきました。
もしお悩みの方は、初回のご相談は30分間無料※ですので当事務所にお気軽にご相談ください。
※ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。