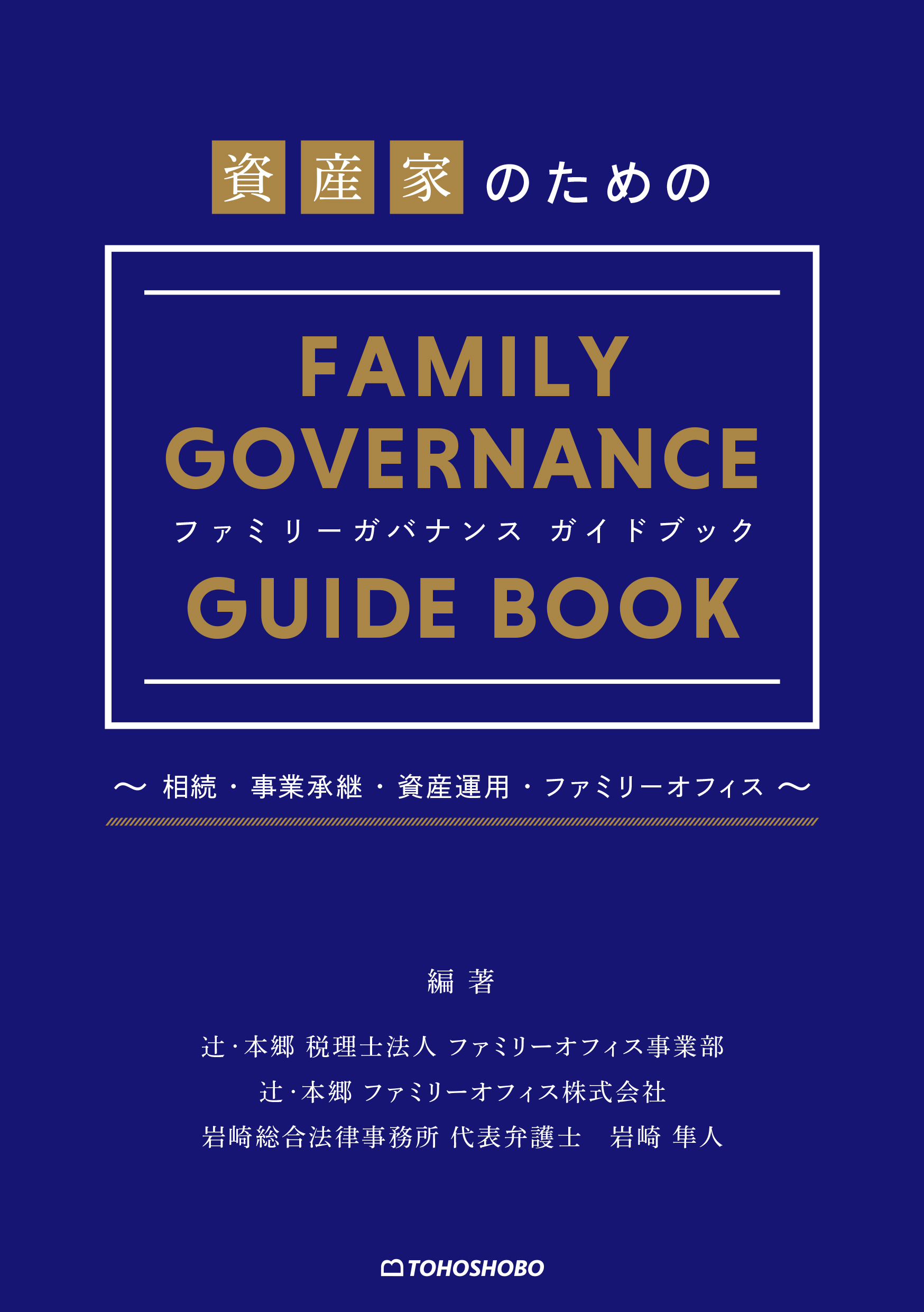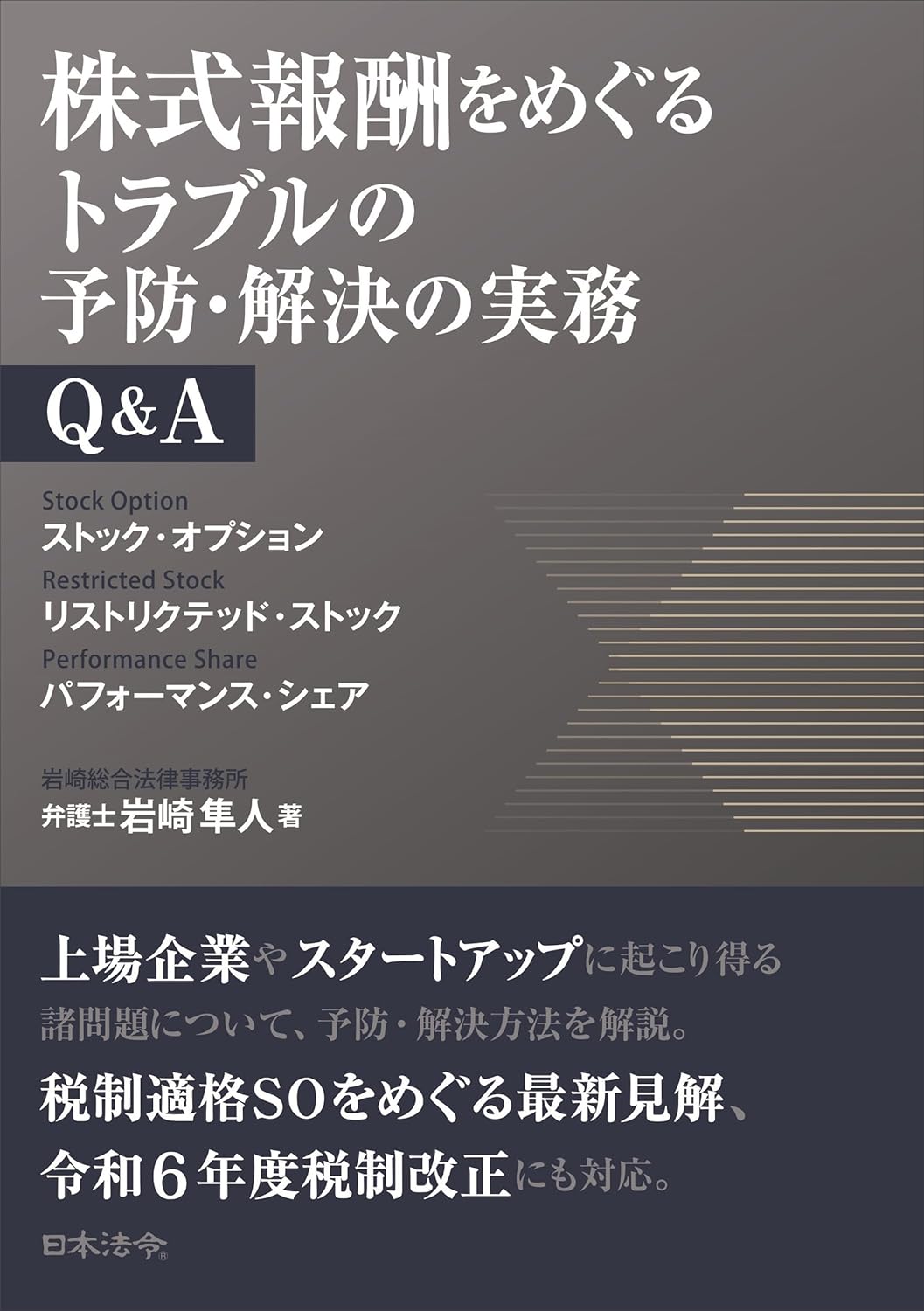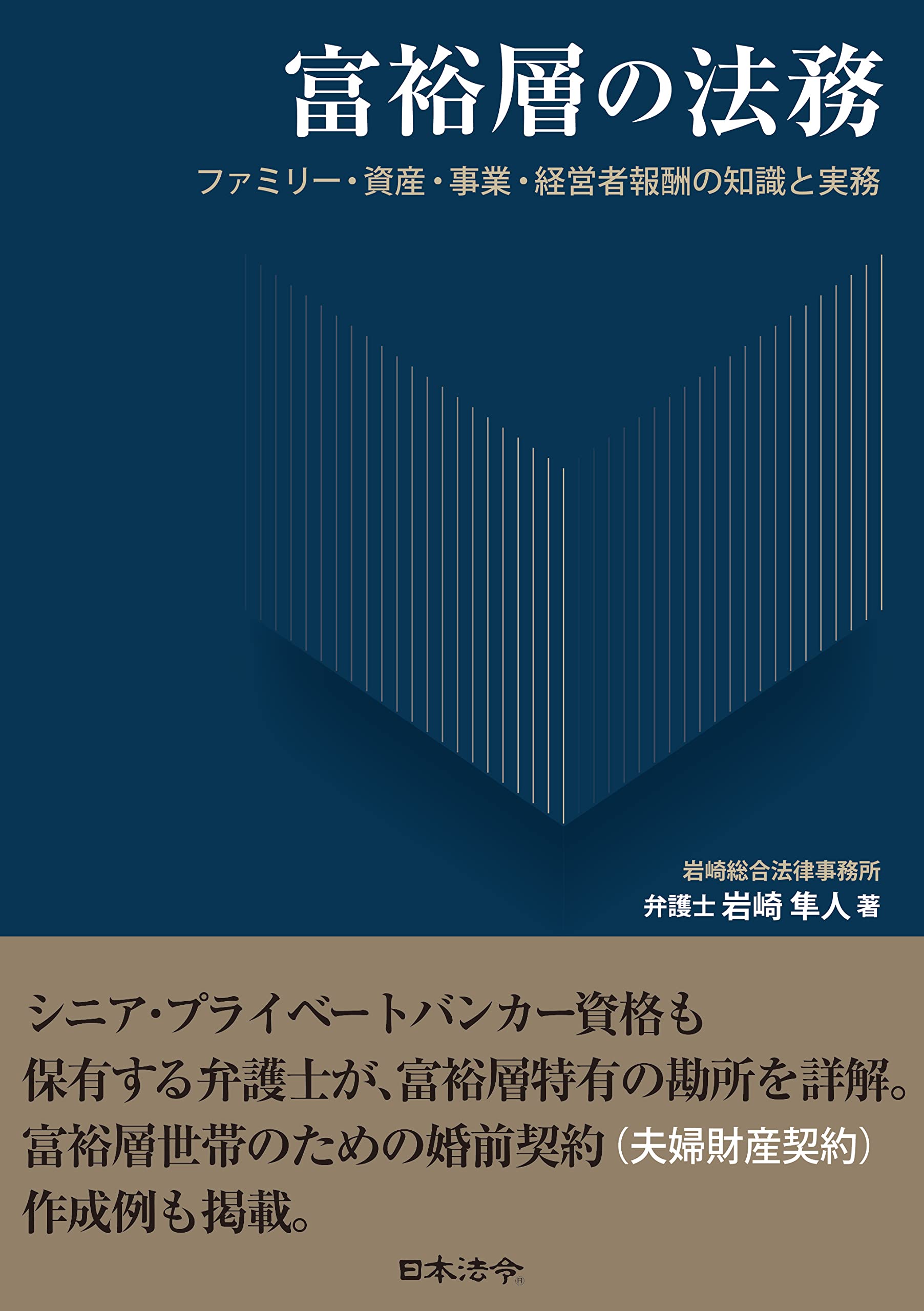2025年5月23日(金曜日)
専業主婦の離婚:正しい財産分与と生活の守り方
専業主婦(専業主夫を含みます。以下、このコラムにおいて同様です。)の方の多くは、離婚に対して様々な不安を抱えておられるかと思います。
・配偶者から経済的に自立できるかどうかへの不安
・財産分与の仕組みが分からないことに対する不安
・離婚後も子どもや自身の生活を維持できるかという不安
・離婚後に相続権が失われることへの不安
ここでは、財産分与にあたっての基本知識と、専業主婦の方の離婚後の生活設計の重要性を分かりやすく解説します。
離婚にあたってどのような行動を取れば良いかが明確になり、少しでも離婚に対する不安が解消されることを願っています。
岩崎総合法律事務所にご相談ください
岩崎総合法律事務所では、一般的な離婚事件のほか、資産家、経営者、投資家、高額所得者などの「富裕層」と呼ばれるお客様に対する法務サービス Legal Prime®を提供する中で、財産分与案件のノウハウ、経験が蓄積されてまいりました。
離婚についてお悩みの専業主婦の方は、当事務所までご相談ください。
弊事務所では、富裕層法務サービス Legal Prime® を通じ、資産家、投資家、会社経営者などの資産・収入の多いお客様に対し多様なサポートを提供してまいりました。
これにより得られた知見の一部を書籍化し発売中です。ご興味をお持ちいただけましたら、書影をクリックして詳細をご確認ください。
目次
-
【財産分与の基本と、専業主婦の場合に重要となるポイント】
- そもそも財産分与とはどのような手続きでしょうか。
- 専業主婦の場合、財産分与の割合はどのように判断されますか。
- 配偶者の財産に関する情報はどのように取得すればいいでしょうか。
- 離婚条件にて、離婚後の生活を考慮してもらうことは可能でしょうか。
- 離婚問題が決着するまで の生活に不安がありますがどうしたら良いですか。
- 強制執行についてはどのように備えておけばいいでしょうか。
- 幼い子どもがいます。離婚にあたって注意すべき点はありますか。
- 離婚後の生活も検討した上で、どのように離婚の交渉を進めればいいでしょうか。
【離婚後の自分と子どもたちの生活を守るためのポイント】
(1)当面の生活を守ることの重要性
(2)紛争期間中の生活環境を確保する方法
(3)専門家によるサポートの重要性
【小さな子どもがいる場合の進め方】
【交渉の落とし所】

1 財産分与の基本と、専業主婦の場合に重要となるポイント
Q1 そもそも財産分与とはどのような手続きでしょうか。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産(共有財産といいます。)を離婚時に分け合う手続です。財産分与は、共有財産を公平に分配することを目的としています。
専業主婦の方にとって財産分与は、離婚にあたって最も重要な手続の一つです。なぜなら、財産分与は、専業主婦の方が婚姻期間中に家族のために行っていた家事労働の価値が法的に評価される場であるためです。
財産分与では、共有財産が分与の対象となり、婚姻前から保有している財産などは財産分与の対象となりません(このような財産分与の対象とならない財産を特有財産といいます)。共有財産の具体例としては、婚姻後に売買等により取得した不動産、預貯金、年金、投資資産などです。特有財産の具体例としては、前記の婚前財産のほか、相続財産、贈与により取得した財産などがあります。
富裕層世帯の特殊性として、ストック・オプション、RSU、暗号資産、絵画、航空機など一般的な家庭では見られない特殊な共有財産を保有しているケースがみられます。実際に弊所でも、ストック・オプション、RSUなどといった特殊な財産の財産分与が争点となった事例を経験しています。
Q2 専業主婦の場合、財産分与の割合はどのように判断されますか。
共有財産を分与する割合は、原則として2分の1とされています(これを「2分の1ルール」といいます)。2分の1ルールはこれまでの裁判実務で確立した考え方でしたが、2024年5月に成立し2026年5月までに施行予定となっている改正民法ではこれが明記されました(改正民法768条3項後段)。
専業主婦の場合であったとしても、原則として財産分与の割合は2分の1とされます。配偶者が財産を築くことができたのは、専業主婦の方の家事労働に支えられていたことなどが考慮され、実務上このような考え方が採用されます。
ただし、特殊な資格・才能により莫大な資産を形成したといったような特殊な事情が存在する場合には、例外的に財産分与の割合に傾斜が掛けられることがあります(詳細については、こちらのコラムをご参照ください)。
財産分与の割合を決めるにあたっては、富裕層世帯の特殊性も考慮する必要があります。例えば、家事代行を活用している場合に論点があります。
前記のとおり、専業主婦の方の場合でも財産分与の割合が2分の1とされるのは、配偶者が築き上げた財産であっても、これは専業主婦の方の家事労働により支えられたためと考えているからです。
家事代行を活用している場合、専業主婦の方がすべての家事を負担していないとなると、専業主婦の方の財産分与の割合が下がる可能性もあります。もっとも、実務上、2分の1ルールは強力なルールであり、家事代行を活用していることのみをもってして、2分の1ルールに傾斜が掛けられる可能性は高くはないと思います。
Q3配偶者の財産に関する情報はどのように取得すればいいでしょうか。
適切な財産分与を実現するためには、双方がすべての財産を開示する必要があります。しかし、配偶者が、財産分与にあたって、一部の財産を開示せず隠匿するケースも見られます。
このような事態に備えて、事前に配偶者の財産に関する資料を収集しておくことが重要になります。
情報の収集方法としては、同居期間中の場合には、自宅にある配偶者の財産資料を確認するといった方法が考えられます。
また、弁護士による弁護士会照会、裁判手続が開始した後においては、調査嘱託や文書提出命令の申立て等といった手段を活用することが可能です。
弊所でも、同居期間中に財産資料を収集しておいたことが奏功し、配偶者が隠していた財産を明らかにすることに成功したり、配偶者が預金口座の残高を頑なに開示しないケースにおいて、調査嘱託を活用し残高を把握できたケースが存在します。
ただし、配偶者が保有している財産すべてに関する情報を収集することは困難です。そして、少しでも多く配偶者の財産を把握するためには、離婚協議前に資産状況を把握しておくことが重要です。
離婚手続に関係してくる財産としては、不動産、預貯金、株式、保険、国外資産、収入などが考えられます。
これらの財産それぞれをリストにまとめ、それぞれについて資料を準備しておきましょう。リストの作成にあたっては、裁判所のホームページで掲載されている婚姻関係財産一覧表を活用するとよいでしょう。
いずれにせよ早い段階で専門家の力を借りて調査を進めることが重要です。例え別居後であったとしても、お悩みの方は、お早めに弊所にご相談ください。
財産調査についての詳細はこちらのコラムでも詳しく解説しています。

2 離婚後の自分と子どもたちの生活を守るためのポイント
Q4 離婚条件にて、離婚後の生活を考慮してもらうことは可能でしょうか。
専業主婦となった経緯については、キャリアを犠牲にして家事専業になった場合や一度も就職したことがない場合など様々なケースがあります。中には、離婚後に就業することが難しいケースも見られます。
特に熟年離婚の場合には顕著です。なお、熟年離婚の場合には、離婚にあたって追加で特殊な論点が存在します。詳細はこちらのコラムをご参照ください。
このため、離婚後の生活設計を立てられるかどうかは大きな問題となります。
離婚にあたっては、離婚前に事前に自分で得られる見込みの収入や離婚後の必要資金(生活費、医療費、教育費、老後資金等)を丁寧に試算しておくことが重要です。それを例えば財産分与等の離婚条件にも反映させるように試みる必要があります。
ただし、配偶者の生活を保護する婚姻費用は離婚によって消滅してしまいますし、財産分与という法的仕組みそのものは、離婚後の扶養を中核にするものではないため、こうした試みを奏功させることは難しいのが一般的な考え方です。
しかし、熟年離婚の場合をはじめ離婚後扶養が必要とされるケースでは、扶養的財産分与やその他の形をとって認められる可能性があります。
また、離婚事件の多くは調停や和解等といった話し合いでの決着が期待され、その話し合いの中で先方の理解を得て合意まで至ることも少なくありません。
たとえ一般的には難しい場合でも、それが必要なことであればしっかり検討して、どうにか実現できないか試みるべきでしょう。
Q5 離婚問題が決着するまで の生活に不安がありますがどうしたら良いですか。
(1) 当面の生活を守ることの重要性
生活設計を行うにあたって、離婚後の生活を検討することも重要ですが、離婚にあたって最初に重要となるのは、配偶者に離婚を切り出してから離婚の手続が完了するまでの当面の生活資金でしょう。
この点、当事務所の経験上は、極めて例外的な場合(生活費の支払いを求める側が不倫をしていた等)を除いて、配偶者が生活費の一切を支払わないような事案には接していません。ただし、余裕がある生活を送れるほどの資金は受け取れず、切り詰めた生活を余儀なくされるケースもありますので、離婚に至るまでの生活についても、綿密に資金状況を計画しておくことが重要です。
もしも、配偶者から生活費を打ち切られる、こちらの資金が尽きることを見越した紛争の長期化といった兵糧攻めに遭ってしまった場合、足元がぐらついて、本来あるべき着地、解決にならないこともあります。足元の基盤を固めておくことは納得のいく解決を得るためにとても重要です。
婚姻期間中の生活費についての権利である婚姻費用分担請求権は、離婚協議中や別居期間中の生活費を確保するための重要な制度です(詳細はこちらのコラム①と②でも解説しています)。
婚姻費用分担請求権は法的な基準に沿って適切に権利行使しなければなりませんが、それが実現するのにも時間を要します(長いケースでは、裁判上の手続で婚姻費用の額が確定するために1年以上の期間を要することもあります )。
(2)紛争期間中の生活環境を確保する方法
そのため、長期間の紛争に耐えるために、婚姻費用だけではなく、より実践的な生活資金の準備、取り組みも必要です。婚姻費用以外の、紛争期間中の生活環境を確保する方法としては以下の方法が考えられます。
① 足元の資金を確保する
婚姻費用以外の資金から足元の資金を確保する方法としては例えば以下の方法があります。
・自身の特有財産(結婚前の預金など)を活用。
・親族からの一時的な借り入れを検討。
・自治体や福祉制度の短期援助等を活用。
上記の方法のほか、どうしても確保できない場合は別居にあたって配偶者の特有財産や夫婦共有財産を持ち出す方法も考えられますが、リスクが伴います。一部の裁判例では、別居時に名義上配偶者の財産や夫婦共有財産を一定範囲で持ち出すことが合法として認められたケースもありますが、あらゆるケースで合法と認められるわけではないため、状況に応じて慎重に判断して対応する必要があります。
② 生活環境を確保する
まず、自宅を出て行かないということが考えられます。自宅以外に居宅を構えようと思えば賃料の負担を始め出費が生じてしまうこともあるからです。
一度自宅を出てしまった後、無理に入ろうとすれば違法行為となってしまう可能性があります。自宅を出るにあたっては初動から慎重な判断が必要です。
③ 教育費を確保する
近年高額になりがちな教育費は、ひとり親の家庭がもらえる手当てや貸付金、奨学金、学生ローン、その他学校などへの事前相談といった備えを検討しておくことも重要です。教育費の備えについての詳細はこちらのコラムで解説しています。
(3) 専門家によるサポートの重要性
いざ離婚しよう、と思ったときどう進めるのか迷われる方も多いと思います。別居を先行させた方が良いのか、初めから代理人付けた方が良いのか、相手にどんな切り口で臨めばよいといった疑問・心配は次々に湧いてきます。
これらは単なる不安にとどまらず、その後の離婚条件交渉や関係性にも影響することがあります。
適切に進めるには、計画的な準備が必要であり、その過程で都度都度専門家の力を借りることが、確実な解決につながります。
一人で抱え込まず、まずは専門家に相談することで、より明確な未来を描く第一歩を踏み出しましょう。
Q6 強制執行についてはどのように備えておけばいいでしょうか。
離婚時に財産分与や養育費の取り決めを行なっていたとしても、配偶者がこの取り決めに従わない可能性もあります。このような場合には、預貯金や不動産等の財産の差押え、給与債権の差押えなどの「強制執行」により、相手方に義務の履行を強制させる必要があります。
このような強制執行を見据える場合、強制執行認諾約款付の「公正証書」や、裁判手続を通じて「調停調書」、「審判書」、「判決書」などの債務名義を取得しておくことが望まれます。
私製の「離婚協議書」「契約書」「合意書」「覚書」などでは直ちに強制執行ができず、別途裁判手続が必要となってしまいます(なお、2024年5月に成立し2026年5月までに施行予定となっている改正民法では、養育費債権のうち一定の範囲について先取特権が付与されることになり、その限度では債務名義がなくても強制執行ができる余地が生まれました。しかし、あくまでも法施行後に生じた養育費のうち法務省令で定める一定の範囲について認められるものにすぎませんので、その範囲を超える養育費や、養育費以外の財産分与等の債権について債務名義が必要なことに変わりはありません)。
離婚条件に大きな争いがなく協議離婚での決着をお考えの場合であっても、将来の強制執行の可能性を見据え、公正証書を作成したり、離婚調停の手続を経ておくことが望ましいケースもあります。

3 小さな子どもがいる場合の進め方
Q7 幼い子どもがいます。離婚にあたって注意すべき点はありますか。
離婚後も両親ともに親子関係は続いていくことになります。
そのため、ご家庭ごとに抱える事情は様々だと思いますが、可能なのであれば関係性を破壊することなく、なるべく円満な方法で進めていくのが望ましいところです。
離婚を子どもにどう伝えるかも重要です 。例えば、子どもの年齢も重要な考慮要素でしょう。幼児、小学生、思春期の子どもの場合、離婚の事実を受け入れられず、教育上の支障が生じてしまうこともあります。少なくとも、幼児期や小学生の頃に伝えることはなるべく避けたり、子どもが多感となっている時期に伝えないようにする工夫が必要です。
また、離婚後にも、非監護親が子どもと十分に交流を得られる機会を設けることも子どもの発育上重要です。
当事者同士で面会交流を進めることに不安がある場合には、面会交流を推進するための民間の機関を活用することも有益でしょう。
4 交渉の落とし所
Q8 離婚後の生活も検討した上で、どのように離婚の交渉を進めればいいでしょうか。
当事務所ではケースに応じた柔軟なサポートを行なっています。
離婚条件の交渉にあたっては、例えば、裁判基準以上の金額を求める場合や、一方で裁判基準以下の金額で合意する場合が考えられます。
前者のケースは離婚後の生活水準維持や必要資金確保のため、裁判基準を超える条件で合意する場合です。
結婚生活の背景や子どもとの関係なども考慮し、説得的な主張を行った結果、法的権利以上の内容での交渉が成立することがあります。
実例として、妻の生活支援として、裁判基準を超える月額60万円の生活費相当額の支払いや住居提供の約束を得た事例があります。
ただし、高額な条件の場合には、贈与税のリスクが発生する可能性があるため、税務対策を含めた検討が必要になる点注意が必要です(税務の影響の詳細はこちらのコラムで解説しています。)。
後者の低い条件で合意するケースはやや特殊です。例えば、早期解決や配偶者との良好な関係維持を優先する場合に、あえて裁判基準以下の条件での合意を選択する場合があります。
当事務所では、ご依頼者の希望や状況、必要性を尊重しつつ、離婚条件の交渉にあたっては必ずしも裁判基準にとらわれ過ぎずに、法的・税務リスクを十分に検討した上でサポートすることに努めています。
離婚条件の交渉や解決事例についてはこちらのコラムをご参照ください。
以上、専業主婦の方が離婚で直面する財産分与問題について解説してきました。
財産分与対策はなるべく早期に実施することが重要です。
現時点では離婚問題が顕在化していない場合でも、現在の状況を確認しておくことは有益といえます。
離婚問題でお悩みの方は、初回のご相談は30分間無料※ですのでお早めに当事務所までご相談ください。
※ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。