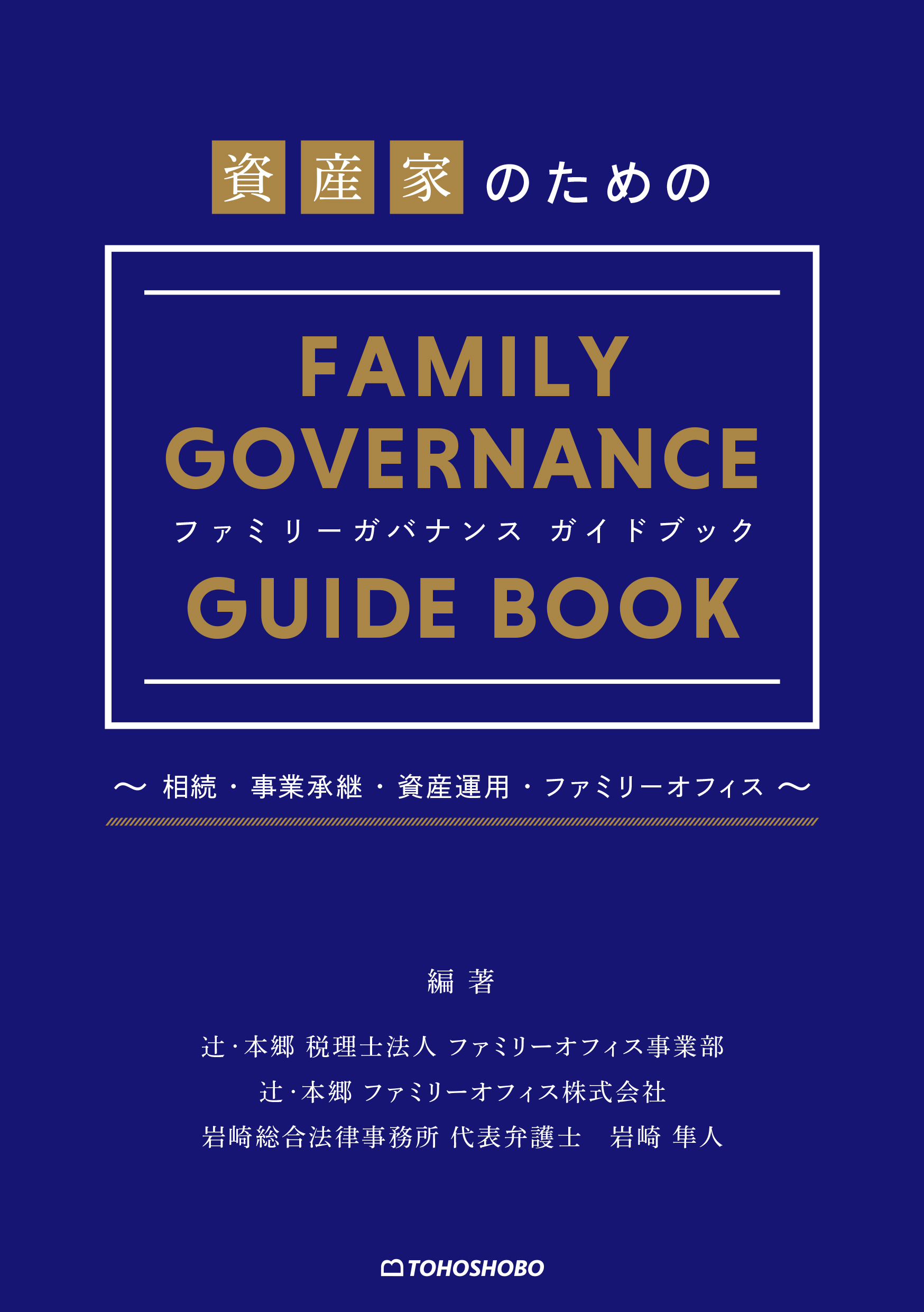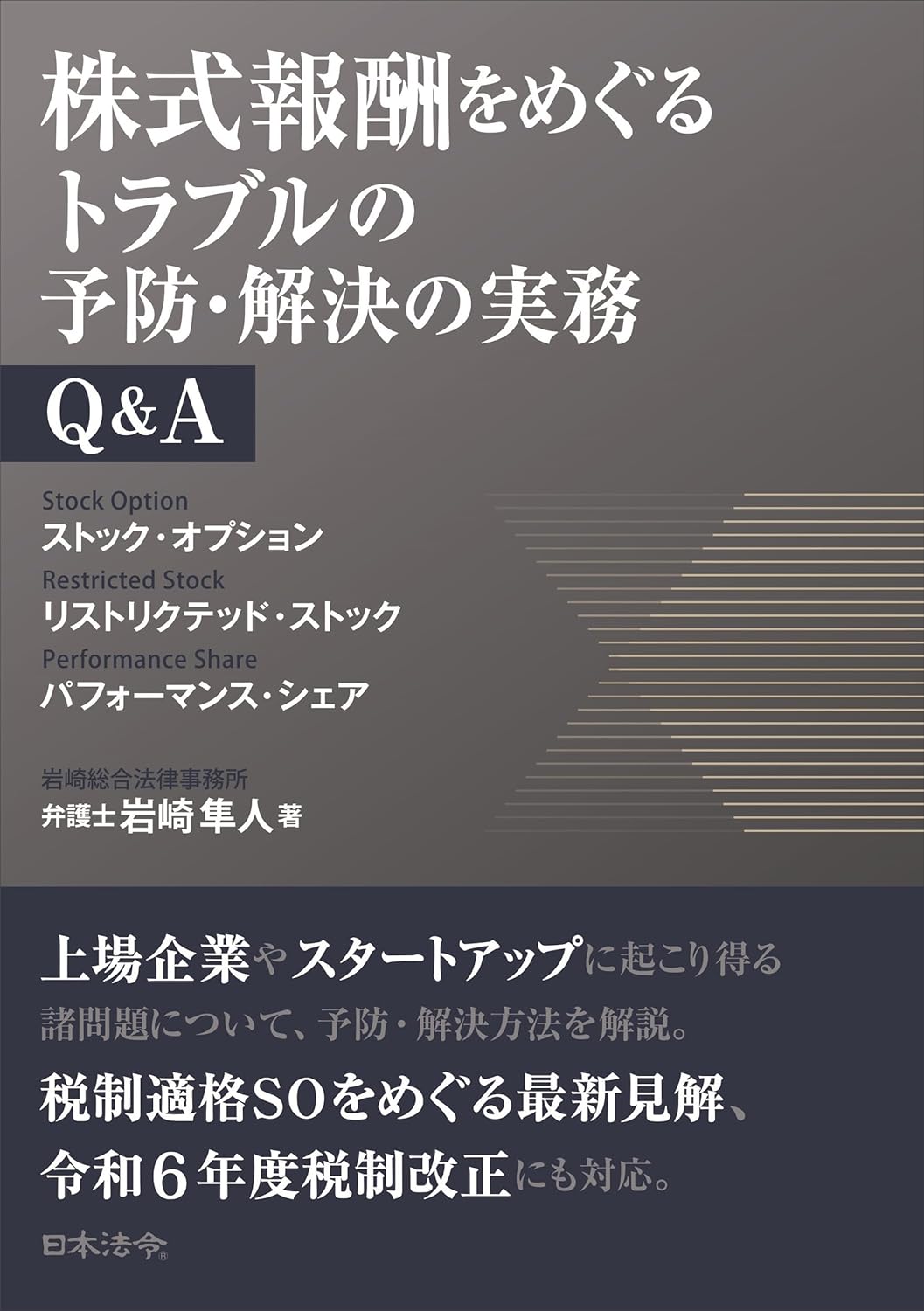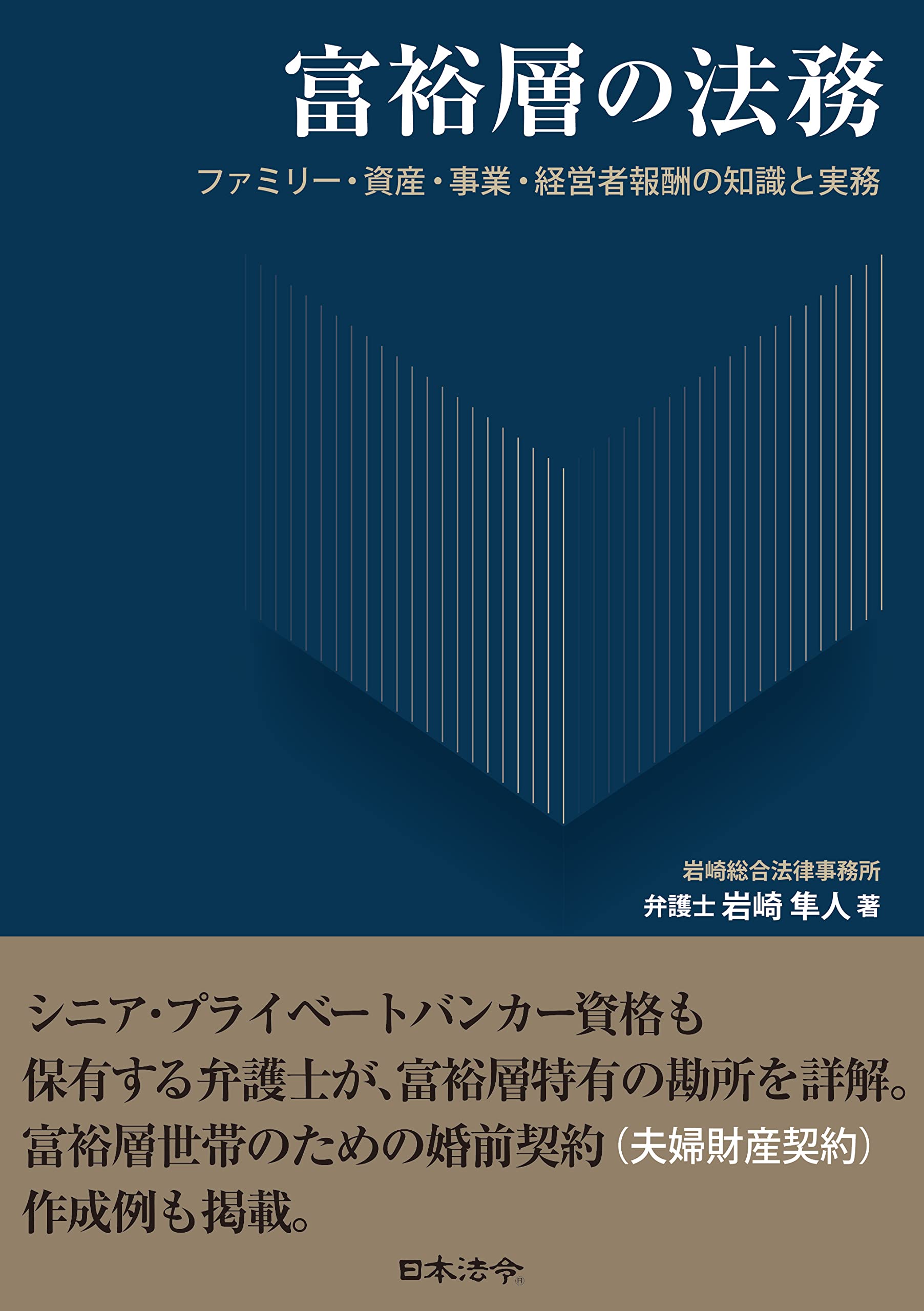2023年3月21日(火曜日)
経営者世帯の「特別受益」の問題 ~ 遺留分関連の問題 ~
経営者の相続においては、「遺留分」を巡る問題が高確率で発生します。
そこでは「特別受益」を巡る論点がよく問題となります。
以下では、遺留分を巡る「特別受益」の問題について、特に経営者世帯の相続に特有のポイントを、Q&A形式で解説いたします。
岩崎総合法律事務所では、経営者、高額所得者などのお客様に対する法務サービス Legal Prime® を通して、相続紛争案件のノウハウや経験を蓄積してまいりました。経営者の相続紛争の問題について、お客様にとって最善の解決となるようにサポートしています。
相続問題についてお悩みの方は、当事務所までお問い合わせくださいませ。
当事務所では、生前に資産承継計画を検討される際の助言や設計もサポートしています。遺留分対策を含む生前の資産承継計画についてご関心をお持ちの方も是非ご相談ください。
弊事務所では、富裕層法務サービス Legal Prime® を通じ、資産家、投資家、会社経営者などの資産・収入の多いお客様に対し多様なサポートを提供してまいりました。
これにより得られた知見の一部を書籍化し発売中です。ご興味をお持ちいただけましたら、書影をクリックして詳細をご確認ください。
目次
- Q1 経営者世帯の相続では、「特別受益」はどのようにして問題になりますか
- Q2 特別受益に該当するかについて、よく論点となるものはどのようなものですか
- Q3 生命保険金は、どのような場合に特別受益になりますか
- Q4 死亡退職金は、特別受益になりますか
- Q5 「資産管理会社」の株式が相続税対策のために用いられていました。特別受益に関してはどのような問題がありますか
- Q6 特別受益の「内容」はどのように考えればいいのでしょうか。例えば不動産購入資金の贈与では、その「資金」でしょうか、「不動産」そのものでしょうか
- Q7 遺産の評価がよく問題になるとのことですが、「特別受益の評価」は、どのような点に注意すればよいのでしょうか
- Q8 生前贈与分の算入には期間制限があるとのことですが、例外はないのでしょうか。どのようなときに例外は認められるのか、経営者世帯の相続の場合の注意点はどのようなものでしょうか
Q1 経営者世帯の相続では、「特別受益」はどのようにして問題になりますか
特定の相続人が、被相続人から、婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与や、遺贈を受けた際の利益のことを「特別受益」と言います。
特別受益分は遺留分算定の基礎となる財産に加算します。
生前贈与については一切の贈与財産が加算されるものではなく、生前贈与が生計の資本としての贈与か、相続財産の前渡しとみられる贈与であるかを基準として判断されます。
居住用の不動産の贈与又はその取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与、借地権の贈与などは生計の基礎として役立つような財産上の給付となり、多くの場合において特別受益となります。
特に経営者世帯の場合には、相続税対策等のために生前に多くの資産を移転している場合も多く、注意が必要です。
また、事業を営む場合、その事業を後継者に承継させるために生前に遺留分問題について対策しようとしている場合も多いですが、その手法の一つとして生前の資産移転等が行われることも、経営者世帯の相続紛争にみられる特徴です。
なお、遺留分侵害の場面では、遺留分制度の趣旨から特別受益の持戻免除の余地はありません(一方、具体的相続分の計算の場面では持戻免除は容易に認められます)。
Q2 特別受益に該当するかについて、よく論点となるものはどのようなものですか

特別受益かどうかが論点となるものもあります。
例えば、被相続人の所有する土地・建物を無償であるいは相当の対価を払わずに利用している場合です。
それが土地か建物か、相続人に独立の占有権があるかないか等によって、賃料相当額等が特別受益と評価される場合があります。
また、ボーディングスクールの費用・留学費用や私立の医科の学費のように特別に多額なものなどは、扶養義務の履行に基づく支出の範囲を超えるものとして、特別受益に相当すると評価される場合があります。
世帯の収入・資産の状況、他の子の就学状況、配偶者の就学に対する姿勢・理解などによって結論は異なります。
また、被相続人が生前に行う遺留分の対策として、生命保険や死亡退職金が活用されている場合もあります。
こうした生命保険や死亡退職金は特別受益性を巡ってよく論点となります。
Q3 生命保険金は、どのような場合に特別受益になりますか
遺言者を契約者とし、後継者を保険金受取人とする生命保険契約を締結すると、遺言者の死亡に起因して後継者は生命保険金を取得することになります。
この生命保険金は、保険会社と遺言者との第三者のためにする契約により取得したものであるため、相続で取得したことにはなりません。
そのため、生命保険金は、遺留分の算定における特別受益とされず、結果的に生命保険を利用しなかった場合と比較して後継者以外の推定相続人の遺留分が縮減します。
しかし、生命保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前に支払ったものです。保険金受取人である相続人に保険金請求権が生じるのは、被相続人の死亡に由来するものでもあります。
こうしたことから、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となります。
特段の事情は、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきとされます。
裁判例を保険金額が遺産総額に占める割合に着目して整理すると、ほぼ100%相当分に及ぶ場合や、61%に及ぶ場合には、持戻しの対象になるとした例があります。
一方、約10%の場合、約9%の場合、約6%の場合では、持戻しを否定した例もあります。
持戻しの対象になる範囲については確たる見解はありませんが、保険金全額を加算するものが多いとされています。
Q4 死亡退職金は、特別受益になりますか
被相続人が生前に行う遺留分の対策として、死亡退職金が活用されている場合もあります。
これが、特別受益に該当するか問題となりますが、実務上は特別受益とならないことでほぼ固まっています。
死亡退職金に関する給付規程において、死亡退職金の受給権者が特定している場合には受給権者の範囲・順位が相続法の規律と無関係に定められているため、死亡退職金の受給は受給権者の固有の権利に基づくものである、という考え方によるものです。
もっとも、これは一方で、規程の内容が「相続人」に支給するという内容である場合には相続財産と解釈される可能性があることを意味します。
したがって、死亡退職金の相続財産性すなわち遺留分算定基礎財産に含まれるかどうかについては、念のため個別事情を検討しなければなりません。
ただし、仮に遺留分算定基礎財産に含まれないことが原則だとしても、生命保険金と同様の解決をすべき場合があるという見解もあります。
すなわち、受給権者である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし是認することができないほど著しいものと評価すべき特段の事情がある場合には、遺留分算定基礎財産に含めて計算すべきというものです。
死亡退職金が遺留分との関係でどのように取り扱われるかの解釈は必ずしも確定的なものはなく、個別事情によってその扱いが変わります。
Q5 「資産管理会社」の株式が相続税対策のために用いられていました。特別受益に関してはどのような問題がありますか

経営者世帯の場合には、相続税対策で資産管理会社を保有し、この株主を子などにしている場合があります。
時には、子ひとりごとに一つの資産管理会社を用意している場合もあります。
このとき、資産管理会社の株式は子の保有下に置かれていますので、それ自体は相続財産にはなりません。
しかし、子がその株式を、(通常はそれなりの大きな額となっている)相続時点の評価額をもった資産として保有できるようになった経緯を捉えて、特別受益性が論点になる場合があります。
この論点は金額も大きく、事件の進行にも大きな影響を与えます。
通常のケースでは特別受益性は肯定されるものと思います。
ただし、遺留分侵害額請求の場面においては、特別受益の持戻しに後記のとおり期間制限があるところ、資産管理会社を用いた相続税対策は相当の長期間をかけて行うことが通常であることなどから問題が顕在化しない場合もありえます。
Q6 特別受益の「内容」はどのように考えればいいのでしょうか。例えば不動産購入資金の贈与では、その「資金」でしょうか、「不動産」そのものでしょうか
特別受益の「内容」をどのようにとらえるかについても注意が必要です。
例えば被相続人から不動産購入資金として、不動産購入に必要となる一切の金銭の贈与を受けた、という事例がよくみられます。
この事例のように、贈与の内容は形式的には金銭であるが、実質的には特定の資産である場合があります。
当然この贈与は特別受益ですが、その内容は金銭でしょうか、それとも不動産でしょうか。
特別受益を評価する基準時は生前贈与時ではなく相続開始時となります。
このため、その間のその資産の価値変動や貨幣価値の変動によっては、贈与の内容を金銭とみるかその特定の資産とみるかで、考慮する金額に大きな差が出ることがあります。
このように、特別受益の内容をどのようにとらえるか、ということも問題となります。
実際に、特別受益の内容がどのように判断されるかは、贈与したそのもの資産がどのようなものか及び贈与の目的・趣旨を中心に、相続人間の公平性も考慮して事案ごとに判断されます。
Q7 遺産の評価がよく問題になるとのことですが、「特別受益の評価」は、どのような点に注意すればよいのでしょうか

「特別受益の評価」をめぐっては、仮に生前に再処分されて相続開始時に存在してなくても相続開始時において評価しなければなりません。
これによって争いになることもあります。
例えば受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価額の増減があったときであっても、相続開始時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定めなければなりません(民法1044条2項、904条)。
こうした既に消滅した財産については、それが上場株式など相続開始時点でも存在し時価のあるものについては大きな問題にはなりにくいものですが、特に非上場株式の場合にはその評価は困難であり、当事者双方での見解が衝突しやすくなります。
また、贈与の性質が負担付贈与であった場合には、その目的の価額から負担の価額を控除した額とされます(民法1045条1項)。
この負担が金銭的な負担でない場合には、いくらで評価すべきか問題となります。
売買のような有償行為であったとしても、それが不相当な対価をもってしたものであり、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについては、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされ、遺留分算定の基礎となる財産額に含まれます(民法1045条2項)。
こうした場合には負担付売買と同様の論点を抱えます。
※ 遺産の評価について、それぞれ以下の解説をご参照ください。
「不動産」の評価の詳細はこちら
「非上場株式」の評価の詳細はこちら
「債権」・「動産」の評価の詳細はこちら
Q8 生前贈与分の算入には期間制限があるとのことですが、例外はないのでしょうか。どのようなときに例外は認められるのか、経営者世帯の相続の場合の注意点はどのようなものでしょうか

遺留分侵害の論点における特別受益分の加算には、期間制限があります。
具体的には、相続人に対する特別受益は相続開始前10年間です。
このように期間制限があるのですが、
このため死亡時が例えば80歳であった場合等には、こうした期間制限は遺留分侵害を請求する側にとって大きなハードルとなります。
しかし、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与である場合には、期間制限なくすべて基礎財産となります。
経営者世帯の遺留分の問題において、「遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与」の要件は相当にハードルの高いものであり、この要件を満たすことは容易ではありません。
しかし、相続時精算課税制度を利用する目的などで、一気に自社株を生前贈与するといったような場合にはこの要件を満たしうるものです。
なお、「損害を加えることを知って」とは、損害を与えるという加害の意図や誰が遺留分権利者であるかを知っている必要はありません。
遺留分権利者に損害を加えるべき事実を知っていることで足ります。この認識は被相続人・相続人両名に必要となります。
こうした認識はその時点だけを切り取って検討するものではなく、あくまで相続開始時点の状況がどのようなものかの見通しをもとにした認識が問題になります。
つまり贈与時点で株価が暴落しており遺留分侵害とならないような場合でも、それが明確に一時的であり相続開始時までに回復する見込みであって、それを当事者が認識していた場合にはやはり侵害認識あり、ということになります。
「損害を加えることを知って」というところの、この「損害」は遺留分割合を割り込むことを意味しますが、それは相続人の構成に拠って異なります。
以下のとおり直系尊属のみが相続人である場合は3分の1となりますが、それ以外の場合、例えば相続人のパターンとして最も多いと思われる配偶者や子が相続人になるときは、2分の1となります。
このように一定の割合を割り込むような贈与は「損害を加えることを知って」に該当する可能性があります。
①相続人が配偶者及び子→被相続人の財産の2分の1
②相続人が子のみ→被相続人の財産の2分の1
③相続人が配偶者のみ→被相続人の財産の2分の1
④相続人が配偶者及び直系尊属→被相続人の財産の2分の1
⑤相続人が直系尊属のみ→被相続人の財産の3分の1

以上の論点について正当な結果を求めるためには、事実関係及び法律関係を整理して、適切な分析に基づいた方針のもと、正確に主張立証していくことが重要です。
もし、相続問題、遺留分の問題を巡ってお悩みの方は、初回のご相談は30分間無料※ですので、少しでもお困りの際にはお気軽にご相談ください。
※ ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。