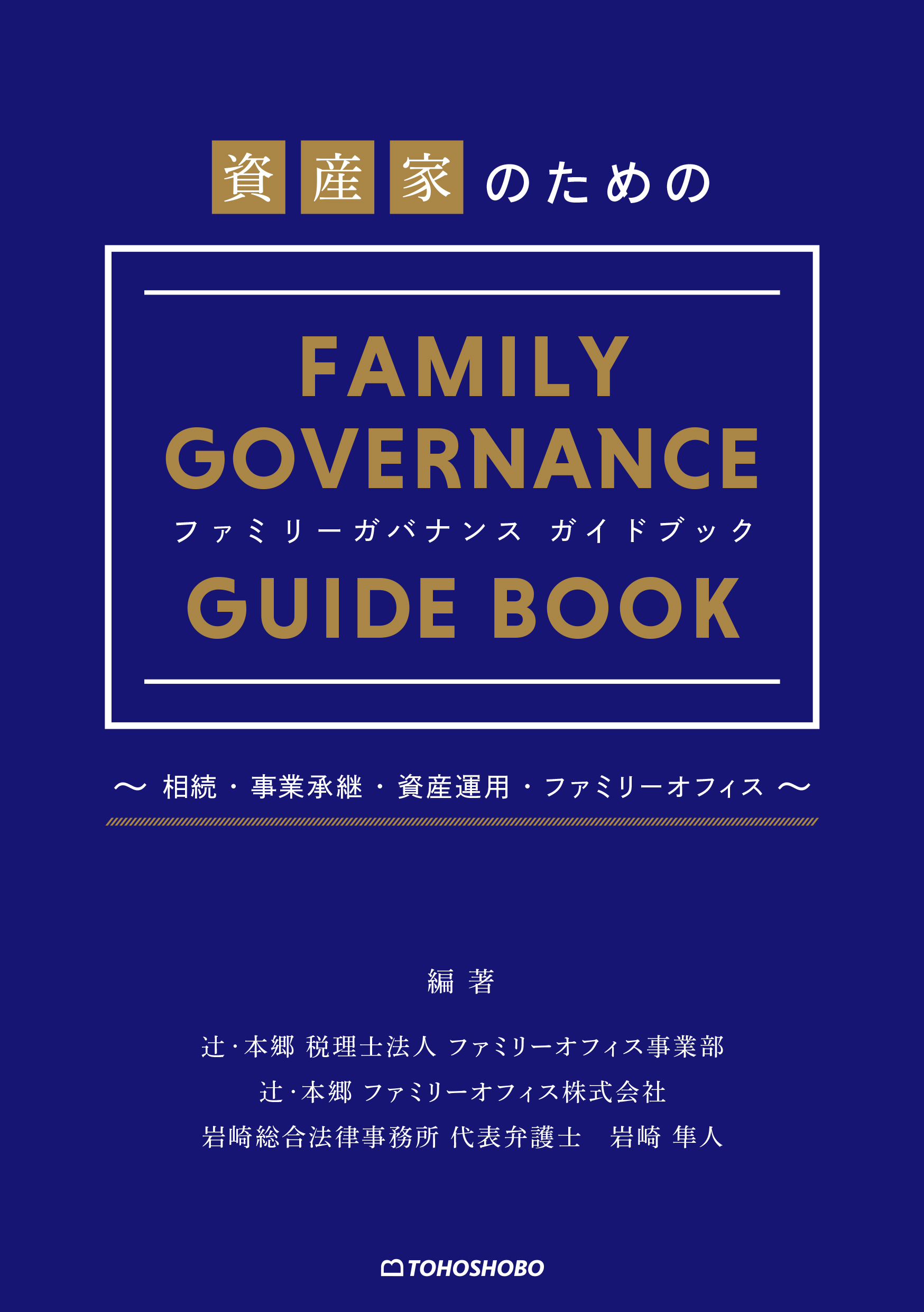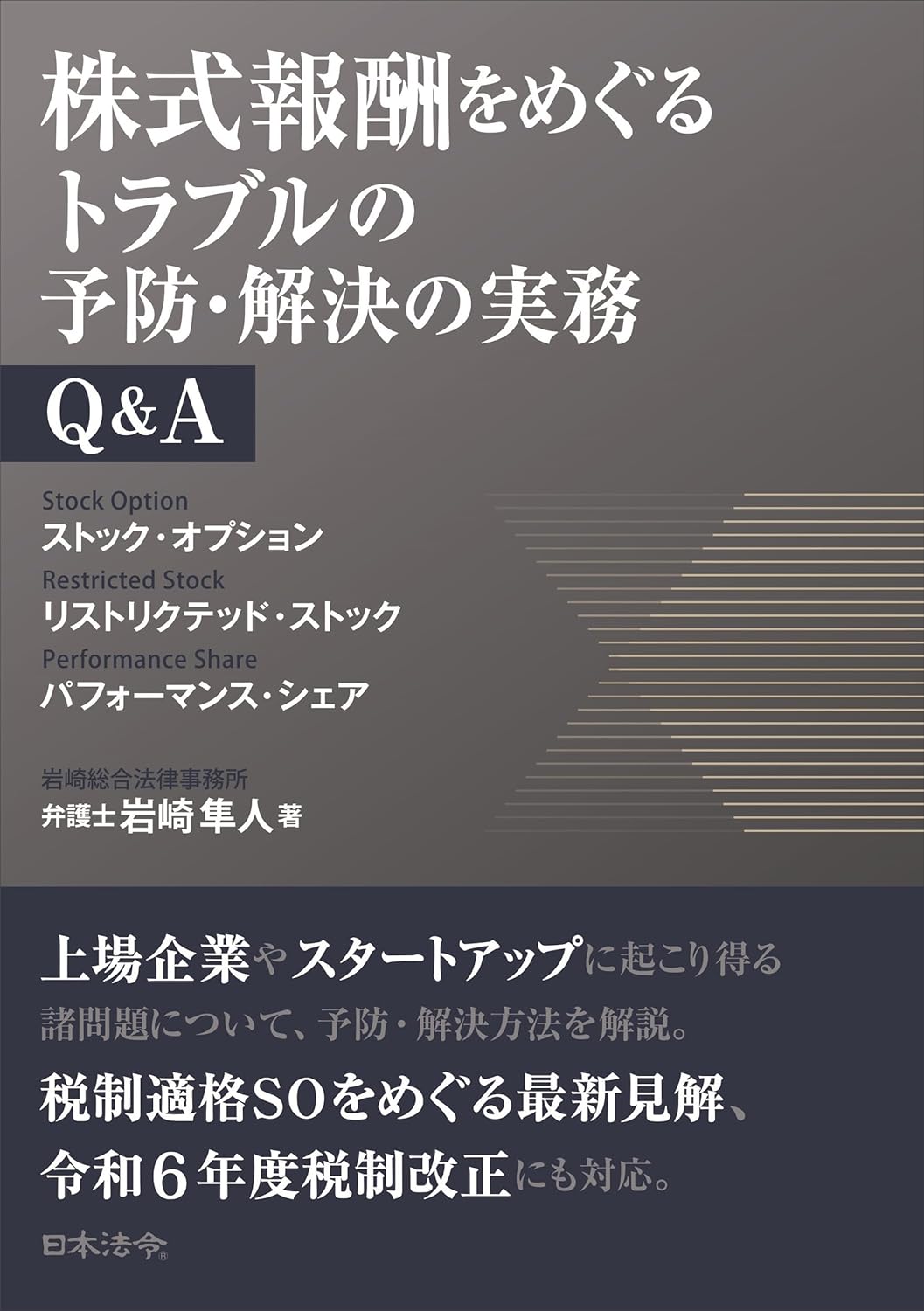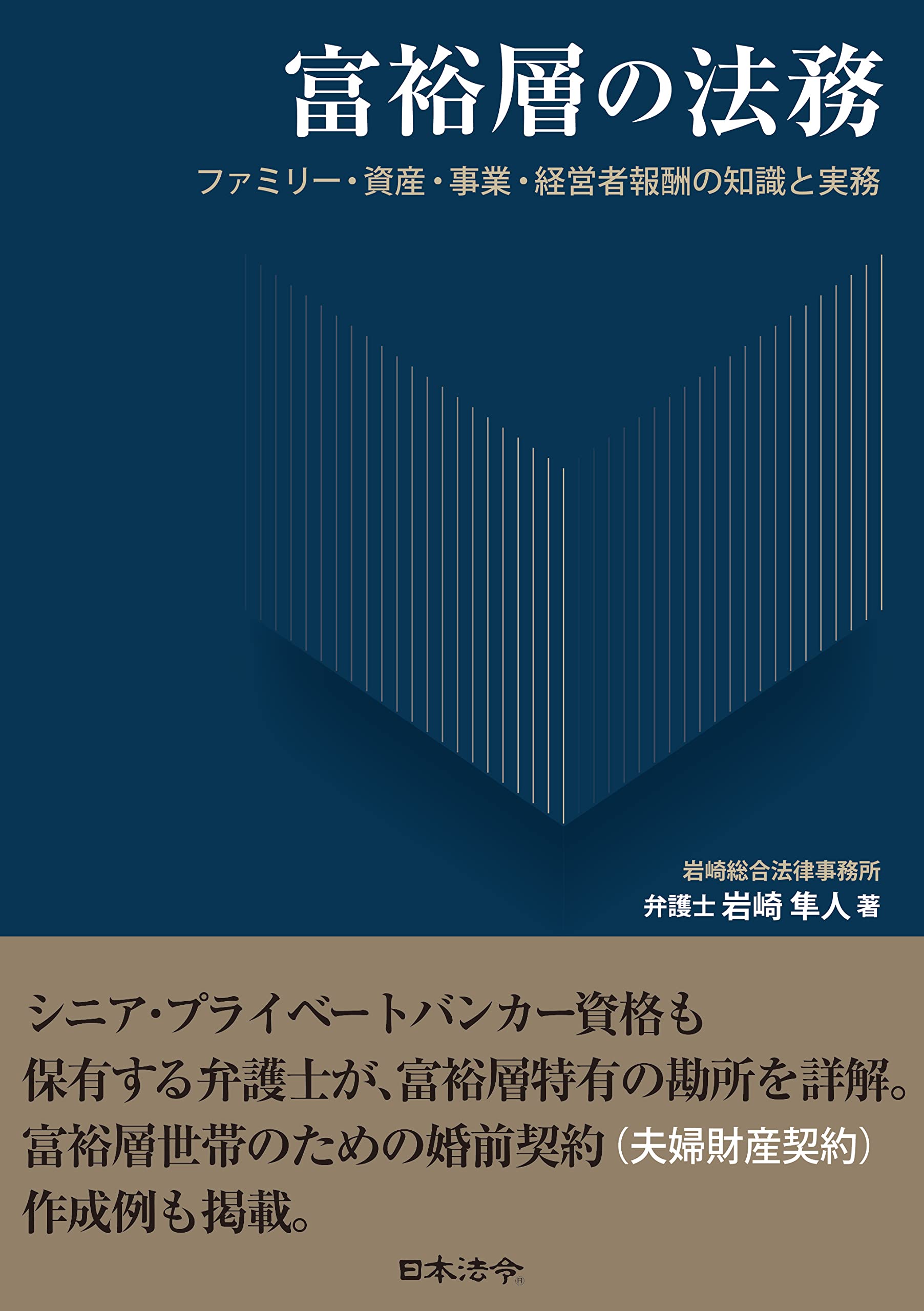2025年10月30日(木曜日)
獣医師の離婚 ~婚姻費用・養育費・財産分与のポイント~
獣医師として働く配偶者と離婚する場合、婚姻費用・養育費・財産分与に特徴はあるのか。
今回はそのような疑問について解説します。
岩崎総合法律事務所にご相談ください
岩崎総合法律事務所では、一般的な離婚事件のほか、資産家、経営者、投資家、高額所得者などの「富裕層」と呼ばれるお客様に対する法務サービス Legal Prime®を提供する中で、財産分与案件のノウハウ、経験が蓄積されてまいりました。
離婚についてお悩みの獣医師世帯の方は、当事務所までご相談ください。
弊事務所では、富裕層法務サービス Legal Prime® を通じ、資産家、投資家、会社経営者などの資産・収入の多いお客様に対し多様なサポートを提供してまいりました。
これにより得られた知見の一部を書籍化し発売中です。ご興味をお持ちいただけましたら、書影をクリックして詳細をご確認ください。
Question
獣医師の配偶者との離婚を考えています。別居中の生活費(婚姻費用)や養育費、財産分与について、獣医師世帯特有の注意点を教えてください。

Answer
はじめに
獣医師は、人間を相手とする医師と同様に一般的に高収入といわれています。そのため、一般的な会社員とは異なり、高収入世帯特有の問題が出てきます。
また、獣医師とひとくちにいっても、国・自治体・企業等で働く勤務医のほか、動物病院などの動物診療施設を経営する開業医がいます。開業形態は個人事業である場合が多いですが、法人を経営している場合もあり、形態は様々です。
そこで、婚姻費用や養育費については、そうした勤務医・開業医の区別から、獣医師の収入をどのように見るか、特に経費が適切に計上されているかどうかが問題となります。
財産分与については、個人名義の事業用財産や法人名義の財産が財産分与の対象となるか、法人経営の場合の株式や持分の評価、財産分与の割合(2分の1ずつ分け合うのか)が特に問題となります。
なお、統計(令和6年賃金構造基本統計調査)によると、勤務獣医師の平均年収は、約885万円とされています。開業獣医師については、公的な統計はないものの、開業5年後の年収は1000万円から2000万円となるケースが多く、なかには5000万円を超えるケースもあるといわれています。

婚姻費用・養育費について
婚姻費用とは、婚姻した夫婦が共同生活を営む上で必要な一切の費用をいいます。具体的には、衣食住に関わる費用、子の監護にかかる費用、医療費等が挙げられます。
仮に別居中であったとしても、離婚が成立するまでの間は、互いに婚姻費用を負担しなければなりません。
養育費とは、離婚後に生じる子の監護にかかる費用をいいます。
算定方法
婚姻費用や養育費の金額は、原則として、夫婦双方の年収をもとに、裁判所が公表している算定表に基づいて算定されます。
算定表に記載されている収入を超える場合は、算定表で用いられている計算式により金額を算定する場合もありますが、従前実際に掛かっていた生活費から算定するといった方式がとられることもあります。
獣医師特有の注意点(押さえておくべきポイント)
個人事業主である獣医師の場合、確定申告書において、総収入に比して高額な経費が計上されている場合があります。ただし、経費が高額であったとしても、婚姻費用算定の際に、高額な経費が直ちに収入に加算されるわけではありません。
もっとも、所得税を抑えたいがために、経費を過剰に計上しているような場合には、過剰な経費部分を収入に加算することが認められる場合があります。
法人経営をしている獣医師(法人役員)の場合、生活費を経費として計上し、役員報酬を低額に設定しているような場合があります。この場合、経費として計上している生活費部分を役員報酬に上乗せできるかという問題が生じます。
しかし、どの範囲が役員個人の生活費であるのか立証が困難である場合が多いため、経費を収入に加算するためのハードルは、個人事業主の場合と比べてより高いといえます。
配偶者が所得隠し(所得操作)をしていると疑われる場合の対応については、こちらのコラムもご参照ください。

財産分与について
財産分与の割合については、原則として「2分の1ルール」が適用されます。
財産分与の基本については、こちらのコラムもご参照ください。
個人事業主(開業医)の場合の注意点(押さえておくべきポイント)
獣医師業により稼いだお金は、個人資産でありながら、事業用資産でもあります。
もっとも、その資産を形成できたのは、配偶者の貢献があったからこそとも考えられるため、通常は財産分与の対象となるものと思われます。
医療機器等の備品や設備についても同様に、獣医師業により稼いだお金によって、備品の購入や設備投資を行うことから、財産分与の対象となると考えられます。
一方、債務(借り入れ)などの消極財産は、原則として、財産分与の対象となりません。したがって、事業のための借り入れも財産分与の対象とならないのが原則です。
しかし、事業用資産は財産分与の対象とするにもかかわらず、事業用資産を取得するための借り入れが財産分与の対象とならないのは不公平です。
そのため、こうした場合には、公平性の観点から事業のための借り入れも財産分与の対象とされうるでしょう。
法人経営(開業医)の場合の注意点(押さえておくべきポイント)
獣医師の法人は、人を相手とする医療法人のように法人形態に制限はありません。そのため、獣医師が法人を設立する場合には、株式会社や合同会社といった形態がとられます。
婚姻後に設立したり、婚姻後に株式や持分を取得した場合には、それらの株式や持分は、財産分与の対象となります。
一方、こうした法人がその法人名義で保有する財産は、原則として財産分与の対象とはなりません。財産分与は、夫婦の共有財産を清算するものだからです。
ただし、法人であっても、その実態が個人経営の域を出ておらず、実質的に夫婦の一方又は双方の財産と評価できるような場合には、株式や持分ではなく、例外的に法人名義の財産が財産分与の対象となる可能性もあります。
第三者名義の財産の取り扱いについては、こちらのコラムもご参照ください。
財産分与の割合について
財産分与割合は原則として2分の1ですが、例外的に財産分与の割合が修正されることもあります。
修正される具体的なケースについては、こちらのコラムをご参照ください。
いわゆる家事従事者(専業主婦・主夫)であって、病院経営に全く関与していない場合であっても、その事情のみをもって、財産分与の割合が修正される可能性は乏しいと思われます。家事従事者による家事労働という貢献の結果、獣医師が病院経営に集中できる環境が形成されていたと考えられるからです。
以上、獣医師の離婚について、婚姻費用・養育費・財産分与で押さえておくべきポイントについて解説してきました。
正当な結果を得るためには、できるだけ早い段階で事実関係や法律関係を正確に整理・理解することが重要です。
獣医師世帯で離婚問題にお悩みの方は、初回のご相談は30分間無料※ですのでお早めに当事務所までご相談ください。
※ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。