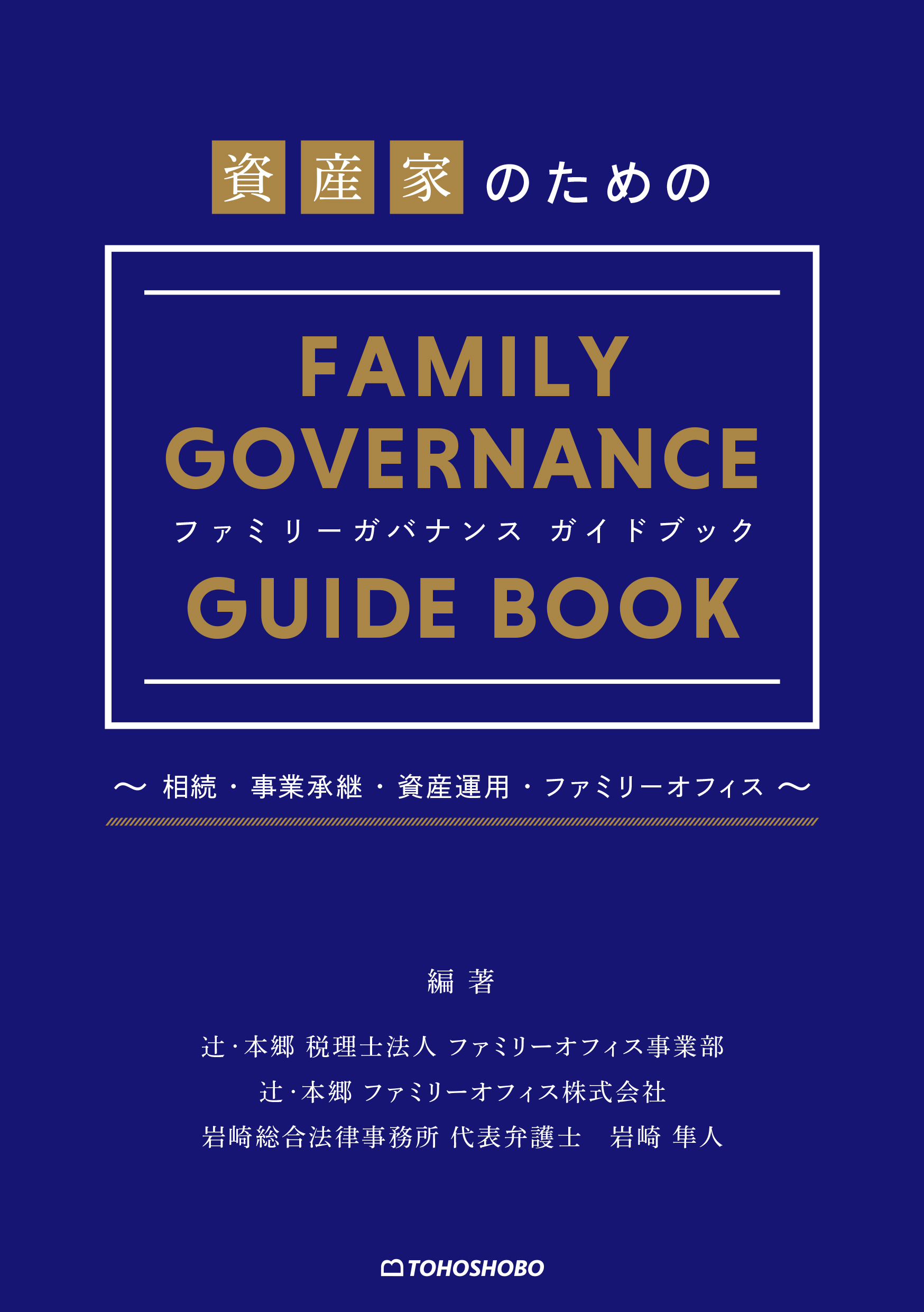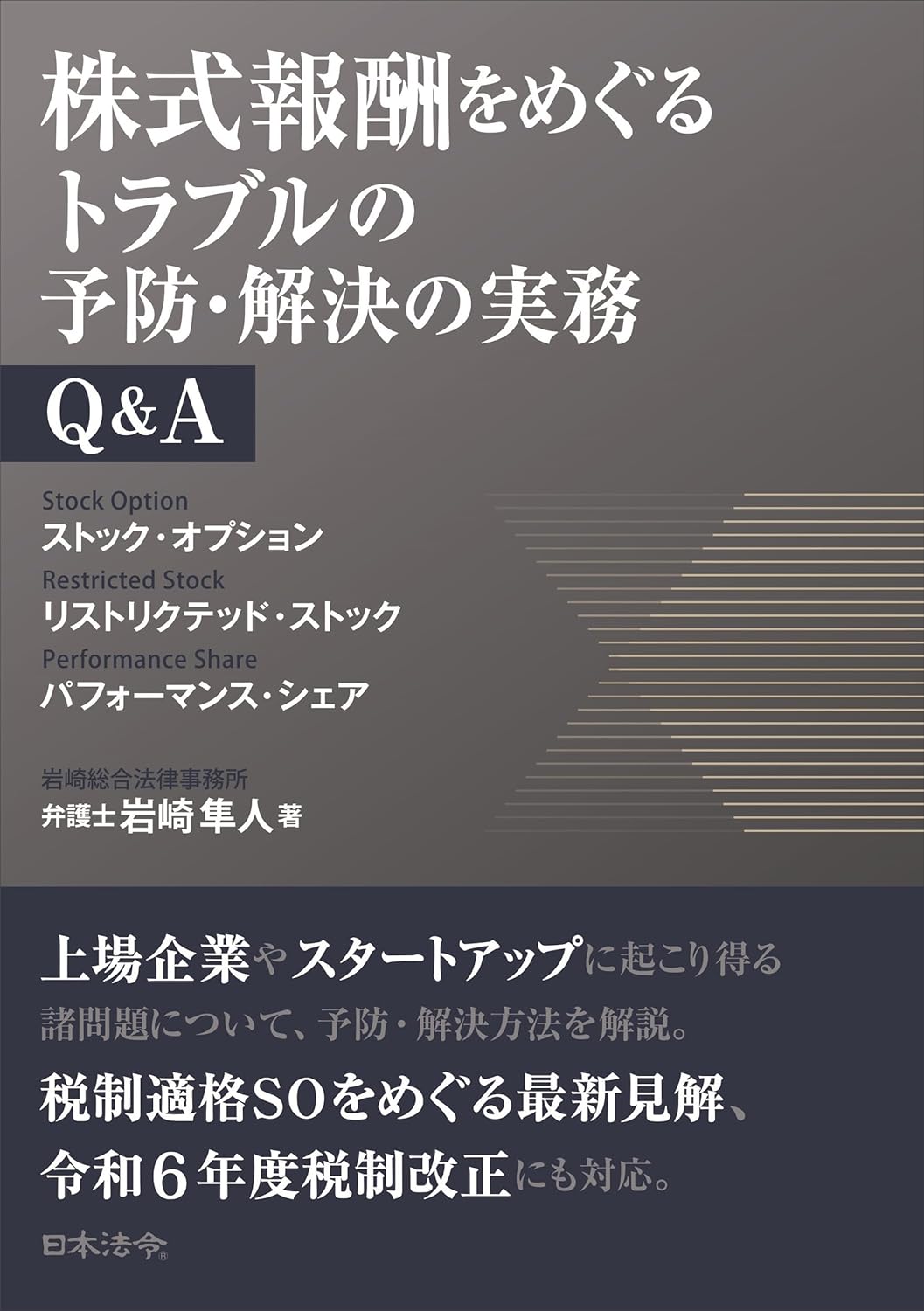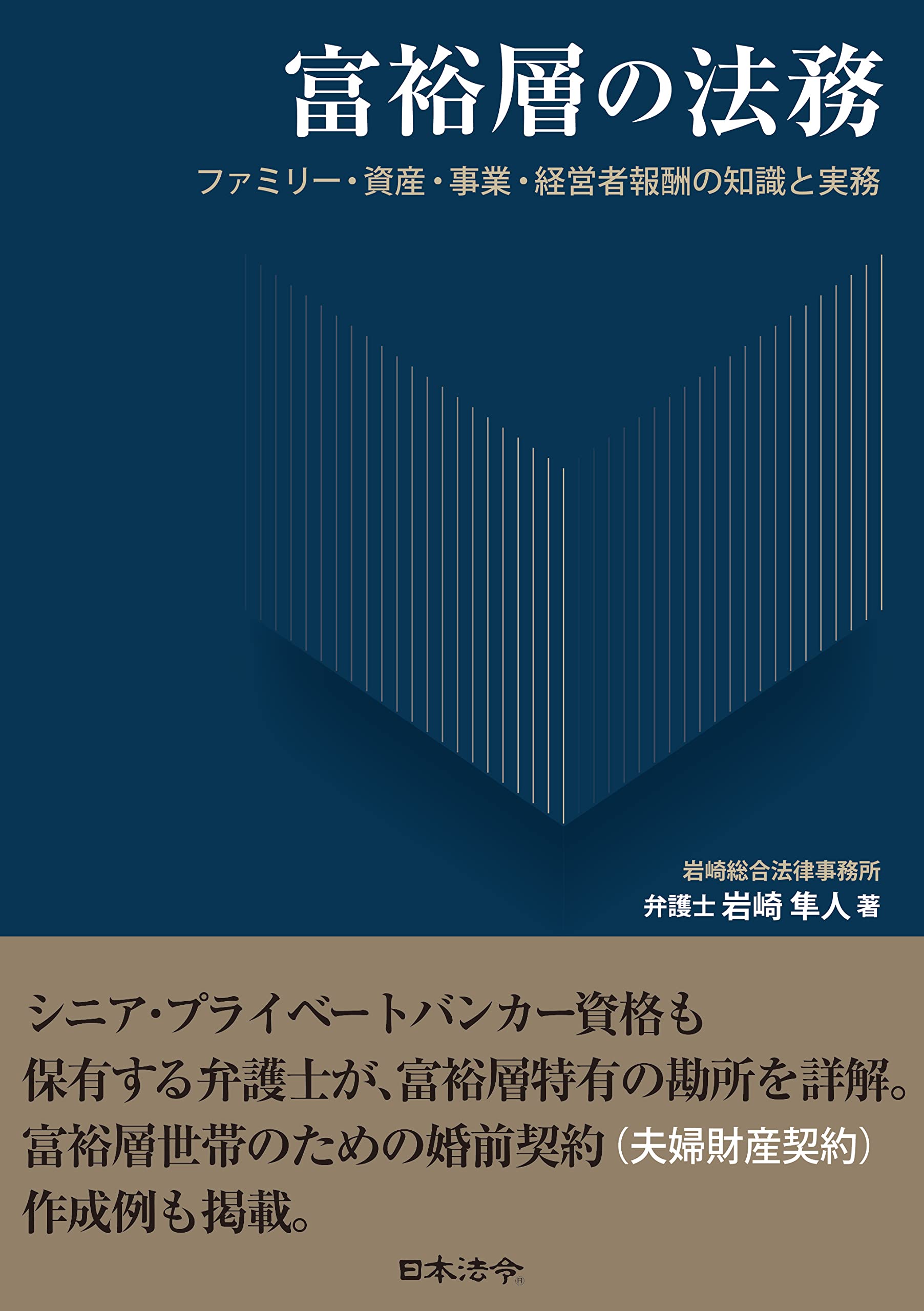2024年7月19日(金曜日)
経営者や不動産オーナーのための遺留分対策 〜家族が争わないように〜
会社経営者や不動産オーナーの相続の場面では、遺留分を巡る紛争に発展するケースがあり、遺留分対策は必須です。
大きな価値をもつ株式や不動産を特定の相続人に集中して承継させることで、他の相続人との不均衡が生じるためです。遺留分問題が生じると会社経営や家族同士の関係にも様々な問題が生じてしまいます。それは時に深刻なものです。
こうした問題を回避するために、このコラムでは遺留分問題の対策方法の要点を解説します。
既に相続が発生し遺留分が問題になっている場合はこちらの解説記事もご参照くださいませ。
・ 富裕層世帯の「遺留分」の問題 ~富裕層世帯の相続に特有のポイント~
・ 生前の遺留分対策に対抗する紛争
・ 富裕層世帯の遺留分を巡る「遺産の範囲」の問題
・ 資産家・富裕層世帯の「特別受益」の問題 ~ 遺留分関連の問題 ~
・ 中小企業経営者の相続紛争 株価の評価や生前対策を巡る問題
・ 不動産オーナー「メガ大家」の相続紛争 その予防法と解決策
岩崎総合法律事務所では、様々な世帯の資産承継をサポートして参りました。
遺留分でお悩みの方は、当事務所までお問い合わせくださいませ。
弊事務所では、富裕層法務サービス Legal Prime® を通じ、資産家、投資家、会社経営者などの資産・収入の多いお客様に対し多様なサポートを提供してまいりました。
これにより得られた知見の一部を書籍化し発売中です。ご興味をお持ちいただけましたら、書影をクリックして詳細をご確認ください。
目次
- Q1 遺留分の見通しを立てるため、侵害額の計算方法を教えてください。
- Q2 承継方法を工夫すると遺留分対策になるとのことですが、どのようなものでしょうか。
- Q3 信託を活用すると遺留分対策になるとのことですが、どのようなものでしょうか。
- Q4 ほか、承継方法を工夫する余地はありますか。種類株式を活用することはどうでしょうか。
- Q5 承継方法を工夫する余地がないのですが、遺留分放棄を活用することはできますか。
- Q6 自社株式を承継させるにあたって何か対策を取ることはできませんか。
- Q7 生前贈与が対策になり得るとのことです。12年前に、子どもに対して不動産を贈与しました。この不動産も、「遺留分算定の基礎となる財産額」を算定するにあたっての持戻しの対象となりますか。
- Q8 生前贈与を活用したいですが、どうも持戻しになりそうです。何か持ち戻しの対策はできますか。
- Q9 有償譲渡が対策になり得るとのことですが、有償であれば持戻しになることはありますか。
- Q10 生命保険が対策になり得るとのことですが、特別受益になることはありますか。
- Q11 死亡退職金が対策になるとのことです。もともと後継者に給付することとしています。死亡退職金も、特別受益として持戻しの対象となることがありますか。
- Q12 ファミリーガバナンスが遺留分問題の対策になるということですが、そもそもファミリーガバナンスとはどのようなものでしょうか。
- Q13 ファミリーガバナンスを遺留分対策に用いるにはどのように取り組めばいいですか。
- Q14 遺言書の付言も活用できますか。
- Q15 再婚したいと考えているのですが遺留分問題が気になり踏み切れません。どうしたらいいですか。
第1遺留分対策の全て 〜まとめ〜
第2遺留分を侵害するおそれの有無や、その程度の見通しを持つこと
第3相続財産の承継方法を工夫すること
第4承継方法を工夫しても、遺留分を侵害する形となってしまう場合の対策
第1 遺留分対策の全て〜まとめ〜
最初に経営者をはじめとする皆様が実施できる遺留分対策の全てをまとめてしまいます。
遺留分で争わないようにする方法は要するに以下のとおりです。
① まずは実施しようとしている承継計画が、遺留分を侵害するおそれがあるか、その程度はどのようなものかの見通しを持つことが重要です。
② その上で、そもそも遺留分侵害状態とならないようにできないかを検討するため、相続財産の承継方法を工夫します(承継財産の分割など様々な方法があります)。
③ 承継方法を工夫しても、どうしても遺留分を侵害する形とならざるを得ない場合には、遺留分放棄をするように促します。遺留分侵害状態をならざるを得ない場合の、実効的な解決方法の一つです。ただし、万能ではないので遺留分放棄だけでは不安定です。他の手法を講じることも必要です。
④ー1 被相続人が中小企業経営者であれば、もし遺留分の放棄が実施できない場合には、除外合意をするよう促します。除外合意とは、経営承継円滑化法に定めのある制度で、株式を遺留分対象の基礎財産から除外することを相続人全員で合意することをいいます。
④ー2 これも難しい場合には、固定合意をするように促します。固定合意とは、株式を遺留分対象の基礎財産に含めるもののその価額を推定相続人全員の合意時の価額で固定することをいいます。
⑤ 以上のいずれについても、推定相続人から協力を得られない場合には、早期の生前贈与を行って遺留分侵害額請求の対象になり得る時間的範囲外とするように調整したり、有償譲渡したり、生命保険や死亡退職金、信託の仕組みを利用したりすることを検討します。
そのほか、ファミリーガバナンスを構築することも効果的です。遺留分を争う動機を与えない仕組みです。
また、熟年結婚を検討されている場合などでは、そもそも結婚しないことも遺留分対策の一つとなります(入籍しない代わりにパートナーシップや事実婚を活用します。そうした方々は多いように感じます)。
このほか、やや特殊なケースですが、婚外子がいる場合にも遺留分が問題となります。認知されていない婚外子であったとしても、婚外子の側から認知請求を行うことにより、相続権を獲得して遺留分問題が生じる可能性があります。そのため、婚外子の存在も視野に入れた承継計画を検討する必要があります。
以下で解説していきます。

第2 遺留分を侵害するおそれの有無や、その程度の見通しを持つこと
Q1 遺留分の見通しを立てるため、侵害額の計算方法を教えてください。
遺言書等も含めた承継計画を検討するにあたって、まずは、遺留分を侵害するおそれがあるか、その程度はどのようなものかを見通すことが重要です。
そもそも、検討している承継計画が遺留分侵害状態を生じさせる可能性がないのであれば、対策を行う必要すらありません。
遺留分侵害額の算定式は、「遺留分額(遺留分算定の基礎となる財産額×個別的遺留分率)-遺留分権利者が受けた遺贈・生計の資本贈与の価額-遺留分権利者が相続で取得した財産の価額+遺留分権利者が承継する債務額」です。個別的遺留分とは、総体的遺留分(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外は2分の1)に法定相続分の割合を乗じたものです。
この算定の過程において、「遺留分算定の基礎となる財産額」が争いになりやすいです。
遺留分算定の基礎となる財産額は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額です。
そして非上場株式や不動産は時価を正しく評価することが難しいです。それぞれの立場による偏向性が介入してしまうことは不可避です。非上場株式や不動産の評価方法についてはこちらのコラムもご参照ください(遺産の評価を巡る問題② ~非上場の自社の株式の評価~、遺産の評価を巡る問題① ~不動産の評価~)。
また、評価は相続開始時点(今現在の時点ではないということ)において行われるものです。このため遺言書等といった承継計画作成時点において遺留分侵害のおそれの有無と侵害額についての見通しを持つことは必ずしも容易ではありません。見通しを持つにあたっては、あり得る評価幅と将来の評価額について保守的に考えておく方が無難です。
「遺留分算定の基礎となる財産額」が争いになりやすいもう一つの理由は、持戻しをする贈与の範囲やその価額に解釈を要する問題があるためです。相続人以外の者に対する贈与については、原則として、相続開始前の1年間のうちになされたもののみが遺留分算定の基礎となる財産額に算入されます(民法1044条1項)。相続人に対する贈与は、特別受益(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与のこと)についてのみになりますが、その期間は、原則として相続開始前の10年間のうちになされたものとなります(民法1044条3項)。

第3 相続財産の承継方法を工夫すること
Q2 承継方法を工夫すると遺留分対策になるとのことですが、どのようなものでしょうか。
遺留分侵害額請求への抜本的な対処方法の一つは、そもそも遺留分を侵害しないように遺言書を作成すること(そして遺留分を侵害するものでないことを遺言書上も明確にすること)です。
他の遺留分権利者に株式以外の十分な財産を相続・贈与させることにより、そもそも遺留分侵害自体を生じさせない方法があります。
他にも、会社の資産・事業にはコアとなるものとそうでないものがあることを踏まえた対策があります。
つまり、コアビジネスに直接関連しない金融資産や不動産を、金融資産運用業や不動産業として切り出して、後継者でない者に承継させることで、遺留分侵害額請求に対応できる可能性があります。
以上は伝統的な遺留分対策ですが、信託を活用することも考えられます。
Q3 信託を活用すると遺留分対策になるとのことですが、どのようなものでしょうか。
そもそも株式にしても不動産にしても共有にしてしまえば遺留分問題は生じないわけです。
しかし、共有にすれば会社のガバナンスや不動産の管理処分に悪影響が生じかねませんし、それは特に後世代に行けば行くほど深刻化します。そうしてトラブルになってしまっている創業家や世帯が実際にあり、共有は避けるべきと提案する専門家や金融機関は多いです。
このため、共有にはせず単独所有させるケースが多く、しかし、そうすると遺留分の問題は生じてしまうわけです。
そこで信託が活用されます。
つまり、株式や不動産の価値を全ての相続人に帰属させつつ、ガバナンスや管理処分に悪影響を生じさせない仕組みを導入するため、その主たる方法として信託が活用されるのです。
例えば、株式や不動産を信託財産に組み入れ、その価値(受益権)を遺留分を侵害しないように相続人に承継させるものとし、管理や処分は後継者に委ねます。その相続人死亡時にはその後の世代へ分散することのないよう受益権を消滅、あるいは集中させるようにします。
信託は相当長期間運用管理されなければならないものです。このため将来を見通した仕組みでなければならず、将来への想像力を働かせて慎重に設計しなければいけません。信託法や会社法の制限もあり、詐害的な信託だとその効力が否定される恐れもあります。また、信託は契約を持って行われるものです。
弁護士の助力は不可欠でしょう。
Q4 ほか、承継方法を工夫する余地はありますか。種類株式を活用することはどうでしょうか。
また、会社またはファミリーオフィス(ファミリーのための資産管理会社)そのものの株式について、議決権等ガバナンスに影響しうる権利は制限しつつ、財産権としての株式を承継させるといった工夫の余地もあります。
この場合には非後継者の死亡時等一定の場合に株式を一方的に取得できる仕組みなど株式分散防止の実効的な仕組みが不可欠です。
種類株、株主間契約、定款、ファミリー契約(親族間契約)を活用します。信託を併用することも考えられます。

第4 工夫しても、遺留分侵害の形となってしまう場合の対策
Q5 承継方法を工夫する余地がないのですが、遺留分放棄を活用することはできますか。
遺留分を侵害する形とならざるを得ない場合、遺留分侵害額請求への抜本的な対処方法の一つが、遺留分の放棄です。
相続開始「後」の遺留分の放棄は、遺留分を行使しないというだけであり自由に行うことができます。ただし、それを求めようとするにあたっては、利益相反状況にある後継者と遺留分権利者同士での交渉となるため、難航しやすいです。
他方、遺留分の放棄は相続開始「前」(遺言者が生前中)にも行うことができます。
遺留分権利者たるべき推定相続人自身が放棄の意思を示さなければならず、そのためには説得をしなければいけません。
この点、事前放棄であれば、被相続人が主導して行う点や、利益相反状況にないリーダーたる親主導で進められる点から説得しやすいものと言えるでしょう。
紛争を抜本的に解決しうる効果的な手法ですので、積極的に活用を検討します。
なお、相続開始前の遺留分放棄を行うには、家庭裁判所の許可が必要です。
許可のためには遺留分権利者の真意に基づくこと、放棄に客観的な合理性があることとされます。
ただし、いずれの年も90%以上は許可されており、許可されないといった事態はほとんど生じないものといえるでしょう。
ただし、遺留分の放棄は万能ではありません。
後になって、その許可を取り消すことで、遺留分の放棄を無かったことにできるのです。
もちろん遺留分の事前放棄の撤回を任意に行うことはできないのですが、申立の前提となった事情が変わり、遺留分を放棄することが不当となった場合には、放棄許可の審判が取り消される可能性があります。
このため、ほとんど許可されるからといって漫然と進めてはいけません。遺留分放棄の許可の要件とされているものを確実に満たすことを確認しておく必要があります。
例えば、遺留分権利者の真意に基づくことという要件との関係では、遺留分権利者が自由な意思で放棄しているかどうかが重視されます。遺留分の放棄に客観的な合理性があるかという要件では、相続法の理念に反しないかが重視されています。
これら重視されている要素をあらかじめ確認しておくことで、後になって、「申立の前提となった事情が変わった」、「遺留分を放棄することが不当となった」といった展開にならないよう気をつけておくべきと言えます。
しかし、それでも許可取り消しの可能性を完全に払拭はできません。
このため、遺留分の事前放棄が実施できたとしても、他の手法も検討しておく方が安全といえるでしょう。
Q6 自社株式を承継させるにあたって何か対策を取ることはできませんか。
遺留分放棄は遺留分を一切主張できなくなるものです。権利がゼロになることを意味します。
このためなかなか説得が難しく同意が得られないことがあります。
そこで会社が中小企業の場合には、自社株式のみを遺留分侵害額請求の対象としないことへの同意(除外合意)や、当該株式の評価額を合意時に固定することへの同意(固定合意)の活用余地が出てきます。
遺留分放棄のオールオアナッシングの問題にしないものですし、付随的な条件を定めることもでき柔軟な調整も期待できます。
前記のとおり、除外合意により、当該株式が遺留分侵害額請求の対象とならなくなります。固定合意により、遺留分侵害額請求との関係で、当該株式の評価額が合意時に固定され、その後の上昇分は考慮されなくなりますし、その評価方法を巡る争いもなくなります。
除外合意と固定合意は二者択一のものではないため、併用することもできます。例えば、後継者が贈与等により取得した1,000株のうち600株を除外合意の対象とし、残りの400株を固定合意の対象とすることもできます。
除外合意や固定合意に付随して、そのほかの合意を行うこともあります。
例えば、後継者が株式を取得するにあたっての納税資金の確保のための金銭や、会社名義で保有しているものではないものの事業に用いている資産を、後継者に付与しておくべき場合には、一定の手続きを踏むことでそうした財産の全部又は一部について、その価額を遺留分算定基礎財産に算入しない旨の定めをすることもできます。この合意の対象とすることができる財産の種類や額に制限はありません。
Q7 生前贈与が対策になり得るとのことです。12年前に、子どもに対して不動産を贈与しました。この不動産も、「遺留分算定の基礎となる財産額」を算定するにあたっての持戻しの対象となりますか。
ご質問のケースは特別受益に該当します。このため持戻しの対象になってしまうものではありますが、2018年の民法改正によってその期間は、原則として相続開始前10年以内のもののみと限定がかかりました(以前は期間制限なし=無制限でした)。
こうした法改正を受けて、早期の生前贈与が遺留分対策になる面があるのです。
ただし、例外があります。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときには期間の制限がありません。つまりいかに早期に取り組んだとしても遺留分対策にならない場合があるということです。
この例外に当てはまってしまうかは、いつ行われた贈与か、それが損害を加えることを知ってなされたものかどうかによって、持戻しの対象となるかどうかの判断が分かれます。
「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」の意味について、裁判所は、①当事者双方が、贈与財産の価額が残存財産の価額を超えることを知った事実ばかりでなく、②なお将来被相続人の財産に何ら変動がないことの予見の下に贈与があった事実まで必要と判示しています(大判昭和11年6月17日民集15巻1246頁)。①は贈与当時においてみるべき財産が残されているかという観点であり、②は被相続人の年齢、生活状況、収入等の具体的かつ客観的な事情を基礎として、将来において財産が増加する見込みがあったかどうかで判断されます。なお、誰が遺留分権利者となるかまでの認識は必要ないものと考えられています。
ご質問のケースでは、原則として、子どもに贈与した不動産は持戻しの対象となりません。ただし例外として、ご質問者と贈与を受けた子どもの双方が、他の遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与を行った場合には、当該不動産は持戻しの対象となります。
Q8 生前贈与を活用したいですが、どうも持戻しになりそうです。何か持ち戻しの対策はできますか。
10年以内の特別受益など遺留分侵害額請求の対象になる可能性がある場合には、遺留分侵害額請求権行使先の相手の順番の指定が役に立つ場合があります。
まず、遺留分侵害額請求の対象に贈与によるものと遺贈によるものがある場合には、遺贈を受けた者が先に対象になります(民法1047条1項1号。この順序は遺言によって変更することはできません)。
遺贈による受遺者が複数ある場合で、遺言者が遺言で順序を定めている場合には、その定めに従います。
生前贈与が複数ある場合、その生前贈与が同時に行われたものであれば、遺言者が遺言で順序を定めている場合には、その定めに従います(民法1047条1項2号ただし書き)。
同時に行われた生前贈与でない場合には、新しい贈与から順次前の贈与に対して受贈者が遺留分侵害額請求の対象となります(民法1047条1項3号。同時になされたものではない生前贈与については、遺贈と異なり遺留分侵害額請求の対象とする順序を指定することはできず、単純に時間的先後関係に従って順序が決まります)。
このように遺留分侵害額請求は、
・優先順位の遺贈
→劣後順位の遺贈
→(同時実施の場合の)優先順位の生前贈与
→(同時実施の場合の)劣後順位の生前贈与
→新しい生前贈与
→古い生前贈与
の順番になされていき、それぞれの受遺者、受贈者が対象となって、遺留分侵害状態を解消していくことになります。
こうした仕組みを踏まえ、様々な資産を生前贈与・遺贈する場合には、遺留分侵害額請求の影響を押さえ込むべき資産として重要なものから順に生前贈与していき、遺贈によるとしてもそれには先に侵害額請求の対象にするものと、それに続くものを遺言書にて指定しておくことを検討します。
なお、持戻し免除は遺留分問題の対策になりません。
持戻し免除とは、被相続人が行う特別受益を持ち戻す必要がないとする旨の意思表示のことであり、遺産分割協議の場面では重要な意味を持つものですが、遺留分の場面では制度として認められておりません。同じく特別受益に関係するものですので誤解しやすいかもしれませんが別物です。遺留分では持戻し免除が対策にはならない点、注意しましょう。
Q9 有償譲渡が対策になり得るとのことですが、有償であれば持戻しになることはありますか。
有償で譲渡したものについては持戻しの対象にならず、遺留分算定の基礎財産に含まれないことが原則です。
もっとも、この対価が時価として相当ではない場合、すなわち不相当な対価をもってした有償行為である場合で一部生前贈与の性質が含まれてしまう場合には、持戻しの対象となる場合があります。当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされてその限りで持戻しとなります。
そこで、生前に有償譲渡する場合には、その対価が相当なものであることや、少なくとも当事者双方においてその対価が相当と考えるだけの正当な根拠があることを確認・整理し、遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでないという状況を整理しておく方が良いです。
なお、その対価を後継者が用意するために、被相続人が便宜を図る行為が生前贈与に該当すると、この便宜を図った行為について前記の生前贈与の問題で検討されることになるため、資金準備にあたっても注意が必要です。
Q10 生命保険が対策になり得るとのことですが、特別受益になることはありますか。
生命保険金は、保険会社と遺言者との第三者のためにする契約により取得したものであるため、相続で取得したことにはなりません。
そのため、生命保険金は、遺留分の算定における特別受益に算入されず、結果的に生命保険を利用しなかった場合と比較して後継者以外の推定相続人の遺留分が縮減します。
もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となる点に注意が必要です(最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)。
特段の事情は、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきとされます。
裁判例では、保険金額が遺産総額に占める割合が61%に及ぶ場合に持戻しの対象になるとしたケースがあります。
Q11死亡退職金が対策になるとのことです。もともと後継者に給付することとしています。死亡退職金も、特別受益として持戻しの対象となることがありますか。
まず、相続財産であれば遺留分算定基礎財産に当然含まれるため、そもそも死亡退職金が相続財産かどうか問題となります。
これについては、死亡退職金に関する給付規程において、死亡退職金の受給権者が特定している場合には受給権者の範囲・順位が相続法の規律と無関係に定められているため、受給権者が固有の権利として取得するものとされるものとして、相続財産ではないという考え方もあります。一方で、この考え方に従えば、規程の内容が「相続人」に支給するという内容である場合には相続財産であると解釈される可能性があることを意味します。したがって、死亡退職金の相続財産性すなわち遺留分算定基礎財産に含まれるかどうかは、個別事情によって死亡退職金の性質を検討しなければなりません。
仮に相続財産ではなく遺留分算定基礎財産に含まれないことが原則だとしても、生命保険金と同様の解決をすべき場合があるという見解もあります。すなわち、受給権者である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし是認することができないほど著しいものと評価すべき特段の事情がある場合には、遺留分算定基礎財産に含めて計算すべきというものです。
死亡退職金が遺留分との関係でどのように取り扱われるかの解釈は必ずしも確定的なものはなく、個別事情によってその扱いが変わります。
そのため、遺留分対策として死亡退職金を活用するケースでは、過去の裁判例をもとに死亡退職金に係る給付規程の作成と運用管理を行うことが重要となります。

Q12 ファミリーガバナンスが遺留分問題の対策になるということですが、そもそもファミリーガバナンスとはどのようなものでしょうか。
ファミリーガバナンスとは、「家族」を「統治」する法的な仕組みです。
ファミリーの現トップが、現在及び数世代先の未来のファミリーのために判断するもので、主に「ファミリーの事業、資産の管理運用」や「ファミリーを円満に保つ仕組み」についてルール化するものです。
その仕組みの中では一定の統治基準やルールに沿った行動をする限りでは恩恵が与えられ、そうでなくては権利・利益の剥奪やペナルティが生じるといった制裁が生じます。
こうした仕組みの中で遺留分問題を起こさせないようにすることが効果的である場合があります。
Q13 ファミリーガバナンスを遺留分対策に用いるにはどのように取り組めばいいですか。
ファミリーガバナンス全般の導入方法はこちらをご参照ください。
遺留分との関係では、遺留分というものの意義やなぜ遺留分を問題にしてはいけないかを話し合うことから始まります。
そこでは遺留分問題を生じさせることが中長期的に見てファミリーの損失になることの説明や、遺留分権利者にとってもメリットのあることを説明して理解を得ることを試みます。
そうして一定の理解が得られましたらファミリー憲章(家族憲章)や、ファミリー契約(親族間契約)、ファミリーオフィスの仕組みに遺留分を問題にさせないための取り決めを定めて法的効力を持たせます。
例えばファミリー憲章(家族憲章)に以下のような内容を書き入れることが考えられます。
ファミリーは後継者が会社の株式を承継したことを原因として自らの遺留分が侵害されたとしても、これに係る遺留分侵害額請求は目先の自らの経済的利益の確保のみを目的とする短絡的で利己的な行為であり、自らの中長期的経済的利益を放棄するだけでなく、ファミリー全体及び後世代の財産を毀損する行為であるから行ってはならない。
後継者から求められた場合には、自社株承継の前の時点においても、遺留分侵害額請求を制限するための措置(除外合意や遺留分侵害額請求権の事前放棄など)に協力し、あるいは実行しなければならない。
Q14 遺言書の付言も活用できますか。
遺言書の付言とは、遺言書において、法律行為ではないものの、遺言書の内容の背景やニュアンスを記載して、遺言者の意思を受遺者に伝え、相続人間の紛争を回避することに役立てるものです。
遺留分侵害額請求権の行使が避けられない可能性が高い場合には、例えば生前贈与(特別受益)の内容や資産評価額を遺言者の立場から明確に整理し記載しておくことで、遺留分侵害額請求で生じる複雑な論点を解消し、紛争の深刻化を抑えるように工夫することが考えられます。
Q15 再婚したいと考えているのですが遺留分問題が気になり踏み切れません。どうしたらいいですか。
再婚すれば配偶者に遺留分が生じます。
熟年結婚のようなケースだと、その遺留分が実現する可能性を具体的なものと感じることが多く、自分が今まで得てきた資産の25%が入籍したばかりの相手に承継されることに抵抗感を覚える方は多いです。
このような方は入籍しないことが抜本的な対策となります。
そうはいっても夫婦の関係にあることが重要であることも多くあり、その点で事実婚、パートナーシップを活用します。
また、遺言書や信託を持って、自分が先だった場合の相手の生活が困らないようにすることもできます。
岩崎総合法律事務所ではこうしたパートナーシップのサポートもしています。
パートナーシップはこちらをご参照ください。
・ 資産家カップルの事実婚・パートナーシップ ~あえて結婚しないという選択~
以上、経営者や不動産オーナーの問題を中心に、遺留分対策についてよく相談に上がる論点や誤解されがちな論点にについて解説してきました。
もし、お悩みの方は、初回のご相談は30分間無料※ですので、少しでもお困りの際にはお気軽にご相談ください。
※ ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。